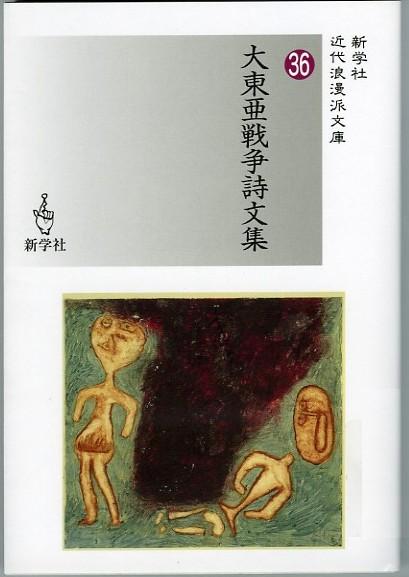
Back (2008.04.02up�@)
�u�c�����Ȃɂ��ā@�푈���̎��Ӂv
����18�N�x�l�G�h�w����(2006�N10��21�� �� ������w���:�_�ˏ������q�w�@��w)�ł̍u���^�����ƂɁA�����A�lj����{�������̂ł��B
1.����������
�@�͂��߂܂��āB�����Љ�ɂ��Â���܂������q��w�}���ق̒����N���Ɛ\���܂��B
�@�킽���͂����̕���4�N�x�̎l�G�h�w����ŁA�u�l�G�v�̕ҏW���l�ł������c�����Ȃ̐t����̂��Ƃɂ��āA�������\�������Ē����܂����B �ł��̂ł��̏�ł��b������͓̂�x�ڂƂȂ�܂��B���݂́u�l�G�E�R�M�g�E���W�z�[���y�[�W�v�Ƃ��ӃC���^�[�l�b�g�̃T�C�g��ʂ��܂��āA ����O�Ɋ����l�G��R�M�g�̎��l�����A���ꂩ��ŋ߂͂܂��A�����̌̋��ł���܂����̊����l�����ɂ��āA�c�q�Ƃ��ӂ��A�Љ�����s���Ă���܂��B �{���͑�w�����ł��L�����l�ł��Ȃ������̂₤�Ȏ҂��A�u���̕��ł��b������͙̂G�z�ɂ�����Ǝv�ӂ̂ł����A�ʂɃ��C���̉��҂���邩��Ƃ��ӂ��Ƃł�������������ł��B 30���ʂ̂͂������Ԃ������Ղ肠��₤�Ȃ̂ŁA���i�l�O�Řb�����邱�Ƃ̂Ȃ��������ʂ����Ď������ԂɊ��ւ�₤�Șb���ł��邩�ǂ����A���R����搶�̎�O�A �����ւ�ʖڂȂ��₤�Ȑ\����Ȃ��₤�ȋC���ŗ����Ă���܂��B
�@�Ƃ�����A�����ߍ�������Ɏv�Ђ܂����Ƃ́A�l�G�h��R�M�g�̐l�X���J���������{�̝R��̐����A���B�ȍ~�̐���͂ǂ�ȋ�Ɏp���ł䂭�̂��炤���Ƃ��ӁA �^��Ƃ��ӂ��s���ł���܂��B�䑶�m�̂悤�ɃC���^�[�l�b�g�ɂ���āA���̂₤�Ȏ҂ł��ւ����̔��M�҂ƂȂ蓾��₤�ɂȂ������ʁA ����܂Ŋw�p�I�Ȍ�����Ղ�������w�ɂ�����ߑ㕶�w�����Ƃ��ӂ��̂��A�g�D�I�ɂ����@�_�̏�ł���ϓ���Ƃ���ɗ�������Ă��₤�Ɏv�Ђ܂� (�������̐E��ł͍����w�Ȃ��p�~����A�~�ς��ꂽ�ߑ㕶�w�W�̐}�����Y�͎������R�̏ɂ���܂�)�B �����ĝR��̎���҂Ɠǎ҂��Ƃ�܂����j�I�Ȗ��Ƃ��܂��ẮA���{�̎��R��l�S�ɂ��āA�ǂ�ǂ�ߋ��������ł��Ȃ��₤�Ȍ`�ŁA�Ȃ����Â��ɕώ����ė��Ă��Ƃ��ӏ�����Ǝv�Ђ܂��B �����͂������ӈӖ��ł͌���Ɍ���邱�Ƃ̂Ȃ��Ȃ������j�̑��ʂɂ��Ă��b�����邱�ƂɂȂ邩�Ǝv�Ђ܂����A��낵������Ђ�\�グ�܂��B
�@�b�����ǂ��܂����A�O�\���܂������e�́A�_�W�̑�W(����5�N)�ɂ܂Ƃ߂܂��āA���̌�A ���l���₵��������L��|�������w����_�x�Ƃ��ӎ��Ɣł̖{�̂Ȃ���(����7�N���ƔŁA����100��)�A ���Ƃ��Ď��^���܂����B���݂̓T�C�g��œǂނ��Ƃ��ł��܂��B���ꂩ�痂�N�̕���8�N�ɂȂ�܂����A ���l�̎��Ƃ��W�������w�c�����Ȏ��W�x���Ђ�芧�s���邱�ƂƂȂ�܂���(����300��)�A���̕ҏW�ɂ��g�͂�܂����B ���l�̎��Ƃ��W���������ŗՂ�i�W�������̂ł����A�y�[�W���̐������đS���W�Ƃ��邱�Ƃ���߂���܂���ł����B�������Ȃ���A ���s���ꂽ���W�Ɛ�O�̏E�⎍�𒆐S�ɐ����āA���̎������I�������Ƃɂ��܂��āA���l�c�����Ȃ̐��U����Ղ����ł́A�p���Ď��j�I�ȑ��ݗ��R������������e�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���Ă���܂��B ����͂܂��c�����͏��Ȃ��炠��Ǝv�Ђ܂��̂ŁA�l�G�h��R�M�g�̎��l���ꂩ����{�Q�֔h�ɋ������������̕��́A ���X����(\9000)�ł������Њ��s��̒����Ђ܂Ŗ�Ѝ��͂��Ē�����Ǝv�Ђ܂��B�ȏ��`�ł��B
�@2.�w�哌���푈�����W�x
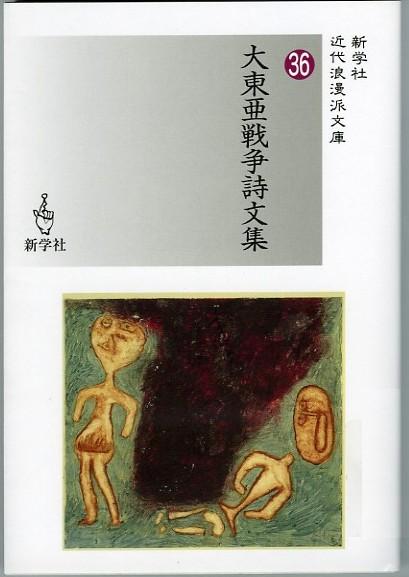
�@���̏W�܂�͎l�G�h�w��Ƃ��ӁA�G���u�l�G�v�ɋ��������l�B�A�܂菺�a�����̌��ꎍ�ɂ����Ēm�I�ʼn���Ȏ������m�������A �u�l�G�h�v�ƌ㐢�Ă��₤�ɂȂ������l�B�ɂ��Ę_�����ӏ�Ȗ�ł�����ǁA�c�����ȂƂ��ӂ̂́u�l�G�v�̏���(15��)����̓��l�ł����A������������A �G���u�R�M�g�v�̑n�����l�ł���܂��B�����Ċ����̋��_�Ƃ͉]�ւ�����́u�R�M�g�v�̕��ł��āA���l���g���u�l�G�ɏ����Ƃ��ɂ͂悻�s���ŗՂނ₤�ȂƂ��낪�������v�Ƙb���Ă���܂������A ����������Ñ��M�v����\����Ƃ���̏����u�l�G�h�v�̎��Ƃ͏����ѐF���قɂ��鎍�l�ł���܂��B��������������l�G�̓��l�ɂȂ��Ă�钆������������ł��B �ނ���������́A�J�e�S���C�Y�����ۂɂ́A�l���h�Ƃ��ӂ��A����S���́u����v�̒��ԂɎQ������邱�Ƃ������̂ł�����ǁA�ҏS�Ƃ͖����̐l�ł����A�����ɚ�܂��Ă��܂Ђ܂��B ����c�����Ȃ́A�_�ی����Y�ƂƂ��ɁA���������S�����Ƃ͒Ñ��M�v�ƎO�l�Łu�l�G�v�̕ҏS�ɂ����Â��͂邱�ƂɂȂ�܂����B�����ĕۓc�o�d�Y��ɓ��×Y�①���L��Y�Ƃ������l�B���A �u�l�G�v�̌㔼����(53�����)���l�ɎQ�����ĎQ��܂����A���̌Ăѐ��ƂȂ������l�̂₤�ɍl�ւ��Ă���܂��B�����Ƃ��ւu�l�G�v��푈���q�������������Ă������A ���{�Q�֔h(�ɂق�낤�܂��)�̎��l�̈�l�Ƃ��āA�F�m�����Ă�邩������܂���B
�@���ĊF����͌��݊��s�����u�ߑ�Q���h���Ɂv�Ƃ��ӑp���͂����m�ł������B �ۓc�o�d�Y�̑S�W��ҏW���܂����V�w�Ђɂ�銧�s�ł����A���̈���A�w�哌���푈�����W�x�Ƃ��ӈꊪ�ɂ��̂��ѓc�����Ȃ̍�i�����߂��邱�ƂɂȂ�܂��āA��⑰�̋����āA �������^���̑I������邱�ƂɂȂ�܂����B���ꂪ����8���ɏo���オ��������̈���ł����A�Ȃ��߂܂��ƁA���e�́A�����̑��Ő펀�E�����E���Y���ꂽ�l�X�ɂ��u�哌���푈�}���r�W�v�B �����O�����ɒu���A�E���̑啨�ł���O�Y�`��A�e�R�����䗼�l�̉̏W�����ɒu���A�����ēc�����Ȃ̍�i��24�Ҏ��߂��Ă�܂��B�������čŌ�ɁA ��胍�}���h�̑I��ł�������v���l�A���c�W�A�R��O���̃A���\���W�[�Œ��ߊ���Ƃ������\���ƂȂ��Ă���܂��B���ۂɓǂ�Œ�����킩��܂����A �O���̉̏W�����ƌ㔼�̎��W�����͂��Ȃ�قȂ�����ۂ�ǎ҂ɗ^�ւ�Ǝv�Ђ܂��B���ɍŌ�̑��c�W�ƎR��O���̕����́A�w�哌���푈�����W�x�Ƃ��ӂ��̂��̂����^�C�g���ɂ͂����͂Ȃ��A �]�R�ȑO�̎Ⴋ���̍�i�Q���������߂Ă���A�ǂ����Ă��̂₤�ȑI���ƂȂ����̂������m�肽���̂ł����A�c�O�Ȃ��ƂɕҏW��L������܂���B �ނ��ޓ����푈���ł͂Ȃ������̝R����I�ꂽ���Ƃɂ��ẮA���ꂪ��ʏ��X�ɂ����Ă܂Ƃ܂��Ď����Љ���ŏ��̏�ł��邱�Ƃ��v�ւA�ނ���K���Ȃ��Ƃł������₤�Ɏv�Ђ܂��B �����ōŏ��ɁA�c�����ȂƋ��Ɏ��^���ꂽ�A���̓�l�̃}�C�i�[�|�G�b�g�ɂ��ď����G��Ă��������Ǝv�Ђ܂��B
�@3.���c�W�ƎR��O��
�@���c�W�ɂ��Đ\���܂��ƁA���O�����ɏI�������W�Ɂw�q�u�x�Ɓw���{�V�I�x�Ƃ��ӏ]�R���̍�i������̂ł����A���Ƃɂ��w���{�V�I�x�Ƃ��Ӓ��҂̐푈���́A �ނ���n����Ȃֈ��Ă��莆�̂Ȃ��ŁA�����́A
�u�����̍����̎��͂̂���Ȃ��Ă��A���̎������͂̂���Ƃ��ӊm�M������(���a18�N4��16���A���q�����͂���)
�Ƃ��ӂقǂ̎����̌��t�ŗՂ݂Ȃ���A���ǂ�
�u���{�V�I�͂قڕs�����Ƒ�����B���̂Ƃ���d���̕����������낭��B���{�V�I�s�����͂₤�₭���M��₽�Ǝv�Ђ����B(���a18�N6��20�����͂���)�v
�Ƃ������Ɏϋl�܂��Ă��܂�����i�ŁA���̓�T�Ԍ�ɔނ͐펀���Ă��܂Ђ܂�����A�܂�s�{�ӂȂ������M�Ƃ����Ă悢��i���Ǝv�Ђ܂��B�`���̈�߂���A
�@���̈�
�킪��ɐ��܂�҂ގq��敷���A��������̌�q�̂����߂܂��L��������̚��́A���͂��߂ē��Z�S�N���o�āA�Ђɖ����Ȃ�����ɂ��ЂʁB���ƂւΖk���̐����҂�A ��̌t�𐁂����ӂ����Ƃ��A�ĉp�̓A�W�A��i�����҂�A�ЂɗזM�������̕����r���킪�_���͂ЂɊ�@�ɋy�ׂ�B
�Ƃ�������ŁA�ނ̎t���ł������ɕ������F���A�Î��L��|�Ă��ď��������W�w���̍c�q�x�A����ɕ���ē��ĊJ��ȗ��̗��j���A ���ɂ����葖����悤�Ƃ�����i�ł���܂��B���ꂪ����́w�哌���푈�����W�x�ɂ͏Љ��Ă���܂���B���ɁA �o�����O�Ɋ��s�������Ɣł̏������W���w�����x(���a16�N3��)�A���̖`��������\����A ����ɘA�Ȃ�Ⴂ���̍�i�������̂��Ă���܂��B������������₤�Ȍ��t�ŁA�Ώۂ̗֊s�����ǂ������ɕ`�����Ƃ��郍�}���`�b�N�ȁA���́u�����v�Ƃ��ӎ��������ǂ�ł݂܂��B
����
�������ɂ�邭
�K�N�F�̎����Ȃ����₤��
�����������邻�̂�����
���������ׂĂ䂭�c�c�c�c
�����̐ڕ�(�����Â�)�̂��Ƃ�
�����ǂ���Ȃ�������ƃA���W�F���X��
�₳�����F��������ӂƂ�
���������ׂĂ䂭�c�c�c�c
������͂��Ȃ��Ƃ��₷��
���������݂ɂ��邻�̔�
���̔����Ȃ����₤�ɖ��݂�₤��
���������ׂĂ䂭�c�c�c�c
���̋����킩���E�F�[���̂����
�����ꂽ�Ƃ������ʂ����
���������̂��͂����ƂȂ�
���������ׂĂ䂭�c�c�c�c
���̔����܂낢���ɂ킩���Ȃ݂�
���r�[�̂����߂������ڂ�����
������ɏ����Ă䂭�܂ǂ�݂̂ЂƂƂ���
���������ׂĂ䂭�c�c�c�c
���ɂ悭�݂邱�̂ЂƂƂ�
���̂Ȃ�����݂��Ă����H���̔���
�������ׂ��Ă䂭�����
���������ׂĂ䂭�c�c�c�c
�@���͓�����̗��������ƕ��я̂���ꂽ�A�炿�̗ǂ��A���n�ȁA�s��h���}�����l�̖ʖڂƂ��������̂����@�Ƃ��Ă���܂��B�ނ��吳�l�N����̔ނ́A ��N��y�ɂ����闧�������̑@�ׂ�����������₤�ȂƂ��낪�����āA�ނ��됔�N(4�N�ł���)��y�ł���c�����Ȃ̎��́A�����̍����⊣�����F�ʂ̕��ɂ��e�߂��o���Ă������₤�ł���܂��B �ނ���n����t���Z�����g���ď����������u�c�����Ȏ��̂��Ɓv�Ƃ��ӈꕶ�ɂ́A����ȏ������Q�������菑������Ă���܂��B�l�b�g��ɂ��サ�Ă���܂����A �܊p�̎l�G�h�w��ł��̂ŁA���������ɊW����ӏ��������Љ�����Ǝv�Ђ܂��B
�@�c�����Ȏ��̂���
�@�����͂��߂ďo�����W�̏o�ŋL�O��͓c�����̐��N�Ȃ̋L�O��ŁA�ۂ̓��̃}�[�u���łЂ炩��A�������͒�吶�ł����B���͓����납��ǖقł����̂ŁA ���̉�ł��قĂ��������̂ł��邪�A�������������ĕ����ł₹���\���(41kg)�̍��Ȏ����A�m�������Ă��͂Ă��̂�����Ɛr���ӊO�ȗ�₂��ꂽ�₤�ȋC�������B
�@���(�邴��)�c�蕨�̂₤�ɂ����ڂ�݂����Ƃ��ӂ��Ƃł������B
�@���̐Ȃŗ�������m���B�����������͎������l�Ԃ̕������͂�����A����Ȃٖ��͂������B���Ƃɂ��̋��łƌy���ɂ䂫�e���X�̍����Ƃ���Ɏ��̓�s�����邵���b��A ���̔��������������ƁA�����̎��͂͂��߂Ď��l���݂�₤�őA�����ĂȂ�Ȃ����B
�@���̌�ΐ��ŏ����Ă���̂ł����u���̎��͎����͂���Ђł������v�Ə����Ă���܂��B
�L�O��̂Ђ�����A�������c�����̎��ɒ悵���A�u�Ξւ�����₤�ȁv�Ƃ��ӌ��t���D�����Ƃ��āA�����Ɠ�l�ł������̂B���ꂩ����悭�����N����莆�����āA ����ł��ӂꂽ�Ƃ����A���Ƃ��炷���Ɏ莆������ЁA����������ł����B�����N�͂͂��߂���䂫�Â܂��l�ł���B���̎��͂����Ƃ���邢�Ƃ����ӎ��ł͂Ȃ��B �����Ƃ������l�́A���Ƃ��Ǝ��������̂ɂ��܂�ė����̂ł͂Ȃ��A���l��(�Ƃ���)����Ȃ����ɂ���邽�߂ɐ��ꂽ�₤�Ȑl�ł����B�������Ӑl����R������悢�̂ł���B
���͂��̌�ɑ������͂��ΐ��ŏ����Ă��镔��������̂ł���
�u���̐Ȃō����t�v�����������̎��Ɠc�����Ȃ̎����Ȃ�ׂĂ悭���Ă��Ƃ��ӂ₤�Ȏ������͂ꂽ�B�����������̕]���͂������Ă�̂ł��邪�A �����͂��̎��������͎v�͂Ȃ��������A���ł������v���Ă�Ȃ��B�c�����͎��l�Ɉ��ɂ���邽�߂ɐ��܂ꂽ�l�ł͂Ȃ��B���ꂪ���{�I�ɂ����ӂ̂ł���B ���̎��͂ނ��뙤���������A�\���͂������Ă�B�哌���퉺�̎��l������Ε��鎖�ł���B�v
�Ə����Ă���܂��B��㌻�㎍�̎��l���������������ƌ��ʂ�������Ƃ͑S���ʂ̕����ɁA�ނ͗����Ă���ł����A�c�����Ȃ����̈������Ђɏo���Ă��̂��A�펞�F�Z���Ȃ��Ă䂭�����Ƀf �r���[�������l�́A����̈ӌ��Ƃ��đ�ϋ����[���Ǝv�Ђ܂��B
�@������l�A�R��O���͑��c�W��肳��Ɉ�N��y�ɂ����鎍�l�ł����A�R�M�g�ɂ����c�W�Ƃ͓���ւ͂�₤�ɐ��҂̌f�ڂ��݂��܂��B�R��O���́A���̌̋��ł�������́A �����Z�̋��Ƃ̏o�g�ł����A���w�@�Ő܌��M�v�ɌO�������G���[�g�w�k�Ƃ��āA���w�̒������(�w�����̎��x�w�ߐ����Y�����̐��_�x���ɑ���{�S�ȑS�����s��)�o���Ă�܂��āA �����ƂȂ��œ������a18�N�A�o�����N�O�̂��Ƃł����A�w�ӂ邭�Ɂx(���a18�N1���A�܂ق�Αp��2 ����{�S�ȑS�����s��)�Ƃ��ӏ������W�����s���Ă���܂��B ����͓��ǂ̏��F�𐳎��Ɏ����s�������Ɂu��R�_�ɕ����v�u�\�������C��v�Ƃ������푈�����A�S�̂̔����߂����߂Ă���܂����A �܂��ʂɈ��Ƃ��Ă��w���{�n���������x(���a27�N ���J�쏑�[)�Ƃ��ӁA �V��Î��L�ƌĂԂׂ��₤�Ȓ��삪����܂��B�{�l�̎�ɂȂ鏘���́A�펞���ɂ����鎍�l�̈⏑�Ƃ��āA���ӂƂ��ċ��܂��ׂ����͂ł���܂����A�n��̈Ӑ}�́A �����̑��c�W�́u���{�V�I�v�Ƃ�����������̂��������܂��B������l�b�g��ɂ͏サ�Ă���܂��������Љ�v���܂��B
(�O��)���⎩���̐����́A�������Ă���������(����)��������̂ł͂Ȃ��B�X(����)�̂ݏ|�Ƃ��ׂĂ��䂪��N�ɂ��������܂��������̎��ɁA���̂���̂�����̐��̎��ɁA �ߋ����N�ɂ킽�āA�h��ח���ē��B�����M�O�̈�[���A���̖����̐��T�����ĂƂ��ĂЂ낭�����Ɍ������A����������ɂ������낱�т͂Ȃ��A���������͂���ʐ����̓��ɂ����āA �����Ȃ鍢��ƕs�ւ����̂�ł��A�_�����{�̂��߁A�䂪���̏����̂��߁A���̂��Ƃ����͏����̂����Ă����������̂ł���B�V�͎��̓G�O�ɂ�����⏑�̋C���ł����̂ɁA ���a�ȓ��ɗI�X���ɂ�đ������������̂��Ƃ����̂ƁA������ނ������Ƃɂ��邱�Ƃ͖��A�~�ނ����Ȃ��Ƃ���ł��炤�B(�㗪)
�@�ނ��܂����́w�哌���푈�����W�x�Ɏ��߂��邱�ƂɂȂ����̂́A���̏����ł��A�����炳�܂ɐ푈���ɍ̂������ł��Ȃ��A���W�w�ӂ邭�Ɂx���e���W�̂Ȃ�����A �f�p�ȝR��������ɑI��Ă��̂ł���܂��B�m���Ɏ��l�̎��l���鏊�Ȃ��A�����u���v��z�ӂɂ���A��قǂ̂₤�Ȍ���ȕ��͂ł͂Ȃ��A �����݂Ȃ���z�����R�Ƃ̂ӂ邳�Ƃ̎v�Џo�ɔ|�͂ꂽ�A���̂₤�ȍ�i�ɂ݂��邱�Ƃ͖����ł���܂����B
�@��������
��������
���͐����̂Ȃ��ɂ��Â܂�
�����ނ������Ђ��Ȑ����Â�
�����̂��Â��Ȃ����̂䂫���Ђ�
���܂ł����܂ĂȂ��߂Ă�悤�B
����͂��Ȃ������Ȃ����ꂵ�����Ȃ�
���ƂȂ��������̂������܂Ђł��炤�B
�����_�����ƂȂ��Ȃ���
�������ɂ��Ȃ��ē���̖X���䂷�Ԃ�
���钩�͖����m��ʏ������Ă����ƂȂ�
�t�����������������肪�ӂ��o����
���̂����܂̂��ւ̓y��������
�킽���̂��Â��Ă��ɂ�
�����̍g�̉Ԃт炪�܂ӂł��炤�B
�����ĉ����Ȃ����̂˂ނ�y�ɂ��肤�Â�
�₪�ďH������ƌ͗t��
��ʂɂ��肵�����炤�B
���͂����ł��̂������Ȃ����Ȃ������Ȃ�
���Ɠy�����Â��ĂȂ����˂ނ�ɓ��邾�炤�B
����͂Ȃ�ƂȂ��������Ƃ�
�������߂��ɂقЂ�������͂�
���̑c����\�c����
���̂��������������̑c�悽����
��͂肵�Â��ɂ˂ނ�Ȃ������y
���̓y�̍��ɂȂ��������{�̍�������
�����{�̋�̉���
���͓����Ƃ����ނ������Â�
�V�䂭���̂��Ƃ��������炤�B
�����Ď��ɂ͎��J�����悻��Ƃ킽��
����Ƃ��͔����Ⴊ���ꂢ�ɂ��Â߂邾�炤�B
����͂Ȃ�ƂȂ��������Ƃ�
�����͕��c�̂ݍ��̂�������{�̓y
�����ł킽���͂��Ƃ����Ђ�
���܂ł����̍��y���Ȃ��߂Ă���B
�����킽���̂ЂƂ̂˂��Ђ�
�����˂��͂��͉Ԃ̂��Ƃɂďt���Ȃ�
�@���̂����炬�̂������̂��넟��
�@�������Ă݂Ă䂫�܂��ƁA���̖{�̍Ō���߂�ׂ���i�́A�^�C�g���̎�|���炷��A���c�W�A�R��O���ł͂Ȃ��A���ƂւΑ�ؓՕv�A���̐l�͂��łɕʊ��ɂĎ��^�ς݂ł���
���ӂȂ���A�N��A�킩����A
���̏���A�܂��������ɂ��A
�C��̂͂邯���ʂĂ�
����A�͂����������͂�A
�M�����������҂�
�傢�Ȃ鋹��@����A
������u�ɂ�������
�b���A�������ЂĐ�(����)�ւ�A
�킪�����̓o�^�r���̊X�A
�N�͂悭�o���h����˂��A
���̗[�x����(����)��Ƃ�
�����₩����\����
���̖邩�A�܂����Ɍ���A
���ӂȂ���A�N��A�킩����A
����A��Ɛ����Ƃ���
�فX�Ɖ_�͍s���_�͂䂯����B
�Ƃ��Ӂu��F�ʔt�̉́v�ŗL���ȁw�C���ɂ���ĉ̂ւ�x�ł���Ƃ��A
���Ђ͐��W�ɂ��p��̒����́A�w�V�ƊC�x(���a40�N4��)�Ƃ��ӎ��W�̂Ȃ��̈�́A
���������̊C��
�ق̔��������䂭
�C�́@����
���@����
���̐l�̉i���̎���
���܂��̎���
�������߂�̂�
�����
�C�ɂ͂��������ƂȂ݂�����
���ɂ͔ނ̌��x������
�l�ɂ͐Ӗ�������
����́@�݂�
�Ӗ����������@�܂�
���̍��y��
���m�̖�����
����݂͂�
������
�Ӗ���
�i���̎���
(�p��ɕ�����72�͂̂���9)
�@����������i�̕����������������̂ł͂Ȃ����Ǝv�������Ƃł��B
�@�������Ĕނ�A���c�W�ƎR��O���ɂ��ẮA���R����搶�������̒��ł悭���O���������܂��A�\���v���v�A�ˎR�E�O�A���Ђ͐��_�����؋��A�����Y�Ƃ������l�X�ƈꏏ�ɁA �u�l�G�E�R�M�g�h���v�̎��̐��Ƃ��āA���炽�߂Ĉꊪ���݂�����ׂ��؍��Ђ̂��̂ł������₤�ɂ��v�ӂ̂ł���܂��B
4.�c�����Ȃ̃A���\���W�[
�@�܂�A���\���W�[�Ƃ��ӂ��̂́A�I��鎍�ɂ���Đ����ǎ҂ɗ^�ւ鎍�l�̈�ۂ��قȂ��Ă�����̂��Ǝv�Ђ܂��B�c�����Ȃ̃A���\���W�[�Ƃ��ẮA �������_�Ђ́w���{�̎��́x��24��(�ێR�O�E�c���~��E���������E�c�����ȁE�����L��Y)�́A��{�z�Y���̉����t�������̂������Ƃ����ؒ��J�ł���A ������z������̂͂Ȃ��Ǝv�Ђ܂���(���l���g����{�z�Y���ɂ͐[�r�̉��`�������Ă�₤�ł�)�A���͍���A�c�����Ȃ̎���I�Ԃɂ������ẮA �^�C�g�����w�哌���푈�����W�x�Ƃ��ӂ��ƂŁA�ҏW�T�C�h����̈˗��ɂ͗\�߁u�푈�����v�Ƃ��Ӑ���������ł��B�����m�̕��͏��Ȃ���������܂��A�c�����ȂƂ��ӎ��l�́A ���L���X�g���ɉ��@���A�Ō�̎��W�Ƃ͉]�ւA�M���Ԃ����ɔz�����i���w�_���Ȗx(1983�N)�Ƃ��ӌ���30������̈���ł��B �s�т̌�w(��q)�����F���鎄�������Ă���܂���(��)�B�ł����A�������ӐS���ŖS���Ȃ�ꂽ�̂ŁA���̑p���ɓc�����Ȃ��}�֓������ɂ������ẮA�L���X�g�҂Ƃ��āA �搶�̈�u�ɔw�����ƂɂȂ�Ȃ����l�ւ܂����B�����Ă������Ė{���o���オ���āA�����Ɏ��߂�ꂽ�A���ɑO���̈�r�W�Ɋ�𗎂Ƃ��܂��ƁA���x�͔��ɁA �����ЂƂ萶���c���Đ��E�ς�ς����l�Ԃ��A䢂ɉ�����p�삽������ǂ�ȕ��Ɍ}�ւ��邾�炤�A�Ƃ��ӕs�����N����܂����B����ɑ����̊��Ɏ��߂�ꂽ���������A�Ñ��M�v�A �ɓ��×Y�A�����L��Y�Ƃ������l�G��R�M�g�̒��ԒB�̍�i�A�����Đ�قǐ\�グ�܂����A���̊��Ɉꏏ�Ɏ��߂�ꂽ��y�́A���c�W��R��O���ɑ���I���̊�Ɣ�ׂ܂��Ă��A �������̑p���ł͑�\�삩��́u�x�X�g�Z���N�V�����v���̂�ꂸ�A�ЂƂ肾�����Ȗ����������邱�ƂƂȂ��Ă��܂������̓^���ɂ��ẮA���l�Ƃ��Ă̐搶�ɐ��ɐ\����Ȃ��v�ЁA ����͂������Ӗ�ł��̖{�Ɏ��߂�ꂽ���т̑I�ɂ��āA�o���Ƃ��ӂ���̐\���J�����������Ƃ��ӂ��Ƃł���ĎQ��܂�������ł��B
�@�c�����Ȃ́A�����u���{�Q�֔h�v�̓��l�ł͂���܂��A��قǂ��\�グ�܂����₤�ɁA���{�Q�֔h�̂��Ƃ�푈�^�����w�҂Ƃ��Ĕᔻ����l�X����́A�w�_�R�x�Ƃ��Ӗ��O�̎��W�������Ƃɏے�����₤�ɁA�ނ��낻�̐��_��̌������펞���̎��l�Ƃ��āA �T�^�I�ȁu���{�Q�֔h�̎��l�v�Ƃ݂��Ă��̂ł͂Ȃ����Ǝv�Ђ܂��B�����Ă����ł���Ȃ�A���{�Q�֔h����̎��l���ǂ�ȕ��Ɂu�m�肷�ׂ��v�푈���������Ď��ɕ\���Ă����̂��A �ЂƂA���\���W�[��҂�ł݂���͂����肷��̂ł͂Ȃ����A�ƍl�ցA���̊��ɋ��͂����Ē������Ƃɂ��܂����B�ҏW�̓��@���A����܂ŌJ��Ԃ���Ă����푈���ᔻ�̗���ł́A �s�抸�Ȃ����Ƃ��A�ǂ̂₤�ɃA���\���W�[�ɔ��f����A�ǎ҂ɓ`�͂�̂��B����N�����ɕ��ׂĈꗗ���邱�ƂŁA���l�̐��n�ƕ����Ɏ���ߒ����A�O��S���W��҂ۂɂ��܂��āA ��w��s�I�Ɏ������Ƃ͂ł��Ȃ����A���̂₤�ɍl�ւ���ł���܂��B
�@����Ȋϓ_�ł�����A������\��͖w�ǂ���������܂�������ǂ��A���Ɏ��l���P�s���W����Ȃ����E�⎍�тɂ��A�ʔ������̂�����Γ���邱�Ƃɂ��܂����B ���Ƃ͎��ۂɍ�i��ǂ�Œ����Ċ����Ē�����ςނ��ƂȂ̂ł����A�܂��͊e���т̎G���ɂ����鏉�o�N�����A���ڎ��W�ƂƂ��Ɉꗗ���邱�Ƃɂ��܂��B��苖�̎������䗗�������B
�f�ڏ� �^�C�g�� ���o�N�� �@���ڎ��W
1 Marchen ���a15�N8�� �u�嗤���]�v
2 �� ���a12�N5��
3 �H�̌� ���a12�N12�� �u���W���N�ȁv
4 ���҂Ɍh�X���� ���a13�N10�� �u�嗤���]�v
5 ���������Ƃ� ���a14�N3��
6 �đ� ���a14�N8�� �u�嗤���]�v
7 �嗤 ���] ���a14�N12�� �u�嗤���]�v
8 �c�I���Z�S�N�̒� ���a15�N1�� �u�嗤���]�v
9 ��� ��� ���a16�N2�� �u�_�R�v
10 �p �J ���a16�N8�� �u�_�R�v
11 ���̍� ���a16�N9�� �u�_�R�v
12 �n���C �����s ���a16�N12�� �u�_�R�v
13 �_ �R ���a17�N1�� �u�_�R�v
14 ���{�� ���� ���a17�N2�� �u�_�R�v
15 �����L�� �u��̐��v
16 ���c������ �u��̐��v
17 �G �~�� �u��̐��v
18 ��x�m ������ ���a17�N9�� �u��̐��v
19 �ʂ�̉� ���a18�N5��
20 �킪 �]�R�L ���a18�N6�� �u��̐��v
21 �l�G�Ȃ����� ���a19�N6��
22 �܂�����҂� ���a19�N12��
23 ���͐����� ���a21�N9�� �u�߉́v
24 ���� �u�߉́v
�@����N�����Ƃ͐\���܂������A���͈�ԍŏ��ɂ́A���a15�N�ɔ��\���ꂽ�uEin Märchen�v�Ƃ��ӁA�푈�Ƃ��W�̂Ȃ��₳�������G��̎��𐘂��܂����B
�@Ein Märchen�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a15�N8�����o ���ڎ��W�w�嗤���]�x
�Ő��̂܂�Ȃ��ɕ���(�ӂ�����)������
����ɉe�f���Ğ�(�ɂ�)�̎�������
�����ň������l�̏������֕�(�����f)��x��
�x����č��炤�Ƃ�����֎q���Z�����Ȃ���
��l����������ċ��������ɂȂ�
��͐��_�͔������̌O�������
���̎��l�͌��������@�K������
�����ǂ��̈�l�����͑����v������
�����ė֕��̓������Џo���Ē��߂�̂���
���̊y���������ɂ��s�^���������̂��Ƃ��v�ӂ�
�ӂ����ƐS�����܂�̂���
�푈�ŕv�����������ׂĂ̍Ȃ����ɕ������тƂ��āA�����Ɏ��l�c�����Ȏ���̐��U���ے��I�ɗ\������₤�Ȉ�тƂ��āA�ǂ����Ă�������ŏ��Ɍf�����������̂ł���܂��B ����ɂ���́A��قǐ\���グ�܂����₤�ɁA���������A�����̎��l�̂Ȃ�����c���搶�ЂƂ肪�푈���������W�߂��邱�ƂƂȂ����A ���̑p���ɂ�����s�K�ȑҋ��̂��Ƃ�慂��Ă��₤�ł�����A�����I��ł����ĉ��Ȃ̂ł����A�ɂ������ւ́u�I�`�v�ƂȂ��Ă���܂��B
�@5.�哌���푈�̒�`
�@���Ă����Ō��t�̖��ł�����ǂ��A���������u�哌���푈�v�Ƃ��ӂ͈̂�̂ǂ�Ȑ푈�̂��Ƃ��w���̂��Ƃ��ӂ��Ƃł���܂��B���{������������̐푈�Ƃ��ւA ��ʂɏ��a12�Nḍa���ɒ[����u�����푈�v�ƁA����ɑ����܂����a16�N12��8���Ɏn�܂����u�����m�푈�v�̂��Ƃł����A�Ƃ��ɐ�コ���Ă��₤�ɂȂ����ď̂ł��B �ق��ɂ͖��B���ςɎn�܂钆���ւ̐N����F�Z���Ӗ�������̂Ƃ��āu15�N�푈�v�Ƃ��ӌ��t������܂��B�܂�����A�����ېV�ȍ~�A���F�l�퍑�Ƃ���ЂƂ萼���̗Ɍނ��������{���A ���m�����Ƃ̍ŏI�I�Ό����f���A���������ʒu�Â���Ƃ���́u100�N�푈�v�Ƃ��Ӎl�֕�������܂��B�u�哌���푈�v�Ƃ��ӌď̂́A ���{���ĉp�ɐ��z�������ۂɌf�������̂Łu�哌��(���A�W�A�E����A�W�A�E�����m����)���h�������邽�߂̐푈�v�Ƃ��ӈӖ��ł����A���̂Ƃ������ɁA����܂ōs���Ă��������ւ̐N�U�����܂߂āA �܂�ḍa���ɖu�������x�ߎ��ςɂ����̂ڂ��āu�哌���푈�v�ƌĂԂ₤�A�푈�ɑ���F�����A���߂Č��t�ƂƂ��Ɍ��ɉ��ς��ꂽ��ł���܂��B �푈�ɑ�`���f������܂ł́A�����ւ̐N�U�ɂ��Ă��͂����肱���푈�ƌĂׂȂ����ێ���������킯��(���{���ɂƂ��Ă͂���ȏ�̍��ۓI�ȌǗ�����������A �������ɂƂ��Ă͎x�����Ă�鐼�m���܂��푈�ɂ͊������܂ꂽ����Ȃ�����)�A���̎��l�B���A���̏��a16�N12��8���Ɏ����Ă͂��߂āA �����Ԃ̏Փ˂��P����Ԃɂ��錴�����w��̐����ɂ��邱�ƁA���������f���Ƃ��u�A�W�A�ΐ��m�v�Ƃ��ӕS�N���̍��݂ɕ��鐳�`�ł���Ƃ��āA����܂łƂ͑ł��ĕς͂��āA �J�������Ԃ���₤�ɐ푈���������n�߂邱�ƂɂȂ��ł���܂��B
�@6.�c�����Ȃ̐푈���@���̇T (�����푈����)
�@����ł͍ŏ��ɓc�����Ȃ��u�哌���푈�v�̑O���A�����푈����ɏ�������i�ɂ��Č��Ă䂫�����Ǝv�Ђ܂��B�ނ��u�R�M�g�v�n���ƂƂ��ɕ��w�I�f�r���[���������a7�N����A ��ꎍ�W�w���W���N�ȁx���o�����a13�N�܂ł̊ԂƂ��ӂ̂́A���B���ψȌ�̓��{�̒鍑��`�ɔ�����^�����A�e���ɂ���Đ��̒�����p�������Ă䂭�����Əd�Ȃ�킯�ł����A �Ƃ�킯���a10�N��ɓ���܂��ƁA���l�͕��ʂɐ������Ă�Đg�̎���Ɍ����Ƃ��Ĕ�э���ł���푈�A�����ɉۂ���ꂽ�h���Ƃ��Ă̐푈�Ƃ��ӂ̂��A����������ł��₪��ɂ��ӎ�������Ȃ��Ȃ��Ă䂫�܂��B �u�l�G�h�v�ɂ����Ă͂�������S�ɃV���b�g�A�E�g���邱�Ƃ������A���͂Έ��́u�ӎ��v����d���ł���������ł����A�u�R�M�g�h�v�̎��ɂ́A �T���̎���A�ȒP�ɂ��ӂƐ^�������߂ă����������銴����Ԃ���f�X�p���[�g�ȋC���Ƃ��������̂��Z���Ɋ������܂��B�����u�q�u�̎��v�ƌĂ�ō����x�ւȂ����Ǝv���܂����A ��N�������푈���Ƃ́A�قȂ�����e��z�肵�ď�����Ă���܂��āA�܂��l�̓ǎ҂ɂ���Ėٓǂ���邱�Ƃ�O���ɏ�����Ă�āA�t�B�N�V�����̊k�ɕ��ł�����̂������̂ł��B ���������ԂɌ��čs�������Ǝv�Ђ܂��B
�@�ŏ��̎��W�w���W���N�ȁx(���a13�N)�̎��ォ��́A��҂̂ݍ̂�܂����B
�@ḍa�������̈ȑO�ɔ��\���ꂽ�u��(���a12�N5��)�v�Ƃ��ӎ��́A�푈��ɂ��Ă͂�܂����A�`����Ă��̂͐푈�̎c�s���Ƃ��ӂ��A�ނ���n�쏖���ɒ��������l�̕��̂��A �j�����}���Ƃ��Ă̐푈���L�q����ɑ�σ}�b�`�������̂ł��邱�Ƃ����������̂̂₤�Ɏv�ЁA�T�����Ƃ��ē���܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a12�N5�����o
�����m�����㍡�n�ڃj���N�����i�C�K
�A�R�m�k�[�\�\�S��_�͎l�q���{�m�Ӄg�f���V�e�I�J�E�\�\
�\�R�j�ރK�����e���ԃV�e���^�֕��m�ꕔ���n
�˔@���σ��N�V�^
�ރ��Õ����Z�B�n�����O�������S���J�n�V
�g�C�`�P�n�x�X�c����P�����^�K�\�\
�\�m��
�ރn��w�����e�R��i�N
�R�X�g�Ό��g��������m�]���j�D�n��
�ډB�V���T���^��e�E�T���^
�ރm���g���g�n�Ì��m��Q�K�����H�q�s�V
�ړ��V���c�^�����m�Փ�c�c�^���m�n
�ރK�������ǃV�^�g�c���A�S�W�m�~�_�c�^�g�]�t
�@���ꂪḍa�������Ȍ�̍�i�ł���u�H�̌�(���a12�N12��)�v�Ƃ��ӎ��Ɏ����āA���l�͗�Ԃœ��Ȃ����n���o�g�̏o�����m�ɁA �킴�Ɓu�������̂������Œ��炵���Ƃ�������܂����v�ƌ�点�܂��B���̎��̃��X�g�ɟ��ގv�ЂƂ��ӂ̂́A�������u����̎��v�Ɓu�q�u�̎��v����钆�Ԃɂ���₤�Ɏv�Ђ܂��B
�@�H�̌@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a12�N12�����o���ڎ��W�w���W���N�ȁx
�l�����͏H�̔������ꏏ�ɕ邵��
�����Ԃ̎O���Ȃ̂��܂�Ƃ�
�G�����͂��Đe���Ɍ��
�u�k�x�͍��͂����������Ƃł�����
���͒}�g�̖k�̘[�̐���
�Ƃɂ͌ܐl�̎q��������܂�
���l�����͊����Ăđ��Ă���܂���
�����ɂ͏\���ԂƂ܂Ă�܂���
���̔��ɔ����͋����̉Ԃł�����
�Ȃ�Ɠ��h�q����R�A��Ă܂���
������͎��̂��ɂ�肸�ƖL���Ȃ��Ƃł��ˁv
�D�Ԃ͍��X�ƓS�H�𑖂�
�Ђ邷���Ĉ���̓S����n��
�H�̉��](�Ƃ��Ƃ���)�̕l���̌�
���͝ނ�@�D�͋A�����(���Ȃ�)�̍]
�R�X�͂��Â��Ɍɉe�f���\�\
���m�͂��Ɗ������Ē���
�y�����ɉ]�Џo���Ėl��܂��܂�
�u�������̂������Œ��炵���Ƃ�������܂����v
�@����͎��̎��W���w�嗤���]�x�Ɏ��߂�ꂽ�u���҂Ɍh�点��(���a13�N10��)�v�Ƃ��ӎ��̂Ȃ��ł́A�펀�҂�O�ɂ��āA �푈�ɑ���^���̌��t�����̌��t�������Ȃ����Ƃɂ���Đ������L�����Ƃ���p���ɕς��܂��B����ɂ₪�āA �u�H�̌v�Ɠ����₤�ɏo�����m��������u�đ�(���a14�N8��)�v�Ƃ��ӎ��ɂ����ẮA�\�������v�Ђ��S�āA�o�����Ă䂭���m�A���̍K�^�Ɩ������F��C���Ɍ����ӂׂ��A ��̓I�ɂƂ��ӂ��\���I�ɕω����Ă����Ă��₤�Ɏv�͂�܂��B
�@���҂Ɍh�点��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a13�N10�����o ���ڎ��W�w�嗤���]�x
���҂Ɍh�点��
�u�X�Ɖ���(�Ƃق����Â�)�̔@������
�킪�F�@�������я����͋P�̞l�ԗ����
���炫�̋e�@�x�炫�̃_���A�݂Ȕ������ďD�Ђ���
�v�ւ��N(����)�̉ā@�̗��𗧂�
�R���͏d��R�̍�
��(������)�̓G��ł�����@��╪���T��
�͂�腎��R�̍�炵�߂㠈����〈����
���(�ЂƂЂ�)�̕ւ肾�ɗ���
�܌���t�̒��܂���
�R���̎R�����o�ʼn͓�Ȕ������̐퓬��
�땺�̒��ɂ͂��肫
�`�F�R�@�e�@⹂���f���ɓˌ���
�c�̌l�ɝ˂�@��\���Ȃ肫
���炫�̋e�@�x�炫�̃_�����݂Ȕ������ďD�Ђ���
�킪�F�@�������я����͋P�̞l�Ԃ͋����
�u�X�Ɖ����̔@�������\�\
���҂Ɍh�点��
�@�@�đ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a14�N8�����o ���ڎ��W�w�嗤���]�x
�������̗���Ɣ����q�Ƃ̊�
�đ��̒��ŋO�����J�[������Ƃ���
�����ɔޓ��͑�������҂��\�ւĂ
���̊ۂƐF��ȉ��ЂƂ����ā\�\
�����l�\�����{�s���}�͎��삷��
�J�[���ł���͈�x���x���ɂ�
���̂Ƃ��ޓ��͓��ɏł����������
���X�X
���͑�N�̏�ɂ�������
���ɏł�����͂�����
�����R(������)�Ɂ@�������y��
���܂����̍��}�ւ邱�Ƃ��炤
���肬�肷���đ��̃J�[���̂Ƃ���
�|��Ђ邪�ւ茩���Ȃ��Ȃ����̊ۂ�
���������юv�ЕԂ��Đ������Ƃ��炤
���́u�đ��v�̎��ł͓����Ɂu���X�X�@���͑�N�̏�(��)�ɂ�������v
�Ƃ��ӌ��t���Y�ւ��Ă�܂��B����������͒P�Ɂu�V�c�É��o���U�C�v�̃C�f�I���M�[���Ȃ��������t�Ƃ��ӂ��́A
�u���ɏł�����͂�����@�����R(������)�Ɂ@�������y�Ɂ@���܂����́u�v���}�ւ邱�Ƃ��炤�v
�Ƃ��Ӂu�����̍v�Ɋ|���錾�t�ł����āA�S�̂̕��͋C���A�����Ă䂭��Ԃ������镗�i�ɏd�˂��āA�߂������̂���������̂ł���܂��B
�@�����I�ɂ͂����̎����͂���ŗ��������̎�������̂ł����A���̕ӂ肩��c�����Ȃ̎��́A���́u�\���I���i�v�Ƃ��ӂ��̂�\���ĎQ��܂��B �Ƃ��Ɂu���������t(���a14�N3��)�v�u�嗤���](���a14�N12��)�v�u�����(���a16�N2��)�v�Ȃǂ̍�i�A�����Ƃ����l�̟T�����Љ�ɑ��Č��ڂꂽ��i�Ƃ��ӂ̂́A ���j�ʂł����l�Ƃ��Ă̎��l�́u�q�u�v�Ƃ��ӂ��A�ނ��뎍�l��ʂ��Ė����̈ӎu�ł���u�哌�����h���v�̗��z������o�����₤�ȁA����ȓnj㊴�ɏP�͂�܂��B �܂����ꂪ���l�̕��̂̎������ł��錉�Ȃ��Ɏx�ւ��āA�嗤�ւ̐N�����m�肷��₤�ȃf���[�j�b�V���ȓƓ��̊�����ł��o���Ă��̂ł��B���ꂪ���l�̂��킲�Ƃ��\�����ӎu�Ȃ̂��́A �������ނ��Ђ��Â�͂��߂邱�Ƃł킩��Ȃ��Ȃ��Ă䂫�܂��B���W�̃^�C�g���Ƃ��Ȃ����u�嗤���](���a14�N12��)�v��ǂ�ł݂܂����A ���̎��͎��l��������(�u���W�u�嗤���]�v�o���v���a15�N10��)�ɋ���܂��ƁA�G���u���Y�����v�̃��[�_�[�I���݂ŁA ���w�҂��R�l�ł������@�c�P�����A�����̐�ꂩ������M�̒��ŁA���Ē����ɈÖ��C���A�`���̂��Ƃ��������鎩���ƂȂ���ւď����t�������ɁA �c�����Ȃ����C�����₤�Ȃ��́A�Ƃ��ӂ��ƂɂȂ��Ă���܂��B�@�c�P���̌��ƂȂ������͂Ǝ��������܂��B
�@�@�u�ʐM�����M�v�@�@�@�c�P���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y�����@���a14�N7����
(�O��)���͊������]��k��Ȃ���A�ӂƘ`���̂��Ƃ�z�������Ƃ�����B���s��M���т͓����������@�o�g�ŁA�����L�҂Ƃ��ď�C�ɂ��݂��l�Ȃ̂Ř`���̂��Ƃɂ��͂����A ���낢���Ă��ꂽ�B���͂ӂ����Ȕނ�̍s�����v���B����͖ܘ_�����̉����Ɛ����I�Ӗ��͔@���ł������A���͂Ƃ肠�ւ����̂₤�ɏ����Ƃ߂Ă������B �����҂̟����͑��ʂ�����̂�����₤�ł���B
�ނ�͝X�˂���A�`�̖��Ȃ肫
�ނ�͊U�薳���ȒÊC�̔ޕ���
�傢�Ȃ��Ɨ��Ƃ�]���āA
��ւ������肯���
�u�������F�v�̊��������āA
��(���Ƃ�)�ʂ��ʍ��X�։�����(��)�ōs���ʁB
�ނ�́g�S���́h�̗|�ɂ����Â�͂��肵����
������ւĂ߂Ō}�ӂ�҂��܂Ђ������݁A
����債�݂čR�ӎ҂�Ĕ������肫�B
�ނ�A�s�v�c�Ȃ�k(�₩��)�́A������
�嗤���A���ɓ�ɗ��߂߂���A
���͌Ð�(�ނ���)���ɍ�(��)�܂��āA�ԓ��̐F����(����)�����V�����P�ЁA
���͒��]��k��āA�V��V�Ă���Ă�T�肵��
�喾�����R(���ǂ낫)�����āA�h�����ւ�
���{���R�ɐ��ЂĔV�ł���Ƃ��A
�s痂Ȃ鑸�̂���A�v���R�Ɛς݂��肵���A
���ɏ��R�V����ߓ������Ƃ����\�\
�B���ƂȂ��ނ玩(����)��Ɛ��Ɏ��ɍs�����c�c
�ЂƂ�R�c�����Ƃ��ւ鋭��(�͂���)�A
�V�������ɁA���҂̐��Ђ��ق����܂܂ɂ��A
�ł��Ă͂��Ȃ��Ŋ����Ƃ�����ƁA
�j�ɂ��̉�����[���܂�ʁB
�嗤���]�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a14�N12�����o ���ڎ��W�w�嗤���]�x
�[�邲�Ƃɑ�C�̂قƂ�̋u�ɗ���
���Ɍ��Čږ]����̂����͂��ƂȂ�
�����[���̒����Ƃł͔g���}�ɍr���Ȃ�
��R�̙ꂫ���������@���̒��ɂ�
����ȂԂԂ����܂��Ă
�����Ă��̈�������]��
�u���̂��߂ɂ��O�͉��������̕��Ɍ��ӂ̂�
���̊C�̔ޕ��ɂ͓ݏd�Ȗʖe������
�ܐ�N��晍�(������)�Ɨ����̗��j������
���F���������������s������݂�
�����œ��X���Ќ�����忂߂��z�Ă�邾����
���̑��ɉ������Ă��O�͒��߂Ă��̂��v
����ɑ����͔���g���Ă������ւ�
�u�����Ƃ����̂��߂Ƃ���͂Ȃ��ł����
���̖�Е��ɂ͑G�������̂��܂��Ă�邩���
�����������Ă��O�ɓ��ւĂ�炤
�킪�c(����)�������ӎu���@�~�]�������Ƃ�
�Ȃىʂ���ʑ傫�Ȋ�Ђ��Ƃ�����
���ꂪ����̌��𑛂����Ď~�܂Ȃ����炾�v
�����]���Ƃ��[��̑��ɂ̒�����
�����̓�(�p�S�^)�A���܂��̝i��(�A�[�`)�A���܂��̏�O�Ȃǂ�
�Ɨ�(�������)�����F(����)�ɋP���̂��������B
�@���X�g��
�u�[��̑��ɂ̒�����A(�p�S�^)�A���܂��̝i��(�A�[�`)�A���܂��̏�O�Ȃǂ��Ɨ������F�ɋP���̂��������B�v
�Ƃ��Ӊӏ��́A���͂����ǂނ��тɂ����A�I�[�P�X�g���̉��F���������Ĉ�C�ɒ��_�܂ōV�Ԃ�₤�ȏ�i���v�Е`���Ă��܂Ђ܂� (�ڋ߂ȗ�ŗ�ւ�Ȃ�ABeatles��m���Ă�l�Ȃ�AI�fm the Walrus�̃��X�g�݂����Ȋ����ł�)�B
�@�܂��A���̗[�ׂ̊C��O�ɂ����T���̋�C�Ƃ��ӂ̂́A�ɓ��×Y�̎��W�w�t�̂������x�Ɏ��߂�ꂽ�u�Ă̏I�v�Ƃ��ӎ��̋C���ɒʂӂ��̂�����̂���Ȃ����Ǝv�Ђ܂��B �u�Ă̏I�v�̃��X�g�ɂ��u����s��Ȃ��̂������ɌX���Ă��̂ł������v�Ƃ��ӂ����肪����܂����A����͑s��ȋG�߂��ǂ��ɂ��Ȃ�ʗ͂ł������X���Ē���ł䂭�Ƃ������Ӗ����Ђł����A ���̎��ɂ�����u�Ɨ�(�������)�����F(����)�ɋP���v�u��(�p�S�^)�A�i��(�A�[�`)�A��O�v�Ƃ��ӂ̂��A�s��ȃA�W�A�̗��j�I�ߋ��̑��̂Ƃ��Ă̌��Ȃ킯�ł����A �V�R�ƌ��������s���Ȗ����_�Ԍ�����̂��Ƃ͎��ɂ͏�����Ă�܂��A�����炭�ŏI�I�Ȍ������ʂ����푈�Ɍ������āu�s��Ȃ��̂������ɌX���āv�������̂ł͂Ȃ��ł������B (�ӂ����ї�ւČ��ւA��قǂ�Beatles�̋Ȃ��I������ɂ��A����Ȃ��₤�ȉ������Ђт��킽��܂���)�B
�@���Ă��̎����^�C�g���Ɍf������W�́A�����ɂ���܂��₤�ɁA�S�̂��@�c�P���ɕ������Ă���܂��B�w���W���N�ȁx���A�@�c�P�������Ɏ��������ĈԂ߂Ƃ��Ă�A �Ƃ��ӂ��Ƃ��Ċ����������l���A���炽�߂đ�W��������킯�ł���܂��B
�@�@�c�P�����`���̎����L�������Ȃ��u���Y�����v�̏��a14�N7�����ɂ́A���l���g���u����̎��l�v�Ƃ��ӑ�ŕ��͂������Ă���܂��B�����ɂ͎��l�̔C���Ƃ��āA ���R�Ɍ���╶����g���ď��ĉ̂͂�Ȃ������u�V�������Ƃv�ɂ�鎍�����邱�ƁA���̐V�����Ƃ́u�����S�����ɌĂт����Ă��̐S��������u�₩���ŏ[�������ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������ɏ�����Ă��̂ł����A �܂�A�푈�̎����������V�c�É��o���U�C�̎����������Ƃ͏����Ă�Ȃ��̂ł����A�u������l�̓ǎ҂ɂ���Ėٓǂ���邱�Ɓv����A���ږ��������֑̂i�ւ悤�Ƃ�������ցA �����̓ǎ҂�\�߈ӎ��������̐���ւƁA���M���Ȃ��Ĉӗ~��ł��o���Ă���܂��B�ǂ��ɂ��Ȃ�ʗ͂ŗ��j�������Ă�邱�Ƃ�̊��������l���A���̗��j�������Ƃǂ߂���A �u�\���I���i�v�������ė��j�̍s����^����ɂ݂Ă�炤�Ƃ̑z�Ђ��������̂�������܂���B
�@�����A�@�c�P���ւ̌X�|���������݂��邱�́w�嗤���]�x�ł����A���̘@�c�P���Ƃ��ӂЂƂ́A�T�^�I�ȌR�l����ŁA (�N���b�`�}�[�̋C�����ނł��ӂȂ�ؓ����ł��܂����̍D���̓T�^�I�ȁu���m�^�Ă�C���v����Ȃ����Ǝv�ӂ̂ł���)�A���Ζʂ̓c�����Ȗ{�l�ɑ��Ă͍����̕s�����������₤�ł���܂��B �₹���������֔h�N�̗��������C�ɏ����Ȃ������̂�������܂��A�u���̎��Ԃ��\����Ă�Ȃ��v�ƁA�����ɕ�����ꂽ���̎��W�̓��e�ɂ��đ�w���˂��ꂽ�����ł���܂��B ���l�ɂ��Ă݂�ΈӊO�Ȍ�Z�Ǝ��]�������₤�ŁA����܂ōD����Ă����Ƃ���v���Ă���h�����y��K�˂���ŁA�܂����v�����ɕ��傪������Ƃ͎v�Ђ����Ȃ��������Ƃł���A ����͂����炭���H���O������A�҂��ċC���V�Ԃ��Ă���ׂ��Ǝv�͂��̂ł����A�Ȍ㎍�l�͂��̐�y�̂��Ƃ������Ȃ��h������₤�ɂȂ����Ƃ��ӂ��Ƃł��B ���Ɉɓ��×Y�Ƃ͘@�c�P���͑�σE�}���������₤�ł���܂����A��N�@�c�P���̈ߔ����p�����O���R�I�v�Ƃ��A�ɓ��×Y�͍D����c�����Ȃ͖������ꂽ�̂��A �s�v�c�ɕ��������ʔ������Ƃ̂₤�Ɏv���Ă���܂��B
�@���ĊJ��Ɏ���O�̍�i�Ƃ��Ă͂ق��ɁA�������h�C�c�𑄋ʂɂ��������̍�i������Ȃ̂ŁA�Ƃ肠���܂����B
�@�p�J�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a16�N8�����o ���ڎ��W�w�_�R�x
�킪�Ⴋ���͒p����
�O(����)�̉��F����
��ꂪ�\��̎��Ȃ肫
�킪�w�Z�ɓƈ�l�@�����L���������Ƃ��Ђ��邪
��w���t�̔C�ɂ���
���ƍ���f���@��(������)�͏�ɏD�ӂ��
�ȂقƁU�܂�ċ��ւ���
�\�ꌎ�̂��ƂȂ肵
���H(������)�̂��Ƃɍ��O��
��R��������
���ăL���������̎��Ǝ��͎O�����Ȃ�
���̋x�e���Ԃɔ��n(�`���E�N)�Ƃ�
���E���ɑ发����
���Ȋח���(�`���^�I�E�C�X�g�E�Q�t�A����)��
�N���X���[�g�͊��т��@����
���@�I����Ȃ��␔�x�m���߂�
�n�Ƃ̏��͖炳���
�C���Ƃ܂�@��(�h�[�A)����
��(����)�L���������͓��藈����
�킪�M�̐Ռ���₢��
���̔��̖ʂɂ́@�g�����@�₪�Ď��҂̔@�@�����߁@��(���т�)�߂��炵��
�ĂыN�銅�тɁ@���͎�(������)���������肫
�\�\�킪�Ⴋ���͒p�����B
�@���k�ɑ��Đ�ΓI�ȗD�ʂł��锤�̐搶�ɑ��āA�l�ւ������s�������Y���u�������������v���ƂɁA���Y�̓����҂��p�������Ă��܂����Ƃ��ӎ��ł����A
�ʂ��グ���Ȃ��������R�ɂ��Ă͓��ɉ��������Ă���܂���B�Љ�I�ȃ}�C�i���e�B�[�ɑ��鍷�ʂ���������u�ԂɁA���m�炸�擪�ɂȂ��ĉ��S���Ă���Ƃ��A
��҂ЂƂ肾��������Ă��A�������ӂ��ƂȂ̂��Ǝv�Ђ܂��B���̂��߁u�킪�Ⴋ���͒p�����B�v�Ȗ�ł��B
�@�ꐡ�ǂނƑ̌��k�̂₤�ɂ������܂����A��ꎟ���Ő����ח������吳�O�N�͎��l��3�̂Ƃ��ł�����A���炩�ȃt�B�N�V�����ł��B���ۂ̑�㍂���w�Z����̎��l�́A
�h�C�c��̐搶�ł��������x���g�V���`���Q���搶�ɂ́A�D�G�Ȑ��k�Ƃ��čł�������ꂽ���ł͂Ȃ������ł������B
�c�����Ȃ̍ŏ��̒���̓m���@���X���w���ԁx�̖|���ł��B���������̎����h�C�c�ꋳ�t�łȂ��p�ꋳ�t�ł������Ȃ�A
�������ă`���^�I���p�[���n�[�o�[�������̓V���K�|�[���ł�������A�ǂ��ł������B�a���I�Ȏ��l�ƌĂ�闝�R�́A����ȍ�i�ɂ��\��Ă��₤�Ɏv�Ђ܂��B
7.�c�����Ȃ̐푈���@���̇U�@(�����m�푈����@���p�܂�)
�@���Ă������ď��a16�N12��8���̊J����}�ւ��ł����A�����u�푈���v�����l�B����Ăɏ����n�߂�Ȃ��A�c�����Ȃ��V������Ő^����ɊJ��̊����������\���܂��B �^��p�U�����r�u�n���C�����s�v�Ƃ��ӎ�������ł�(���a16�N12�����{��̐V��)�B���L�ɂ���12��15���������Ă���܂��B
�@�@�n���C�����s�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���a16�N12�����o ���ڎ��W�w�_�R�x
���R���遖���
�݂͂Ĕ�������
���ɘ߂�Đ��`����������Ɨ~��
���N�ߓ�����͂Ƌ@�ƖC��
�C�O�ɔ������Đ_�B��ۂނƑz�ւ�
�ꉭ�����݂Ȑ؎�������
���ف@���ɉ���ďH������
���͈ۂꏺ�a�\�Z�N�\����
�F���������܂炸�S�V��(����)��
��́X��@�i�߁@����`��
���X�s��ɂ��ĕ��������ɂ�
�g��̌����@����(������)��
�Ⴊ���͍c���ɋ����@���͕z��(�n���C)
�X�G��j�蓾�č����ɕ��
���肵�ċ@�ɏ��܂���ڂ���
�������X�@�G�������
����(����)�ꂽ�ы��~�ɗՂނƌ�����
�{�k�ɝ��j�����鋐���
�_���U�����č�(��)���e������
�^��p���@�������Ⴕ
����A(����)��Ɍ̍��ɓ���
�R�슽�Ă��đ��ؗh(���)��
���M�܂��Ӗڂ��@�X���T����
��ꍑ�j�̍��̏u�Ԃɐ�����������
���ŗ���x�m��]�����
�É_��@�����ᩂƂ��Ĕ���
�@�����Ă��̎����͂��߂Ƃ��ė����Ə������푈���ƁA��قǂ́u�p�J�v�̂₤�ȁA�푈���O�̎����ɂȂ����������������Ɏ��߂�ꂽ�A �w�_�R�x�Ƃ��Ӗ��̑�O���W�����s�����킯�ł���܂��B���l���g�͊J��̒���A���{�R���A��A�������߂������̎����ɁA ���m���p�̑��w�Ƃ��āA�_�ی����Y�A�k��~�F�A����������ƂƂ��ɃV���K�|�[���֔h������邱�ƂɂȂ�̂ł����A���W�͂��̗��璆�ɁA�ۓc�o�d�Y�ɂ���Ċ��s�̈������Ȃ���A �w�_�R�x�Ƃ��Ӄ^�C�g�����ނɂ���ĕt���ꂽ���̂������ł���܂��B�Ȃ��ɓ����́u�_�R�v�Ƃ��ӎ��т�����̂ł����A��������W�̃^�C�g���Ƃ��Čf����ɑ����������ǂ����Ƃ��ӂƁA �ꐡ���������݂��������܂������������A���(�͂ɂ���)���|�Ƃ������l���g�͖ʐH������炤�Ǝv�Ђ܂��B����Ƃē������ꂪ�܂����������������Ɖ]�ւ����Ƃ��v�͂ꂸ�A �ۓc�o�d�Y���땶�Łu�w�_�R�x�͑哌���푈��M�������V����̎��W�ł���v�Ə����Ă�܂����A�w�_�R�x�Ƃ��Ӄ^�C�g���́A���⓾�ӂ̐Ⓒ�ɂ��������l�̐S�����������āA ��������C�悭�㉟������z�������������̂̂₤�ɁA���ɂ͎v�͂�܂��B
�@������������A��N�̌����I�v�i�푈���ւ̓��@�w����̌{�x���猩���O�D�B���x2005�_�ˏ������q�w�@��w�@�����I�v46)�̂Ȃ��ŁA�푈���̎O�D�B���̂��Ƃ��A �u����͈������₽��ɂ܂䂢����ɗ�������Ă����v�Ƃ��ӕ��ɕ\������Ă����܂����A�o���オ�����{����ɂ��āA�c�����Ȃ��܂��A����͈������A ���������ډf�����ꂪ�܂�������ɗ�������Ă����A�Ƃ��ӐS���ł����������Ȃ��ł������B
�@�����āA�\���ɂȂ��Ă��u�_�R�v�Ƃ��ӎ��тł����A���ꂪ�܂��s�v�c�ȁA��퓧���ȕ��V���ɖ�������i�ɂȂ��Ă���܂��B ���ɑł��グ��ꂽ�e���オ�肫�����Ƃ���Ŏ~�܂��Ă���u���ʂ������̂₤�ȁA�������̂����͂Ȃ��A�Ƃ��ӊ����ł��B��������Y�����A���g�����p����邱�Ƃ�슴�ŗa���������̂₤�ȓ��e�ł���A �Ə����Ă�܂����A�ɓ��×Y�����̎��Ɏ��C����Ӗ��Łu���ʁv�Ƃ��ӎ����R�M�g�ɏ����Ă�܂�(���a17�N3���R�M�g)�B���ƂȂ��Ă����ǂ߂Ή��Ƃ��ӂ��Ƃ͂Ȃ��̂ł������A ���ɂ͂��̖{�����l�̏o�����A�R�M�g�̖��F(�ۓc�o�d�Y�Ɣ쉺�P�v)�ɂ���ĕ҂܂ꂽ�Ƃ��ӊ��s����ƍ����āA���ꂪ���̂܂��l�̈�e���W�ɂȂ��Ă����������Ȃ��₤�Ȑ_�����������͋C���A ���W�̃^�C�g���ƂȂ������̎����犴���܂��āA�܂��ɕs�g�ȁu�܂䂳�v�ɐ�ɂ��o�������Ƃ�����܂����B
�@�@�_�R�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a17�N1�����o ���ڎ��W�w�_�R�x
�n���C�C��A�}���C���C��A�䓇�n���̓G�O�㗤
�ƍc�R�̓��鏈������������Ȃ��A����ЂƂւ�
�_�ƂƎv�ӂ��O�Ȃ��B���T�ɉ����č��鎍�B
���̒��i�������j�@����Ɍ���
�_�l(����)�̔�ь��ӂ�����
�ЂƂ�]�Ӂ@�w��Д@���Ɂx
���ӂ炭�w�c�R(�݂�����)��
�����ɏ�������
�q�ǂ��炪���钹�M(�Ƃ�Ԃ�)
�������Ɋ�(�ӂ�)��������
���߂��͑��(���قԂ�)�܂�
�������ׂĖ�(�₤)�Ȃ��͂���
�c�_(���߂���)�ɐ\���ނ��߂�
�}���䂭�Ȃ�@���ċ�(����)�́x
�G(����)�̂��̓��ւĂ��͂�
�w��(�݂�Ȃ�)�̌R(������)�����ɂ�
�c�_(���߂���)�̔C(�܂�)�̂܂ɂ܂�
�䂭�Ȃ�ǁ@������܂�
�������͂���ށ@�݂������Ȃ�x
���Č�͌�(����)�Ɛ₦��
������̂܂��p�Ȃ��B
�@�@�@�@���ʁ@�@�@�@�@�ɓ��×Y�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a17�N3�����o
�N���u�_�R�v�Ƒ肷�鎍����߂�
�_�l������ɂЂ���
�����Ƃ���
�݂�Ȃ݂̂�����
�N���݂ɂ䂭
�݂���ɋ�͌����邲�Ƃ�
�t���邽�̂�����̂���̂���
�������������@�c����
��������Ă䂫�ɂ��邩��
�@���ۂ̕���Ƃ��ӂ̂́A�퓬�����ɏI������̒n��Ŕ��s����V���̕ҏW����ł����āA�{�l���A����Ɂu�R�M�g�v��u�c���v�̘A�ڂ̂Ȃ��ŏڍׂɕ��Ă���܂����A �ꏏ�ɍs�������w�ҁA��ւΖk��~�F�̏����w�����x(�蒠���ɁA���a22�N12���n����)�̂Ȃ��Ŗ�������Ă��̂́A���p�ғ��u�̊m����ʂ��Ă݂����{�R�̓ƑP�̑̎��ł������₤�ł��B ���̖\�I�{�ɂ��Γc�����Ȃ́A��y���w�҂��ɂ܂�ăV���K�|�[���̐V���Ђ���Ӓn�̃X�}�g���֔����A�����Ō�ʎ��̂ɑ����āA���Ȃ���_�o����̋C���ŋA���Ă����A �Ƃ̂��Ƃł����A����֍s���r���ł̃G�s�\�[�h�Ȃǂ͎��l�̋C�����O�҂����ʂ��đ�ϖʔ����̂ŏ��������Ă݂܂��B
�@�@�����w�����x(�k��~�F)���
�@����ӁA����(����)�ƕ���(�����F�嗤�V��L��)�ƁA�����V�~�ɓ��h�̏��Z�ƁA�O�l�́A���Y�ł��̏��Z����ɓ��ꂽ�E�C�X�L�[���X���Ȃ���A�����C���������Ă�B �����\�ꎞ�ɂ��Ȃ炤�Ƃ��ӂ̂ɂȂ��Ȃ��~�߂Ȃ��B���邳���Ă��₤���Ȃ��B�䖝���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ď��́A���ɂȂ����܂܁A
�u���邳�����I�v�Ɠ{�����B����ƕ���͂������Ƒ�������Ŏ��̕����ɂ���A���̂Ƃ��A
�u����N�A���������ɂ�����ǂ����v�ƁA���̂�������D���Ђ��玡���Ă�_�ی����Y�����ׂ̗��琺��������ƁA�܂�Ŕ̂₤�Ɏ����щz���A�_�ۂɂƂт��������z�����B ����Ε��삾�B
���̂Ƃ��A����͗����オ�����_�ۂ̂̂nj������ւāA
�u�������邳���I�v�Ɖ]�����B���͕���������납�牟�ւ悤�Ƃ����B�Ƃ���A�_�ۂ̌��ӂɐQ�Ă�c�����A�N���オ�肴�܂ɒႢ�w�ŁA �w�̂т���₤�Ȋ��D�ŕ���̖j��ł��ɂ����B���͓c�������̂₤�ȍs���ɏo��Ƃ͈ӊO�ł������B���̎��W��u�R�M�g�v�Ȃ��Ō����Ă�A �c�����Ȃ̏d���ȍ����Ȏ�������͑z�Ђ��y�Ȃ��Ƃ���ł��������炾�B�S���f�������̂ł������B
(����)
����͋r�𗣂����ƁA�����̐Ȃւ��ւ����B���ւ肪���ɁA
�u���n�ɒ�������A�c���Ɛ_�ۂ͐���������u���Ȃ��A�@�����Ă��B�v�Ǝ̂đ䎌���c�����B�����������֖҂Ȗʍ\�ւ́A���Ɉ�u�A��̂���ȘA���ɉ��̎d���������悤�Ƃ��ӂ̂��炤�B ���z�Ƃ���ɂȂ��Ă�钆���͂ǂ����Ӑς�Ȃ̂ł��炤�B��w�̃t�����X���Ȃ̍u�t�ł���A�ЂƂ��ǂ̕��|�]�_�ƂƂ��Ēʂ��Ă�钆���̖ʂ��A �O�������Ƃ̈����ۂ��łĂ�Ă�Ǝ��̊�ɉf�����B
���̒����Ƃ��Ӑ�y���w�҂́A�܂��A
�u����ɂ��Ă��c���͍���������Ȃ��B�v�ƓƂ茾�̂₤�ɉ]�ӁB�ǂ����ӂ��̂������͓c������ᛂŎd�����Ȃ��炵���̂ł���B �c���͂���낿��낵�ď������Ȃɗ����t���Ȃ��B�ʖ�̐l�����̂Ƃ���֍s���ĂЂ����Ƀ}���C��̕��Ȃ������Ă��炵���������A�����͂����m���Ă��Ȃ̂��A �Ƃ���������낿��낷��c���́A���Ƃɂ���ǂ̕����ł��ɂ����c���̂��₢�p�́A�ڏ��ɂȂ�炵�������B
�@�܂��A����Ȋ����ł���܂��B
�@���łɂ��b���܂��Ƃ��́w�_�R�x�Ƃ��ӎ��W�́A�����u���{�o�ŕ�������E�V���v����������т�t���āA���ł�1000���ɑ�����5000�����č�����邱�ƂƂȂ�A ���ʓI�Ɍ��Ö{���ň�ԊȒP�Ɏ�ɓ��鎍�l�̎��W�ƂȂ��Ă���܂��B���̂��߁u�_�R�v�Ƃ��ӌ��t�͐��A���l�̐푈�ӔC��_����ۂɔނ��ꌾ�ŕЕt����E������A ���b�e���Ƃ��Ȃ�A�L���X�g���ɉ��@�������l�炭�ꂵ�߂錾�t�ƂȂ�܂����B
�@8.�c�����Ȃ̐푈���@���̇V�@(�����m�푈����@���p�Ȍ�)
�@���āA���p�Ƃ��ӉX��������̏ꂩ��u���Ă��ڂ��H�������C�o���̈ɓ��×Y�́A�����₤�ɐ푈���������Ȃ�����A�I�n���s���̕��Ɉ���Ƃ������Ƃ��낪����܂������A �c�����Ȃ͔��ɁA���̗D�����ꂽ�R���̌o���ȍ~�A��C�Ɏ��̐��ʂ������Ă䂭�̂ł��B�ɓ��×Y�̎��Ƃ��ӂ̂́A�v���Ɛ��Ȃ��J��Ԃ��A �Y�݂̋ꂵ�݂�����Ɍo�����̂��̂ł��邱�Ƃ͂悭���͂�܂����A�c�����Ȃ̎��Ƃ��ӂ̂͌������Ȃ̐Ղ�����Ȃɗ��߂܂���B���ꂪ�܂��������ł����āA �ۓc�o�d�Y�����w�j�I������F�߂������̍�i�Ƃ��ӂ̂́A�܂��ɑ��n�̓V�˂̎�ɂȂ���̂ƌĂ�ł悢���̂ł����A���̎����A �����N�ǂɂ��ς�����u�푈���v�����ɋ��߂���₤�ɂȂ��āA����̃��`�x�[�V�������l�̂��̂����̂��̂�����Ȃ��A�������L���L��֏o�Ă��܂����̂���Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B �ŏ��ɏ������u�n���C�����s�v���A���L�ɂ����̖��ɓ��������Ƃ̂��Ƃł����A���ܓǂݕԂ��ĐS�ӋC�Ƌ��̍��͓`�͂���̂́A��ςɂނȂ������������܂��B ����́u�哌����r�W�v�ɂ������M�Ɠ����ł��B�{���͎����Ƃ��Ă����ɁA ���a18�N2��4������œ����̎�����㒆�������Ǖ��|��(���X�؉p�V��)���ɑ��B�ő����܂����A���W�I�p�̘N�ǎ��̌��e�������ĎQ��܂����B�S���Ōܕ҂���܂����A �Ȃ��ō���A���\���W�[�Ɏ��߂܂����u�G�~���v�Ƃ��ӎ����A�������e�̃o�[�W�����œǂ�ł݂܂��B �V���K�|�[���ɂ������Ƃ��A�}���[������[�̃W���z�[���o�[���ł̑̌��k�������Ď��ɂ������̂ł��B
�@�G�~���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (���a18�N2���������e�@���o) ���ڎ��W�w��̐��x
�ˌ��̖��߉���
��Ԃ܂Ï������C��
�������̖T��ɗ���
��������꓁(�Ƃ�)�ʂ���
���܂��s����@���Ȃ�Ƃ����
�Ȃɂ��@�w���`��
�ˌ����~�I
��u�̐Î�̂���
�₪�Ă₪�ā@��g�̂���
��������@�t�c���
���c�A�����B������
����A�����B�����ɕ�
�G�͍~�����@�Ƃ�
���ق݂��ɂ݂Ȃ�����
�������T�ɂ��ׂč~���
�j���ӗ܂̂����
�m��T���p����
�₪�Ă܂����ߗ���
�i���I�@�ƁB�����@���̉����̎|���肵���ƁB
�@����Ȃǂ̓I�`�������Ă�قǖʔ������ł���̂ł����A�������l�̓ƒd��ł������V�j�J���Ȑl���ς�A���Ȃȕ��i�̐؎����A�T������ɐ������R��Ƃ��������̂́A �c�O�Ȃ��猩���܂���B������������ł̌����̌������Ƃɐ��������̂́A���̑�4���W���w��̐��x�Ɏ��߂��Ă���܂��B ���x�̊��s�����͎O�D�B���Ƃ��ӂ��ƂŁA��̂ɐ푈���W�Ƃ��ӂ̂́A�\�����ϋɓI�Ɏ���o�ł���Ƃ��ӂ��̂ł͂Ȃ������₤�ł���܂��B
�@���Ă����Ő��R����搶�����̓x�̐V���w���Ɛ����邩�����x�̂Ȃ��ŁA���̑哌���푈���s���ɏ����ꂽ�푈���ɂ��āA��ς킩��₷�������������Ă����܂��̂ŁA �������p�������Ē��������Ǝv�Ђ܂��B
�u�@���l�͍Z�̂����̂܂�ď����₤�ɁA���܂�Đ푈�����������Ǝv���B�Z�̂ɁA�R�����쐴���A�̊��p����g���l�ɁA���p��Ő푈���q�ׂĂ���B ���������d��������A�o���͂��Ƃ��悭�Ȃ��B���W�ɁA�Z�̂����Ȃ��悤�ɁA�푈�������Ȃ��B����͏o�����ق�����ł���B ����������i�𑼂̍�i�Ɣ�r����̂́A�Z�̂ɐ쐴���Ə������l�ɐ�̉����������A�Ɛӂ߂�͍̂��ł���B
�@����A�f��ēɒO����́A�푈�f�������Ă��Ȃ�����ƂāA�푈�f�拊�e�g�D�̗����ɐ��E���ꂽ�̂�f���Ă���B �u�������푈�f������Ȃ������̂́A�������Ȃ���������ŁA���e�Ȃǂ����܂����B������Ă�肵���̂́A�R���ł����ǂł��Ȃ��A���݂����אl�������v�Ƃ����Ă���B �I�����l�ɂ݂͂Ȓ����˗����������B�����ĂȂ��͉̂��肾������A��������������ł���B�v(�w���Ɛ����邩�����x50-51p�ҏW�H�[�m�A2006)
�@�����Ƃ��A�c�����Ȃ��͂��߂Ƃ��đS�Ă̎��l���A�����u�o�����悭�Ȃ��v�Ǝv���Đ푈���������Ă��ł͂Ȃ��Ǝv�Ђ܂��B �͂�����]���Đ푈���ɉ��l�����͂ꂽ�̂́A�u�푈�ɕ���������v�ɑ��Ȃ�܂���B�Z�̂�������w�Z���Ȃ��Ȃ��Ă��܂ւA�Z�̂��܂����݉��l�����ӂ̂ł���܂��B �����Đ�Ӎ��g�̂��߂ɐ���ɍ��ꂽ���Ƃ��ӂ̂́A��l�̓ǎ҂ɂ���Ėٓǂ���邱�Ƃ�O���ɒu�������̂Ƃ͈قȂ�A�N�ǂ���邱�Ƃ�\�肵�č���Ă���܂��B �w�Z���Ђł��A�݂�Ȃňꐺ�ɘN�ǂ����u�������v�Ƃ��ӂ��̂����s�����̂ł����A�ł����炱��Ȃ̂͂���ς萙�R�搶�̋���₤�ɁA �w�Z�̍Z�̂Ɠ��������̍�i�Ƃ����Ă悢���̂��Ǝv�Ђ܂��B
�@�c�����Ȃ̐푈���́A�������A������݂Ă��܂����₤�ɁA�{���́u�q�u�̎��v�̉�������ɕ����߂�ꂽ�܂܂ł���͂��̂��̂������₤�ɁA���͎v���Ă���܂��B �J��ȑO�ɂȂ����A���j�ɑ�ނ���������̂ɂ́A���͂Ζ����ېV�ȍ~�S�N���̓��{�����̍��݂��]����������t�B�N�V�������������Ƃ͏q�ׂ܂����B �푈���̓��{�ŗ��s�����펞�W��Ɂu�����Ă���܂ށv�Ƃ��ӂ̂�����܂����A ����͌Î��L�̒��̋v�ĉ̂̌���u�݂݂� �v�Ă̎q�����_��(��������)�ɐA��G(�͂�����) ���u(�Ђ�)�� ��(��)�͖Y�ꂶ�����Ă���܂ށv����̂�ꂽ���̂ł��B ���łɓc�����Ȃ͏������сu��(����)�v(���a7�N6���R�M�g)�Ƃ��ӎ��ɂ�����
�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a7
�N6�����o�@�@���ڎ��W�w���W���N�ȁx
���͐g�ɎR���̏L�Ђ�тт���(�����Ȃ�)�ł���
���̗͓�����Ƌ��F(����)�Ɍ���
����͈łł͔Z������ƂȂ�
���̕��ɂ͍g���Ȃ���(�ӂ�����)�ƂقĂ��
���͎��̓�(����)�ɓV�쐯(�Ă�Ȃ₤)��A��Ă��
���̉Ԃ͎��̓����ق̖��邭����
���̍������͐H���ɂ���
���͎l�ܓ���(���̂���)�d�X(�C���C��)�������Ă��
�d�X�͂��̑��̒��ɂ˂ނĂ��
���͂��̍g����������(����)������
����͎������̗����Ƃ�Ɍ˔���������ł���
����͉d�X�̛X(��������)�ɖ_��ŝ����ꂽ
���͗��ꕔ������Ă��
���͕��w�𐾂Ă��
�V�쐯�̍�������łł���
�Ƃ��Ӌ�ɁA��i�̒��߂�����ɓ��������������ނƂ��ӎ����������āA�u���Q�v���e�[�}�ɝR��������Ă���ł����A���ɂ́A �c�����Ȃ̎��̖��͂Ɛ푈���Ɏ��镣���Ƃ��ӂ̂́A���Ђ͓�������ق���Ƃ���́A���́u��(��)�͖Y�ꂶ�����Ă���܂ށv�Ƃ��ӟT����ᒐ��ɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B ���l�����ۂɂ͕K���������Ђɏo����܂�
�u���݂̂����������̂䂫�����Ɓ@�킪�Y��Ȃ��ꂩ�m���ށv
�Ƃ��Ӊ̂��A�ł�������͂��̟T��ނ��ڂꂽ��ɊJ�����A���{���L�̒��O�ƂƂ��ɔޕ��֊J�����R��Ȃ킯�ł��B ����Љ�܂����uEin Märchen�v��u�H�̌v���܂����l�̂��̂��Ƃ��ւ܂����B�Ƃ��낪�T��O�Ɍ������Ĕ������Ă��܂ӂƁA�܂�u�����Ă���܂ށv�������ƂȂ��ĊJ��Ɏ���A �����̑叟���̊���ɐ����Ă��܂����Ƃ���ŁA���l�͍�����O�̋C���ƈꏏ�ɂȂ�A�Љ�I�ȐM�����\�w�ŏ������Ă��܂ӎ��Ԃ������܂����B ���ꂪ���l�̍K���ł���ߌ��ł������ƁA����ǂ���ƂȂ�R��̊j���A�D���Ă��܂������R�ł͂Ȃ��������Ǝv�ӂ̂ł���܂��B
�@���̌�A���l�͉�������̎��j���u���őr�ЁA����ɏI�풼�O�ɂ͕ۓc�o�d�Y�ƂƂ��ɍēx���W���|����܂��B���������x�͈ꕺ���A ���̓��Ƃ��Ėk�x�O���֑����邱�ƂɂȂ�킯�ł��B�ۓc�o�d�Y�̏��W�ɂ͌R������̒����̈Ӗ������߂��Ă�炵���Ƃ��ӂ��Ƃ́A�����̐l���،����Ă��Ƃ���ł����A ���������̌��ʂ��͂��������Ȃ������c�����Ȃ��܂��A���ǂ���^���̕s�������̂ł������B�V�c�̌��l�_�ɂ��炴�邱�Ƃ͔s��ɐ旧��������Ƃ̂��Ƃł����A ����́w��̐��x���s�Ȍ�̍�i�A�܂�푈�����ɐ��̎��W�ɂ����^���ꂸ�������ꂽ��i�̂Ȃ��ɂ݂���A���̂₤�ȕ\���ɂ���������C�����܂��B ���́u�܂�����҂�(���a19�N12�����o)�v�Ƃ��ӎ��́A���āu���҂Ɍh�点��(���a13�N)�v�ʼn̂����Ɠ��l�A�펀�����F�𓉂�ł��̂ł����A�����A ����C�n�k�̔�Q���֔邵���قǂɁA�q�X�e���b�N�ȕǐ���~���Ă���a19�N�̍�i�ɁA���̂₤�ȗ����݂��܂��B
�@�@�܂�����҂�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a19�N12�����o
�����͂͂̍��͍g�t��
�����ł����鎞�����Â���
����肠��A��(������)�����Ă�
�͂��̂͂��̂ӂ邳�Ƃɐ_�Ƃ��҂鄟��
�͂��߂Ă̏����ɂ䂫����
�k�x�߂̍g�t���邭��
���ւ藈�čg�t������
���Ђ����Ƃ��͖Y�ꂸ
�嗤�̋�����̍g�t����ɍg����
�ӂ����т�������Ă䂫��
���k�̓}�_���A�����E�P�A�A�C�^�x��
�������ɒm�炸������Ă̍��ɂ��肯��
�g�t�Ȃ�����ɂ�
�G�@�̂ݓ����ȕ��Ђ���
�܂�����₢������炸
��@�݂̂��e��(����)�������
�ӂ邳�Ƃɍ��݂��]�͂�
�O�N�o�����ӂ���肠��
�����ӂ邳�Ƃɐ_�Ƃ��҂�B
�@�펀�����F�ɑ�͂��āu��@�݂̂��e��(����)������ʁ@�ӂ邳�Ƃɍ��݂��]�͂��v�Ƃ��ӂ₤�ȁA�����v�А����������A��ʎ�(�u���Y�v������)�ɓf�I���Ă���܂��B ���̌������x�u���Ёv�Ƃ��ӋS�{�ĉp���ł̎�����я����ċC��f���Ă���܂���(�u���Y�t�H�v���a20�N3��)�A���ǂ͐���\�グ�܂����₤�ɁA �ۓc�o�d�Y�ƂƂ��ɓ��Ƃ��Ėk�x�֑����邱�ƂɂȂ�̂ł��B�����ē��{�Q�֔h�̉e�����Ɉ�����Ⴂ���l����(���c�W��R��O���Ȃ�)���A���X�Ɛ펀���Ă䂭�Ȃ��A �����l�Ȋ��ɐg�͒u���Ȃ���A�ޓ��̂₤�ɐ펀���Đ_���J���邱�Ƃ��A�^���͂��̓�l�̎��l�ɂ͋����Ȃ������̂ł���܂��B
�@�@���͐����ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a21�N9�����o ���ڎ��W�w�߉́x
���t�̒g����
�앗�̐������C��
���������ڂ����D�͒�����
�㗤���Ă��炭����
����܂ŎG�̖��Ȃ��炩�ȎR
�ߐ�����q
�����̔�̊����Ă��鉏��
����ȕ��i�̈���
���͂���˂�ɒ��߂Ȃ���
�v�ӂ��Ƃ͂��U�ЂƂ�
���T�@���́@������
�҂ė����I
�@�A���\���W�[�ɂ����܂��ẮA���́u���͐����āv�Ƃ��ӁA�푈���I���ē��{�ɋA���Ă����Ƃ��̎����������܂łɁA�傫�ȋ������������Ƃ��L���ׂ��Ȃ̂ł����A ���̎��Ǝ��̎��́A���̖{�̒��Łu�V�c�É��o���U�C�v�̍c���j�ς������蔲���ď�����Ă�鎍�ł���܂��B
�@�Ō�Ɍf���܂����A�t�B���s���Ő펀�����R�M�g���l�̐e�F�A�����h���Y�̂��Ƃ𓉂u���́v��ǂ�ł݂܂��B ���l�̐S��ɂ́A���́uEin Märchen�v�ʼn����E�������ɂȝR��߂��ĎQ��܂��B����͐��b���o���Ă���̎��W�w�߉��x�Ɏ��߂��܂����B
�@���́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڎ��W�w�߉́x
���̋Ȃ�p���܂����
���܂ւ̉Ƃ������ė���
����̂悱�̖X�ɂ����܂ꂽ�Ƃ�
���������ɂ͂�Ȃ��̂�
���܂ւ��ʐ^�ł̂₤��
���������Â��ɂ����ŏĂ��₤�Ɏv��
�����Ă��ʐ^���@�����Ă��ʐ^
���ʂ��߂ɂ͂������̂����ׂ���
�l�͂��܂ւ̂��Ƃ��l�ւ��
���܂��ꂽ���Ƃ̂₤�ɂ��₵���Ȃ�B
�@���͂₱���ɂ́A���l�̗��j�I�Ӌ`�Ƃ��ӂ��̂͊������Ȃ��Ȃ���A���Ƃ̏h�������l�̑��ݗ��R�Ƃ��Đ����A�����Ă��̗����琶�҂ł����ЂƂ����炱���̂ӂ��Ƃ̂ł���A �����ʂ����[���C�̂₤�Ȕ߂��݂��A���͊����܂��B����͂��́u���́v�̑��ɂ��A�ɓ��×Y�Ȃ�ΐ��ɂȂ����u�Ă̏I��v�Ƃ��ӎ��A ���Ђ͑����L��Y�Ȃ�u���̒��ʼn̂�����ۂ̎q��S�v�Ƃ��Ӌ�ɁA�R�M�g�h�̎��l�B�ɂ͂ЂƂ�ɂЂƂÂ��̐⏥�Ƃ��Ă���₤�Ɏv�ӂ̂ł����A�������ӝR����A ���́w�哌���푈�����W�x�A���\���W�[�̍Ō�ɓY�ւĂ��悩���������Ȃ����Ǝv�������Ƃł����B�Ȃ��Ȃ�哌���푈�Ƃ͂���ɏ}���Ď��ʂ��Ƃ̏o�����҂��������̐푈�ł͂Ȃ������Ǝv�ӂ���ł���܂��B
�@9.���͂��
�@�c�����Ȃɂ��Ă̂��b�͂����܂łł��B�����܂Ђɂ����܂Řb���Ă��āA���̖{�ɑ����Ęb���Ă�������ɂ́A�I�҂Ƃ��Đ푈���Ƃǂ������������̂��A �܂肳���̑����ǂ��ς���̂��A��ɂ��ׂ�����������r�W�ƈꏏ�Ɏ��߂��Ă�܂�����A���������Ȃ��Ƃ͏q�ׂ��܂��A���������q�ׂ����Ǝv�Ђ܂��B
�@�킽�����v�Ђ܂��̂ɁA�푈�ŕ��������ɂ����ẮA���̂��߂Ɏ��Ƃ��ӂ̂��A���̂���ŎE���ꂽ�Ƃ��ӂ̂��A�펀�̎����Ƃ��Ă͓����Ȃ̂Ɉ�ЂȂ��Ƃ��ӂ��Ƃł���܂��B �����Đ_�ЂŐl���J��Ƃ��ӂ��Ƃɂ́A�_�ߏ̂ւ�Ƃ��ӈӖ��Ƃ͕ʂɁA���O�Ɏ��ނ����A���̍��݂���߂鑤�ʂ�����̂��Ƃ��ӂ��Ƃ��A �O���ɂ����Ɨ������Ă���ӕK�v������̂���Ȃ����Ǝv�Ђ܂��B�܂������Ɍ����ẮA�u�A�W�A�����̂Ȃ��ł̓��{�v�Ƃ��ӂ��Ƃ���j�I�ɍĔF�����ׂ��ł��邱�ƁB �u�哌�����h���v���v�Ђ����������̂ł���Ȃ�A�p���ʎ߈ȑO�̂܂������{�l�̂�����A�_���܂ƕ����܂ƍE�q���܂��������ĕ�炵�Ă�A ���E���̂ǂ��ɂ��Ȃ��₤�ȍ����Ɏv�Ђ�v�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł������B
�@���̗��j�̍Ōオ�u�s���������v�Ȗ�ł�����A���������Ă������I�ɉ��߂���A�g�������Ƃ���\��������̂́A�v�����Ȃ����Ƃ�������܂���B ����Ȃ�D��ŏ��X�ϐl���Ђ���邱�Ƃ��A���l�Ƃ��Ă͑I�Ԃׂ����������A�Ƃ����͍l�ւĂ���܂��B�l���̎O���ł���A�V����n�R��a�C���ցA ���̍ۂ͊��D�̉B�ق̉B�ꖪ�ɂȂ邩������܂���B����K�Y����Ƃ��ӁA���s�ň�l��炵�����Ȃ���N���Ōl�G�����o���Ă���ς͂�Ȃ�����������܂������A ���w��̕t�����Ђɂ����Ă͌��ǒN�ɂ��m��ꂸ�ǓƂ̂����ɖS���Ȃ�܂����B���O�A���̎G���̌�L�̕Ћ��ŌJ��Ԃ��i�ւĂ���ꂽ�A���{�Q�֔h�Ƒ哌���푈���̂ւ�ێq��K�ȕ��������A ���̕ЁX����p���t���b�g�G���̊��s�����\�N���Ђ��ނ��ɑ�����ꂽ�p�ɁA���͂����݂䂭���̓��{�ŁA�߂Ƃ��ӂ��A�M����S�����Đ�����(�܂�����)�Ƃ��ӂ��Ƃ́A �p�ɂ����Ă������ӂ��ƂȂ̂ł͂Ȃ����ƁA�ꐡ�v�������Ƃł���܂��B
�@�����قǂ́u�ނȂ����v�Ɖ]�Ђ܂������A�����̓��{�̐����Љ�Ƃ��ӂ̂́A���̖{�̑O���ɏW�߂�ꂽ�u�哌���푈�}���r�W�v�̉p��ɑ��āA ���������u�������킯�Ȃ��v�̈ꌾ�ł��B�ʂ����Č��݂̓��{�́A��������̗��j�F���̎w�E�ɂ��Ă��ꂱ��]�ӑO�ɁA���͂�łтē��R�̍߈���c��ɑ��ĔƂ��Ă����̂̂₤�ɁA ���ɂ͎v�͂�ĂȂ�܂���B�O�D�B���͂��łɐ펞���̓����A
�u��X�̖ʔ�����ʊ�ʂ̋������d�ȕs���R�Ȕ��f�⌋�_���A���ꂾ���ɂ܂����d�Ȉ��͌��z�Ȍ��ӂ̌��������̉��ɒ�o�����̂ł͂���܂����v
�Ƃ��Ӌ�ɁA�u�V�c�É��o���U�C�v�̍c���j�ψ�ӓ|�ł�������҂����̍s�������뜜���Ă���܂������A�푈�ɑ���
�u���͂Ƃ����Ƃ��̒P���Ȏ����ł͂Ȃ��A���̂������ł��̂悤�Ȏ��������c�������Ȃ������t���������Ƃ������l�Ȏ���(���c�W�w���{�V�I�x1973�N�A���i�ވꎁ������)�v
�ɂ��ẮA���݂̓��O�̐��E�ςɂ���Ĕނ炪�J�߂��邱�Ƃ̂Ȃ��₤�A�����̎v�Ђ����̋��[�Ƃ��Ď��R�ɕ\�����A�U���ӂ��Ƃ̂ł�����{�l�ł��肽���A ���̂₤�Ɏv�Ђ܂��B
�@�܂������Ƃ�Ƃ߂Ȃ��I�͂���ł������̘b�͂���ŏI��܂��B���肪�����������܂����B