���W�w�嗤���]�x
�c������ ��W
���a15�N9��17�� �q�����@��
(���Y�����p�� 8)
21p 217.5cm �㐻�J�o�[�@\1.00�@(1000��)
�����K�F����
(2006.11.10up�@/�@2006.11.24update)
Back
���Ȃ����݁y�c�����ȁz�w�嗤���]�x1940
���W�w�嗤���]�x
�c������ ��W
���a15�N9��17�� �q�����@��
(���Y�����p�� 8)
21p 217.5cm �㐻�J�o�[�@\1.00�@(1000��)
�����K�F����
�@����͂킽���̑�W�Łu���W���N�ȁv�ɂ����̂ł���B�킽���͂��̐ق��𒆎x�Ȃ�@�c�P�����ɂ������悤�Ǝv�ӁB����͂������ӂ킯����ł���B
�@�c���͂킽�����u���N�ȁv���o�����Ɗ������������ď��a�\��N�̏\���ɉ������ꂽ�B����ɂ������̈���������₤�Ɏv�ӁB�����サ�炭���͌̋��̘A���ɋ���ꂽ�B
�嗤�ɏo���̖�����ꂽ�̂����N�̎O���������B���̎��A���̓R�M�g�̔��s���ɑ��B�ł킽���̎��W�����߂�ꂽ�B�킽���͂����`�֕������Ƃ���ϊ��������B
���̐ق����W�ɂ͐�y��m�l�̂��肪�������オ���������A���̂ǂ�����܂��āA
��n�ɓn��O���̂܂�������킽���̎��W�̂��Ƃ�O���ɂ����Ă��ꂽ�Ƃ��ӂ��̂��Ƃ����������B
�@���̂��֎����ɂ͂킽���ΐ�n�̓��B������ւ�������������B����ɂ͂������ӓ�т̎������Ă�B
�@�@��
�o���̓��ɁA���Ȃ��̎��́A
�����̔ޕ����玄���ĂB
�킽���͂��Ȃ��̎��W�������ɒu�������ƌg�ւė��������B
�킽���͒T���Ƃ��A���̑��Ô铽(���݂���)���ꂽ�邽������A
��(����)�����G�}�����ɊJ���č�(����)���₤�ɁA
���Ȃ��̎��W���Ђ̂ɂ͂��(�Ђ�)���B
�����Ŏ��͂�����(����)�������B
�̏�ɂ͑������ɐ�����Ă�B
�킽���͂��̏����ő���E�݁A���Ȃ��̎��W�ɂ��Ƒ}�B
�@�@����
�F�̔��������W�ɁA�킽����
���X�A���X�œE�݂Ƃ�����Ԃ�}�B
(�����A����Ȏ��A����ȏ��X�I)
���o�āA���W���J�����A����瑐��
�����ɉ����ԂƂȂ�āA�Ђ����
�₳�����p���A�����܂c���Ă�B
���͂₠�̂�͂炩���͖��������
�߂�����̌`�ɂȂ�ʂĂĂ͂���A
�c�������Ԃ́A���̌������B
���̈�̉Ԃ��A�킽���͈�������߂łāA
�j��ʂ₤�ɂ��Ǝw���Ĕ������Č�����ɁA
�ԂɓY�ւ�t�̗��ɂ�����Ė��Ԃ�������Ƃ��Ă�B
�@�@�c���͂܂����Y��������ł��Í��W�ȂǂƋ��ɂ킽���̐ق����W���w���̈Ԃ߂ƂȂĂ��R�����Ă���ꂽ�B
�@�c���̋��������͑S���P����ԂƂȂĂ�ēG�������ߋ������ɂ݂����܂ܑΛ����Ă��B�₦����ْ����v��������ӏ��ł���B��R�̉����̓��������݂��Ă��̉��Ɍ��ŐQ�邾���ŁA
�钋���ʌ�����ɂ��Ă�����Ƃ��������B�C�܂������ǂ����Ɏx�ߕ��̌��e�ۂ������ł����ŗ���ƕ������B�ʂ��Ę@�c������ɐ폝�Ĉꎞ�㑗���ꂽ�̂͂��̔N�̏I��߂��ł����B
�킽���͂�����Đg�̂Ђ����܂�v�Ђ������B
�@�S�ア�킽���ɂ͂������ꂢ���Ƃ����Â����Ƃ̕��������B�������킽���ɂ͂܂������ɂ��Ƃ�y�m�F�̂��ƂƂĂ��ȂقɎ���ʂЂ��ݐS������A
�܂���т�f���ɂ���͂��ʒm㵂̏����B���������X���̋��ɂ����Ă����@�c���̂��Ƃ����͂��̂킽���ɂ��f���ɑՂ����Ƃ��o�����B
�]�Ă���Ȍ�킽���̍�i�͎��Ɍ����ď����Â���ꂽ�B���ꂪ���̉������N�L�]�ł���Ȃɗ��Ă��܂��̂ł���B
�@���̎��W���܂��@�c���ɂ�ēE�܂��嗤�̔������ԁX��}�ނ��Ƃ��o����ƐɎv�ӁB
�@�@�@���a�\�ܔN�Z������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c������
�����@�@�@(���a15�N9���@���Y���I 9����)
�n���[�a���͈���Z�N�Ɍ��͂�
(���̗��N�ɂ���͐��ꂽ�̂�)
���̏T���͎��\�Z�N�Ǝ���������
��㔪�Z�N�ɍĂь�����Ƃ���
����͂��̏���ǂݐS�y���܂Ȃ���
��������͈�x�����̐������Ȃ����炤
�v�ӂɐl�Ԃ̑����ӂ̂�����ɓ������̂�
�m�Ȃ���l����͂���قǓ
���l����l������܂���̂�
����̒m�Ȃ͂���̎���ɏo�ė���̂�
����̗��l�͂���̐����O�Ɏ��̂�
�c���O�[�X�@�@�@(���a15�N6���@�R�M�g 96��)
�������t��(����܂�)�Ɠ̏�(�Ƃǂ܂�)�̗т̒��ɔނ͌e�ւ�
���ē鎭�i�g�i�J�C�j�����Ў��̓���V�Ђ�����
�쐶�̌I�l���(�Ă�)�ƌςƂ���@�F�ƌՂƂɖT�ЂĖ��肵���̂����Ɍe�ւ�
��ق��o�ł���̓�����̎}�Ɩџ��i�t�F���g�j�Ƃ�萬�肵
�����i�E�B�O�����j�̒��ɐ����܁i�X���[�s���O�o�b�O�j�ɖ��肵���̂����ɖ����
�����(��������)�ƐY(�͂�)�̎��Ƃ�V�Ђ����̂��̍����
�Ă̖��邷����A�x(�����O�_���X)���ǂ肵���̂����Ɍe�ւ�
�I���N�}�́A�A���K���́A���i�̗͂��ɉ���
�[�[���́A�����]�A�A���O���̗͂��ɉ��ЂďZ�߂���̂̈�l�����Ɍe�ւ�
�V�ɋF�莵���ɋF��n�ɂ������̐_����
�����ɉ̐_���Ղ肵�h�i�Ȃ���́@�b�܂ꂵ���̂����ɖ����
�r���F�̒܂��̂�����M(�ӂ�)�߂���Ղ̉���̂��ꂵ����
�����ꔭ�̏��e�̍���O�z�̍��ɂƂǂ߂�
�������t���Ɠ̏��̗т̒��ɉi��(�Ƃ�)�ɖ����
�킪�a�����@�@�@(���a15�N9���@�R�M�g 99��)
�����O�\����@�Ă̐s�����
�������炷�ׂĂ̕��ɕY�Ă�H�̋C��
��╨���Ƃɂ܂ł�����t�ɂȂĂ��
�l�̋L���̒��ł͂܂����̓����ʂ�
�吳�V�c�̓V���߂̓��̊ۂ��Ђ�߂���
�ċx�݂̍Ō�����Ƃ������Ɣ߂��݂Ȃ���
���̓��������̓��Ƃ��ꐡ�����ւ������
�l�ɂ͂����ċx�݂��Ȃ����Ƃ��������Ȃ�
�H�͕����Ƃ̓V��Ɍ��Ă��q�������̂��̂�
�������Ă͂��͂��Ƃ͂��߂��Ă��
�Ō�̐䂪�e�����������
���j������ɕ������𗧂ĂĂ��
���̊�̖͐̂l�����肾�ƍȂ�����
Ein Märchen�@�@�@(���a15�N8���@�ނ炳�� 8����)
�Ő��̂܂�Ȃ��ɕ���(�ӂ�����)������
����ɉe�f���Ğ�(�ɂ�)�̎�������
�����ň������l�̏������֕�(�����f)��x��
�x����č��炤�Ƃ�����֎q���Z�����Ȃ���
��l����������ċ��������ɂȂ�
��͐��_�͔������̌O�������
���̎��l�͌��������@�K������
�����ǂ��̈�l�����͑����v������
�����ė֕��̓������Џo���Ē��߂�̂���
���̊y���������ɂ��s�^���������̂��Ƃ��v�ӂ�
�ӂ����ƐS�����܂�̂���
�������s�� 1 2�@�@�@(���a15�N8���@���Y���� 26��)
�ݐF(�ɂт���)�̊C���k���߂���
�Ⴂ���R������͂ޏ������s(�܂�)�ɍ~�肽�Ƃ�
������������Ă��D�Ԃ͂������̌��ӂ։B�ꂽ
�w�O�̍L�ꂩ��꞊(�ЂƂ���)����哹�ɂ�
����(�ނ�����)�����������グ�Ă��
�����̏���ނ��Ă��̂�
������ٔ����ƌx�@�Ǝs�����Ƃ��炤
���v���f�������������͒��w��
��Ԃł͏������ދ����@�҂ł͎ԕv�������肵�Ă��
���̂������s�x��̕�������X�͏������Ŗ�����
���a�I�����͂����ł��s��̉̂������Ă��
�����@���Ƃ֎s���ɑI��邱�Ƃ����炤��
�܂����Ƃւ��̎s��Ԃ̎��l����ւ��邱�Ƃ����炤��
��������܂��₤�Ȏs
�M駂̍J�ɂ��ā@�����ꔫ�̍g���V�����i�[���j���[���j��u����
�킪�Ƃ��Ȃً��ꂵ���v�͂����
�@�B�ɂ��Ă̊��z�@�@�@(���a15�N5���@�H�Ƒ�{�U�O�V�� 5/27)
������˂������Ɉ��镔���̓s�J�s�J�P��
���镔���͔��Ɩ��Ƃō�������Ȃ���
�݂�ȋٖ��ɑg���͂���Ĉ�̂ƂȂ�
���̎n�Ƃ�҂Ă��@�B
�ǂ��ɂ��̗͂̎�̂�����ł�邩�͂킩��ʂȂ���
�S�̂Ƃ��ėY�X�����C鮂��Ă�
���ł������o�����������Ăǂ���ƍ��Ă��z
�����o�Z�̂��тɒ��߂Ȃ���ʂ����w���̓�
���̂Ƃ��̊��������X�v�ЋN��
��Ƃ��ĉ�(�Ђ�)�������̌����Ă̂Ƃ��ǂ���
�s�g�ȗ[���@�@�@(���a15�N5���@���V�� 5/20)
���̏I�������čs������
�����ɂ��(�ɂ�)���ɕ�F���Y����
���炭�͂��Ɖ����䂭��Ԃ̚b������������
���������ł��ꂪ�����Ȃ��Ȃ�J�[���̂������
�g������(�e�[�������v)����h�ꂷ���
�l��(������)�͐Â��ɂȂ�z�e���̐~�[��
�H������Ӊ������X��欂���
�q�������͗��e�ɁA�����͗��l�Ɋ��Y����
�A�R�̗[������������ɗ����͂��߂�
����Ȍ`�̉_��s�����Ɍ����Ă��
���ĂЂƂ�̂���͗��ĉ��y���ɂ͂���
�����s�i�Ȃ̃��R�[�h��������
���ꂪ���܂ւ̎������[������
���N�@�@�@(���a15�N5���@�ᑐ)
�͖�i�A���C�j�֖l�������̂͏\�Z�̎�����
��\����(�T�U���N���X)��A���S����g���ԍ炭���K��(�Ԃ�������)
���ق�̍����仁A�f�](������)�\�\�����������̂���������
�`�g��(���イ���傤)�����Ă��ߏ�������������
���đD��(�ӂȂ�)�Ђ̑����Ƃ�����뗤�ɏ����
���H(���r�����X)�߂��ܓ�(�����݂�)�ł䂫���Ӑl�̊�̐���
����킩���ʌӋ|�̉�(��)�A���ƏƂ���̂Ă肩�ւ�
ῂ䂭�����ꂵ���ĉԂȂnj�������₾��
���͐����������Ăǂꂪ�ǂ�Ƃ��m��Ȃ�
�����ɉƂ����Ђ����āA���V�u�ق̒u���Ă���
�킪��(��)�̊������Ђ����Ėl���A��(��������)�������̂�
�͖�֖l�������̂͏\�Z�̎�����
���Ҏ� 1 2�@�@�@(���a15�N4���@���� 4����)
������͐��Ղ����A���
�܂���𐁂��ʗ��t���̗тƂ�������
���̎��ɖl�͒������ԁ@���Ă
������ɂȂ��F�B�͊P���Ȃ���
���̊O�̕��i�����߂Ă
�r�X�������i�������ꂪ�m���̐l�Ԃ�
��̂Ȃ�ƌ�������̂�
�l�͂��̎c���Ȏ��₪��������
���������肰�Ȃ������t�̗��邱�Ƃ�
���Ƃ����҂��ĂȂ��̂ɂ��ǂ��ǂƌ��
�a�l�͂܂����̕s���ȊP�����I�ւĂ���
�Ⴂ�m�ꐺ�ł����]��
�u�������t�����������悭���Č����̂�
���̊��҂Ō������G�߂͂ƂĂ������₷�����v����
���ܖX�͉萁���@�R�X�͐�
�G�߂̊��҂͂��ׂĖ������ꂽ�I
���������̕a�l�́H�@���҂����҂́H
�����̂����鑋�ɂ͕~�z(�V�[�c)��������Ă�邪
����ɂ͎r�L�����т���Ă��̂��B
���� 1 2�@�@�@(���a15�N4���@�V���� 4����)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������߄���
���̓��݂͂�Ȃ��₢�f�U������邵
�}�}�̌��t�����Ȃقɕ����Ȃ�����
���ɂ��K�N���Β|(�J�[�l�[�V����)���A�����������Ȃ�����
���̂����������ɐ���Ă����
�������͔g�~��ɍs�Ă݂���
���T(�X���[�f��)��������(�m���E�F�[)�����A�ǂ����₵������
���D��������Ђ��蔑�Ă��
��������Ă���ƋC�����܂���
���ꂩ��V�A�g������D�D������
��R�̏�q�����₩�ɍ~��ė�����
�����čŌ�ɏo�}�ւ���l����Ȃ��Ȃ�����
������鞂��������k���~��ė���
����Ɗ��������Ă������Ă��
�u�����A���ꂪ�j�c�|���A�\�N�ڂ̃j�c�|���v
�������͂��̎��A���݊�Č�����
�u���k����A���Ȃ��̑��̋�؍����L�q�ł���v
���̂Ƃ��������͂ƂĂ��K��������B
�C�l�z�e���@�@�@(���a15�N2���@���Y 2����)
�������ɔ~�̂Ђ炭�ɂ͂܂��܂�������
���̎Ō���������
�Q���ׂ����q�Ɍ`���������̕��֕����Ă݂悤
���܂̋x�ɂ��y���݂ɂ���e�q�͗����̂�����
�Ȃ������Ă�Ċ�Ȃ��ȗ��l���u��
���~�������ȋ��d(�{�[�C)��ɂ��������͂Ă���Ȃ�
���̂����ۂ��|�^�[�a���⍻���ނ₤�ȎM�X�ɂ�
���Y�����Y�����������₤��
�����~�̓��̌X���ʂ���
(���̂₤�ɒZ���l�����������)
�i�F�̂������ւ���s����
�Q���ׂ����q�Ɍ`���������̕��֕����Ă݂悤
�c�I���Z�S�N�̒��@�@�@(���a15�N1���@���Y���I 1����)
��ԑ������z�̌�����
���o��ܘZ�x�O�@�瓇�̐��(�V�����V��)���̐�ڂ������߂��Ƃ�
���̑傢�Ȃ�N�̒����͂��܂�܂�
���̐�����Ɖ��\(�͂ȂÂ�)�𐼐i��
�x�m�̒���^�g�ɐ��߂邱��ɂ�
�߉q�����������̋N���h�ڂ���ЁU��
�킪�ƂɌ�q������Ђ炫�܂�
�܂����̕��͖��Ă�܂����@���̖����
�݂Ȑ[�����҂̖������Ă�Ȃ���ł�
�����Ėk���A�ϓ�A�����A�J���A���c�A�싞�A�Y�B�A
�@�쏹�A�����A�L���A��J�̏\��̏ȏ�ł�
����ʐl�Ƃ��ĕ���������҂Ă�܂�
�Í����ł͌R�n������
�ɕE(���Ă���)��k�͂��Ȃ��獂���z���܂��B
�D�� 1 2�@�@�@(���a14�N12�� �������_ 12����)
�D��̒����Ɉ�̎ԑ�����~���Ă
�G�߂͐��ɒ��~�@���͔���ł���
��ɂ͋Q��Ǝ��a�Ƃ��ے�����_������㫂߂Ă
���̎Ԃɂ�q�H�ƌĂꂽ�j��
��(����)�����������߂ēƂ育�Ƃ�����
�u�ǂ̉������䓙��e��悤�Ƃ͂��Ȃ���
�����Ďt�͂킪���̐M�����Ȃ��킯��
�킪���̍s�͂�Ȃ��킯���l�ւČ��悤�Ƃ�����Ȃ�
�킪�m�A�킪�m�ɑ���ʂƂ���͂Ȃ���
����͎t�̎��M�����߂������֎v�͂��v
���̎Ԃɂ�q�v�ƌĂꂽ�j��
���������Ȋ�����Ȃ���Ƃ育�Ƃ�����
�u�ǂ̉����������e��悤�Ƃ͂��Ȃ���
�t�̓��̎���Ȃ��Ƃ𗝐��ł͒m��Ȃ���
����̐��q�͂��̑傫��������Ƃ����k�߂�
�l�ɗe�����₤�ɂ���̂͂킯�̂Ȃ����Ƃ���
�t�����ނƂ������Ă��ꂪ�߂����v�͂��v
�܂��ʂ̎Ԃɂ�畣�ƌĂꂽ�j��
���̎ᔒ���̓����������ēƂ育�Ƃ�����
�u�ǂ̉������䓙��e��悤�Ƃ͂��Ȃ���
�����Ă��ꂪ���ł͂���ɂƂĊ������̂�
�Ȃ��Ȃ�e����Ȃ��̂����ł���N�q�ł��邱�Ƃ�
���X�Ɋm�M����Ă��̓��Ǝt��M����S��
���ʂ��Ƃ̏o����̂��ꓙ�K���Ȃ��炾�v
���̂Ƃ������̎Ԃɂ�V�N�̂ЂƂ�
�Ղ������炵�Ď�(����)�����Ђ͂���
���̐��Ƃ��̋Ȃ͞D��əz�X�Ƌ������B
�嗤���] 1 2�@�@�@(���a14�N12�� �������_ 12����)
�[�邲�Ƃɑ�C�̂قƂ�̋u�ɗ���
���Ɍ��Čږ]����̂����͂��ƂȂ�
�����[���̒����Ƃł͔g���}�ɍr���Ȃ�
��R�̙ꂫ���������@���̒��ɂ�
����ȂԂԂ����܂��Ă
�����Ă��̈�������]��
�u���̂��߂ɂ��O�͉��������̕��Ɍ��ӂ̂�
���̊C�̔ޕ��ɂ͓ݏd�Ȗʖe������
�ܐ�N��晍�(������)�Ɨ����̗��j������
���F���������������s������݂�
�����œ��X���Ќ�����忂߂��z�Ă�邾����
���̑��ɉ������Ă��O�͒��߂Ă��̂��v
����ɑ����͔���g���Ă������ւ�
�u�����Ƃ����̂��߂Ƃ���͂Ȃ��ł����
���̖�Е��ɂ͑G�������̂��܂��Ă�邩���
�����������Ă��O�ɓ��ւĂ�炤
�킪�c(����)�������ӎu���@�~�]�������Ƃ�
�Ȃىʂ���ʑ傫�Ȋ�Ђ��Ƃ�����
���ꂪ����̌��𑛂����Ď~�܂Ȃ����炾�v
�����]���Ƃ��[��̑��ɂ̒�����
�����̓�(�p�S�^)�A���܂��̝i��(�A�[�`)�A���܂��̏�O�Ȃǂ�
�Ɨ�(�������)�����F(����)�ɋP���̂��������B
�����������悤�ƂƂ߂邷�ׂĂ̐l�Ɉ����ꗝ����������
����ƌ���Ƃ���I�яo���ꂽ�ł����������{��ŒԂ�ꂽ����
���o�ɂ͔���^�֒��o�ɂ̓��Y����^�ւ����
��������̃t�B�N�V�����ł���t�B�N�V�������猻�����������������
�������������ƌĂ�
��N�@�@�@(���a14�N12���@�F[��A] 30��)
�킪���V
�������W�R����Encyclopaedia Britannica(�G���T�C�N���y�f�B�A�u���^�j�J)��(�Ȃ�)�ׂ��鏑�I�̏�
�A�y���A�t���X�R�A��̕����A�V���ƂȂ�т�
�͞ǂ��s�����N����(���ꂱ����)����
��������鎞���̊��|���o��
�{�Ȃ������Ⴋῂ��R������
�u���Ă�ꐶ������Ɂ@�ւ�͂�����
�@���S�̎�(����)���肵�����͍��̂킪����
�@���Ȃ����Ȃ���Ȃ��`�[(������)�݂̂Ȃ肵��m�炸
�@�������̎�(����)�ЂƂ�̏���������������
�@��Ђ̎�(����)�ЂƂ�̐�m�̌����������炳������b(����)���݂�
�@���čV�R�ƌ��������炭�@�m�Ȃ��N�ɋ��߂��
�@���ܐ�N�@��������ɂ����ċ����������ɗ��߂��炸�v
��(����)�ʂ�Η܂����܂����v�Ɖ�����O�j�̏��忂�������
�C�b�@�@�@(���a14�N9���@�l�G 50��)
�C�̎��Ԃł͐��߂���Â��߂������낪�ł�����(�̂ǂ�)�ł���
�����ɕՏƂ�����͒��V�����X���ĕ���
�ނ݂͂ȕ\���ттē��]���Ƃ�܂��Ă��
�g��C����v�����N�g���⋛�̌Q���ߐ�����
�킽�������������ƕ�Ƅ����Ƃ͊�𖾂��ċ�����Ă��
�C�Ƌ�Ƃ̉����鑊��
�ˑR�A�q�̂킽���ɂ͂��������|������
���̌�ɂ͖邪���邾�炤�@�₪�Ē���(�����Ђ�)���͂��܂邾�炤
�ہA���܂������̂��₩�ɒ������Ȃ��痬���̂�m��
�����čł����Â��Ȃ��̎����ʂ��L�������킪�]����
�r�X�������̂̉�ɂ�Đ��f�����u�Ԃ�z��
�킽���͕����Ăѕ���Ă�
���̂₳�����u��(���X)�H�v�ɓ��ւ�̂����߂��
�����ɂ��@�@�@(���a14�N10���@���Y���� 16��)
��͐�����@���@��
����(�X����)�̂ނ�͐��ɕ���
����̂��Ěe�����͂�
(���̏�炩�̂����͂���
�@�����Ă����Ă���˂�)
���Ă���q(����)�Ɗ݂ɘ�(��)��
Swan(�X����)����(��)��Ƌ��ӂ��
�������O(����)���J�肩�ւ�
���̐����̂�������
���X(����)�����������
����ɍV(����)�߂Ă����䂫��
��͐�����@���@��
�܂��ЂƂ������������
�s���@�@�@(���a14�N10���@�R�M�g 88��)
��\���قǒJ��ɉ��ēo��܂�
�O�̟�(����)���ƈ�o�̎R���Ɩ����̕S���̉Ԃ�����
���ł͗�������������
����S��\�Ă̐��(�݂Â���)�R���_��ттĂ��
�����ւ�Ή_�R��z�������̑����P��
���̏��������䂪�g���ӂƂӂ肩�ւ炷
�����Ă��܂͎R�F�ɂ��ւ��ǂ낫��������
�����Ȃ邩�ȁ@�R�́@�n�́@�V�́@�_��
�đ��@�@�@(���a14�N8�� �R�M�g 87��)
�������̗���Ɣ����q�Ƃ̊�
�đ��̒��ŋO�����J�[������Ƃ���
�����ɔޓ��͑�������҂��\�ւĂ
���̊ۂƐF��ȉ��ЂƂ����ā\�\
�����l�\�����{�s���}�͎��삷��
�J�[���ł���͈�x���x���ɂ�
���̂Ƃ��ޓ��͓��ɏł����������
���X�X
���͑�N�̏�ɂ�������
���ɏł�����͂�����
�����R(������)�Ɂ@�������y��
���܂����̍��}�ւ邱�Ƃ��炤
���肬�肷���đ��̃J�[���̂Ƃ���
�|��Ђ邪�ւ茩���Ȃ��Ȃ����̊ۂ�
���������юv�ЕԂ��Đ������Ƃ��炤
�x�m�Ɋ���� 1 2�@�@�@(���a14�N10���@�V���� 10����)
�Ă̓����̎s�X�͂��́u�]���v�̃J�X�p�̒��̂₤��
���V�ɃL���L���Ɣ��˂�����(��)�Ă
���ɏo�悤�@���ɏo�悤�@�����ɂ̖͗X��
�S���Ԃ߂镗�ƒ��̉̂�����
�@���͗��ɏo�������Ă�����̂܂ւ�
�@�̖X�������@���ƒ��̉̂���
�@����������@�x�m�́@���F�̃A�t�^�k�[���𒅂�
�@���̂ЂƂ̂₤�ɗ����ɗ��Ă
�b�{��[�ɔ����@�B��܂ŗ����Ƃ�
�x�m�͗[�f���ɐ[�g�ɂȂ�@�₪��
���ɂȂ�@���ɂȂĕ��Ă��܂�
���̂Ƃ����̂ЂƂ̎��̑���(�J�[�e��)�Ɏ���
�����_��������Ƃ���ӂ̂�������
���͎ԑ��Ɍ��Ă�ā@���������řꂢ��
�x�m��@�x�m��@���₷�݁@���̕x�m��
�z�K�̏h�Ŏl����x��đ��d��(�X�^���h)�������Ƃ�
���͂���x���Ђ������řꂢ��
�x�m��@�x�m��@���₷�݂��@�������������
�z�K�̒��@�@�@(���a14�N10���@�F�J���{ 10����)
�R�X�Ɉ͂܂ꂽ�Â��Ȍΐ��̕���
�Ȃ��炩�ɍ~��Ă䂭�Q��������
�čՂ̗����@���͔��Ă܂����Ă��
����̖�̂���religious�ȋ����͂ǂ��֍s��
���������_�̉e���ΐ����悬��
���͌K���Ɩ���钬�ɂ��₢��˂𓊂�������
�隬�ɂ��@�@�@(���a14�N7���@�R�M�g 86��)
�܌��̛ӂ����R�ւƓo��
��������@�������������Ĕ�������̐�
�ꂵ��ῂ䂢���̒��ɐ����Ă��₤�Ȉꍏ(�ЂƂƂ�)
�����Đ̂̏���ł��钸��
��ʂɃA�l���l�̉Ԃ��炫����
�M���Ȃ������K�N���b(��������)�ɓZ�Ђ��Ă��Ƃ���
��(��)�悤�@�������̂̐l�̖��͐��ւ܂��@����ɂ�
�ڂ�����ނقǔ߂����v�Ђ�����
�܂����o�ė��������g���镽���̂������������܂�
�ڂ𐅕��ɕ�(��)�Ă@�����Ɍ�����(��)��
��́u�i���v�̐Ⴊ�@���肰�Ȃ�
����������ȏ�ᰂ������ƂɒX�ւĂ��̂�����
�ԖɊ��@�@�@(���a14�N7���@�{�Y�W�] 7����)
�`�̉Ԃ��炯�Ύ��ɂȂ�����v��
����̍�����������q�������ĉԂ�҂�
��ɂ��t��(�悠��)��҂��@���ɂ͗[��]��
�u���̂�����@�ς�ĉ��ɂȂ���ށv
�u�V���A�����䗗�Ȃ����v
���@�@�@(���a14�N8�� �l�G 48��)
���z�Ԃ̂����͂�@�|�M�̂��Ԃ�����
�����ɐ��܂͂���Ă�傫����̎���
���܂��̓����ܖ�����
�|�Ɛh�q�Ɩ��\�̏����������
��ǂ肬�@�@�@(���a14�N5���@�{�Y�W�] 5����)
���̋ΐ�̑��̂܂ւɂ�
�傫�ȉ|�̖����Ă��܂͗��t���Ă��
���������̎}�X�Ɋ�(��ǂ肬)�����Ă�Ă��ꂾ������
���ꂪ��Ɏv�͂���������̂�
�ؗ��̌��ӂ̓������낢��̐l���䂭
������͊`�F�̕��̎��l���s��
�����ߌ�����ɂ͗X�֎����Ԃ��䂭
����Șb�ʼn��̋Ζ��Ԃ���z���o���邾�炤�ˁB
�~�������@�@�@(���a14�N5���@�V�� 5����)
��q�̔M������Ή��ɏo�Ē������
��ɂ͉ԍ炭�Ȃ�
�ԏ��̓���Ɓ@�����̈�p(�ЂƂނ�)
�~���z�����݂̂ȋ���
���т������킽���D�X�Ɩ点��
�����Ȃ��킪��ɑ납���葓���k(����)��(��)��
��q�Ƃ��Ɗ��N���Ƃ��ɏZ�މƂȂ��
������@��q��
����@�@�@(���a14�N5���@�V�� 5����)
�������s���Ĉ������Ƃ�
���o�@�Ƃɂ��܂˂�������Ђ炭�ɉ����ĒĂ�����
��̏�������鏼�̎�q�����
�y�ɂ����ȂΈ���Ƃ̑��(������)�ƂȂ�����
�����銴�S�ɕ�����̑���
�����Ђ��@�@�@(���a14�N8�� ���Y���I �n����)
��(����)������(�܂Ȃ�)�@��������@����������
�₩�Ɋp�Ɣ�(��)�����ď��肵�g��㵂Â邲��
���̑f�U��̗D������
���߂Ă���Αz�Џo(��)��킪��߂��Ƃ�
���܂��@���ɔ�(����)�ւĂ悫�ЂƂȂ�˂�
��������ǂ�����ɂ���v�Џo��
������@�@�@(���a14�N5���@�Z�̌��� 5����)
�킪�F�̑�(�ق�)��̓��Ȃ�
���番�����ɂ̂ڂ�Ό�(����)�����
���������ȘZ��(�݂ȂÂ�)�̑��z�̉�(����)
�݂Â��݂̐��͂����܂���(��)�Ă킽��
�߂����R�̐t�݂Ȃ��Ȃ���ނ�
�炭�Ԃ͎}���Ă��Ă��Ȃ���̕X���ԂȂ�
�y(����)�t(����)�ł䂭�D�̂���
�����q(���Ƃ߂�)�݂͂Ȑ��߂Ēj(���̂�)�ə~(��)��Ď��ɂ䂫�ʄ���
�����Ɋy�̉��͐��ƂƂ��Ė�킽��
�Ȃ݂��X�ւ��킪��ɂ�
���̐��ɂ���ʌ��i(����)�����
���{�̏t�@�@�@(���a14�N3���@���Y���� 9��)
���ȂقȂ邱����ɂ͏t�����̂���
����ɂ܂����X(�����炢)�̏����̂���
���R�̗s(������)�Ӑ�͌����Ă���ǂ�
���N(����)�̗��t���킪�Ƃ肠��
�Ȃƌ�q�ƐЂ��č����
�y�����������V�����A�����Q(�ӂ�)�݂�
�₪�Ă₪�Ė��m��ʑ������炫�o�ł�
��(��)�ƌ�(����)�ƉƂ��������͍��Ȃ肫
��q�@���̐�(��)�ꂵ�����܂�
���ȂقȂ邱����ɂ͏t�����̂���
�����~���](����)���A�����͂Ȃ�
�z���悬�肿�����Ăт���
�����̉�b�@�@�@(���a14�N2���@�ނ炳�� 2����)
�͂��߂ɔ����ԕقɎ���g�̂ӂ��Ƃ�̂���V�l�����A�̉Ԃ����Ђ܂���
�u�킽�������͐��E��������ʂ邽�߂ɐ���ė����̂�v
���ɔ����ԕق̒ꂪ����Ɖ��F���t���[�W�A�̉Ԃ����Ђ܂���
�u�������A�킽�������̊](������)�łނ��߂ɂ�v
���g�̐��m����(�v������)������ɂ��R�c��\�����݂܂���
�u�������A�킽�������͏t�������ɗ����̂�v
�ΐF�̃o�i�i�̖�s������(�t�F�j�b�N�X)��S���̖Ȃǂ�
�ʂĂ��̉�b�Ɏ����X���Ă�܂���
�l�͂����C���ɂȂĎ��̊O�֏o�܂���
�s���[�c�A�����Ȃ�ĂЂǂ������炤
��ʂ͖̌쌴�ɖk���������Ă܂�
�O���݂̋𗧂ĂȂ���l��ῂ��܂���
�u���E�����������̂��ق肪���邾�̏t���������̂��ӂ��Ƃ�
�@���͖̌쌴�ɂ܂��������p(����ۂ�)��
�@係��炭�܂ł͐M���Ȃ����Ƃɂ��Ă������v
�]�Ă��牷���̂��삳���Ɉꐡ�����₤�ȋC�����܂���
���l�̐��U 1 2 3 4 5 6�@�@�@(���a14�N2���@���̂� 2����)
�l��͌Âւ�冂̍�
���N�����̈�n�Ɍq��������闫����
���̈⚖���������E����
鰌��ƓC�����ēV���O���̌v���Ȃ����Ƃ���
�R�X�͂��̖~�n�����т����Ƃ�͂�
����������礱�]�A���]�A�×ˍ]�A���]�����s���č~��ė���
���]�����̎x���́A���N�Ȃ��痬��ė����n�͂�����n��
�v��ȗ��̖��W�Ő̂̉Ò�{�A���͊y�R���Ƃ���
������(����)�ĉ���R������
(���̎R�ɓo��ΉĂ̓���
�@���Ղ�������̎R�X��������)
�ꔪ���N�ނ͂����ɐ��ꂽ�Ƃ��ӂ���
���N�͎l�\���ł��炤
�ނ����w�ɂ���@�h��v�����u����
�A���A�l��͓S�����L��肩�瑍���⎢�L���ÎE����
�v���̌�����ꂽ�Ƃ���ł���
������������h�����ꂽ���R�[����
����a���A���̎�͐��m�M�̏�ɐ���ꂽ
�ނ͂��̎ʐ^�����ăT�����̂₤���Ǝv��
����l�N�ނ͓��{�ɗ��w��
�ꍂ�ƘZ���ƂɊw��Ō�A�����̈�ȑ�w�ɓ���
�ނ���U�w��a���w���w���Ȃ�
�����̖�����D�ꂽ���m��w�ňȂċ~�ς��悤�Ƃ̐S����ł���
����ܔN���{������ӏ���v����
�͐��M������������ɔr�����͂��߂��Ƃ�
�ނ͒����ɏ�D���ď�C�ɋA��
�����ł͐l�X�͈������ƕς��l�q���Ȃ�
�������ގ��g�Ɨ��Ă͏h�̋ߕӂ�
�H���ւ낭�낭�킩��ʈʂ���
�ނ͂����œ��{�ɕ��߂�A�����j�n�N�ɂ͕����a�@��
���{�l�̊Ō�w��哪(�A���i)�Ɨ�������
���̗����͔ނ����ĕ��w����������
�A���A�̓�(�Q�[�e)�Ɛᗉ(�V�F���[)�Ƃ��������߂�
�~���[�Y�����B�[�i�X�Ɠ��������Ƃ���
��ɐl�X���Ȃ����߂���@��
�ނ͘Q�֓I�ɂȂ�Q�֎�`��������
�ނ͉̓��̗��̉̂�A�Ⴋ�ۓ�(�����e��)�̔Y�݂��
�ᗉ�̃l�[�v���X�p�Ȃ̃X�^���U���
�{�Č�(�V���g����)��䟖���(�C�������[�[)���ւ���
(�l�͂��̏��ǂ����܂�D�܂Ȃ���)
�����N���E��킪�~�ނ�
�R����肪�N�ė����w����
���X�ƋA�����Č܌��l���ɂ͑唽������(�f��)�����s����
�ނ͂��̊ԓ��{�ɗ��܂Ă���A���{�̐V���G������
�����x�ߐN���I�Ȍ��_���ʂ�������
�����Ė{���̊w�Z��V���m�ɑ��Ă
����O�N�ɂ͓�����{�ɋ����Ȃ��Ȃ�
��C�ɋA�Ĉ�B�v�仿�Ⴝ���Ƒn���m���N��
�a���w���U�w��w���������
���w�G���u�n���G���v��u�n���T��v�����
���w�̗͂Œ����̐N��S�̒ꂩ��h�蓮�������ƍl�ւ�
���������͐h��v������ɏ\�]�N
�c��͐������Ă����c�m�ǂ���
����̓y����a�Ɖ����ق�Ƃ���Ȃ�
�v���R�͌R���Ɖ�������ԂƂ���Ȃ�
�R���͏��Ăٔ̕��̑������ƕς�Ȃ���
(�v����Ɏx�߂͌Â��x�߂̂܂܂���)
�����������V������ł����������Â���
���Y�}�Ǝ������{���a����K������
�h������Ăъ����k���ŋq������
�ނ����̍��A�Q�֔h����ߊv���h�ɂȂ�
�v�����w�����։͏㔣���
�Ӊ�������R���w�Z���k�R��擪�ɗ��Ă�
�k�����J�n����������B�A�e���j����
�����ɗ��Ċv���R�̐N�̐펀�����������
������̐��ɗ��邷��̂�����
�ނ͕������{�̑��������鏑���ƂȂ�
�����B���E�����Ɠ��{�ɓ��ꂽ
�ނ͂��̊v����`�̂��ߋA������Ύ��Y�̉^��������
�܂����̂��ߒ����̃C���e���̎x����
(�����N�̖k����w�̊w����
�ł����q���镶�w�҂Ƃ��ĘD�v�ɎO�\�l�[��
�ނɂ͎O�\��[�𓊂��A�ł����q���鐭���ƂƂ���
�]�����ɂ͌\��[�A���b�\���[�j�ɓ�\���[
�Ӊ�ɂ͋͂��ɘZ�[���������Ȃ����B)
�ނ͂����ė��j�ƂƂȂ�u�����Ñ�Љ���v���o��
�u��܂ł̎x�ߎЉ�͂܂������Љ�ł���
�ꌠ���̓m��ł��������
��������ɂ͓z��m��ɐi����
�`�̎n�c��̂����ŕ����Љ�ɐi�������Ƃ���
(���_�͎a�V�����������I������)
�ނ͂܂��u���̋�����������
���́u�����p�l�v�͐����������ւ��ǂ�
�ނ͐�t�̎s�O�ŐÂ��ɘV���䂭���Ɍ�������
���O���N���������Aḍa���ɓ��x���ς��ΊW����
�ނ̌��͂܂���(����)��A�����̈���
�ނ͗��߂����̂܂܁A�q�������ɂ��ق�
��D���Č̍��ɋA�Ă��܂�
�D���Ŏ������u�w�ɕʂꐗ��e���X����f�v�Ɖr��
�Ӊ�ɉy���Ă��̐�`�҂ƂȂ�
�ނ͂����ďœy��p����������R����č���
���X�c�R�ɒ��͂�Č̍��̎l��ɋ߂Â�
���͑����d�c�ɂł���邱�Ƃ��炤
�ނ̈ꐶ�͈����ƔM���ƁA���Ɨ܂ƈ��Ɗw���
���ׂđ��`�̓�����ł������
���Ƃւ��̈����̎d�����ܗ������ł��炤��
�l�͔ނ�������A�ނ̐�������������
���������A�s�����N�͂�����x��
(�f���X��(�͂��̂���)���Ȃ���Ȃ��₤��)
������Ȏq�����邱�Ƃ͂Ȃ����炤
�����ĉ_�삩�l��̎R���ł��̐g�����ւ�Ƃ�
�p���ɂ��s���ȕ������֖S�������
�n�[���@�[�h��w�̍u�t�ɂȂ��Ȃ��
���l�炵���ߌ��I�ȍŊ��𐋂���
���̎��@�l�͉��߂ČN�̓`�L���������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̍��N�͏��a�\�l�N
�V�@�@�@(���a14�N2���@�l�G 45��)
��\�x(����������)�̏t�̉Ԃ������܂Ђ���
�䑷(�݂܂�)�Ȃ��q����������鏑(�ӂ�)�����䂫���Ɍڂ݂��܂͂�
���͉��Ɨ̈�(����)���ČÂ��Ȃ����ӂ�
�����ĚL(��)�����܂ӂ��ƌ��ɂ䂩��
���e��(���邫)�ɌX���Ă̂��s������Ζ��肽�܂ւ�
�~��ⳋL�@�@�@(���a14�N3���@�{�Y�W�] 3����)
�~�̂��т����͂��т��тЂƂ̐Q�t����邭����
�Ɏq���ɑ��̍~��̂߂Ȃ���
�����Ɨ���鐅�Ɖ_�̉e��
���������̂���̖������邽�߂�
������}�����Ƃ��o���悤��
�d����������������肵�Ȃ���
�l�͙ꂭ
�u���F�������K�N�͂������щԍ炢�����v
����w���̎��@�@�@(���a14�N1���@�����Ƃ�)
�ł��ӑĂ������̂���ɂ���
�{���͂܂����������Ƃ���ɂȂĂ��
�������f���č]�m�����┒�\�����̂��߂ł͂Ȃ��@�@�@�@�@�@�@�@���E�G�̓X��(�����₫�A�i���X)
�搶�͂܂�����ł����@�F�B��
�j�݂�c�ɋ��t�ɂȂ����@������p��
������Ȃ̂��{��ǂ݂Ȃ���ʂ������Ă�
�ނ��t���ɍ炭���̒r���͂�
�}���j�G�̔����Ԃɂ������炩�S���䂩���
�}���ق̓��d���͖���Ƃ������悩����
�������̖{�͎�o���̂�����������
����ł���w�͂Ƃ��ǂ��v�Џo��
�����Ă���ƈ��������Đe�߂̏������
����ȃV�j�b�N�Ȑ��i�����O����̎���(���܂���)��
�s��ɌՂ����@�@�@(���a14�N2���@�l�G 44��)
�Ε�(��)�⒃�̉Ԃ��������爤���o�����炤
�F�ʂ���͉��������
�����ڂ��Ԃ邽�тɑz�ӂ̂�
�r���̗t�̖��R��
�_���܂Ƃ����A�R�̒��̈ꌬ��
�s����A�����o�����Ƃ��Ȃ�������
�Ղ̔@���\(����)�����t�Ől��������
���̂��ꂪ�������Ɨ������Ă����
�k�Ɍ����@�@�@(���a14�N2���@�R�M�g 81��)
���̂�����y�n�͋N���������Ⴋ�͂܂�Ȃ�
���̖͓~�̐F��X�ւĂ��������ɂ��т�
��͒w偎�ɗ����僂Ƃ��ĐÖ��̂₤
�����k�Ɍ��ē�������
���F���捇�����Ԃ������̊X������������
����͖Z�����ŁA���̂������ɂ̂�̂낵�Ă��
���˂̉��̍��������镗�̂Ȃ����A�����Ă��̗₢��C
�����k�Ɍ��ē�������
���݂̕a�ފق͂��Â��H�@���̊��X�Ƃ����ڗ�
�ꂫ�͖ڗ��傫������A�̌��E�A�݂Ȕ����h���
�킪�s��ɂ������~���`�̎o���ΎR
�����k�Ɍ��ē����䂭
�������@�@�@(���a14�N1���@�l�G 43��)
���̕Ћ����ꐡ�����������ɂȂĂ��ӂ�ɂ�
���ɖ邪���Ă�@�����܂ŗz��������
�q�������̑����ł�z�R�͂��������Ȃ�
�}�ɔw�������Ȃ��₤�Ɏv�ւ�
�킽���͑҂������т�č��Ă
�[���̟B�̂Ȃ�����G���P�b�P�b�P�b�P�b�ƚe������
����Ƃ��������ł���ɉ��ւČĂт��͂�
�킽���͑����u���܂łƊ�ȂȌ��S������
����ł��҂������т�č��Ă
���t������(����)�̏��ɗ[����������
���̂������͂킽���̔��̂₤�ɐ_�o���Ɍ�����
�킽���͑҂������т�č��Ă
�L���̓� 1 2�@�@�@(���a14�N1���@�����₤ )
�@�L���̎s���ɂ͓�̓�������܂��B��͉ԓ��Ƃ��ĘZ�Վ��Ƃ��ӂ����̒��ɂ���܂��B ����͍���������l�S�N�O�̗��̍����J�_�Ƃ��Ӑl�����Ă����̂ŁA���̌`�͔��p�ŋ�d�ɂȂĂ�܂��B�����͓�S���\�ڂŏ�ɓ��̒�������A���̐�ɂ͋��̕�삪���Ă�܂��B ���̉��ɑ�H�̐_�l�ł���D�ʂ̑�������܂����A���̑��͕Ў�������Ėڂ��������Ȃ��瓃�̈�����߂Ă�āA���̎����̓���Ƃ��낾�����������Ɍ������̂ł��B ���\����ւ����������Ƃ������ł��B �@������̓��͌����Ƃ��ĉ������ɂ���܂��B���̎��Ɠ��Ƃ͓���ɃA���r���l�����Ă��̂œ��̍����͕S�Z�\�ڂ���܂��B ���͗�����̊K�i����Ă䂭�₤�ɂȂĂ�ĉ��d�̓��Ƃ��ӂ킯�ɂ͎Q��܂���B����ɂ͂��Ƌ��̌{�����ĕ��̂܂ɂ܂ɉ�Ă�܂������A ��v�̍��ɓ�����������啗�̓��ɓo�čs�āA�J�P��𗃂ɂ��A�{�̕Б����ӂƂ���ɓ���Ĕ�щ��肽���Ƃ�����A���̍��ɂ͑啗�Ő������Ƃ��ꂽ���̂ł�����A ���ꂩ�瓺�̌{�Ɗ��ւ� ��Ă��܂Ђ܂����B���̍��ɂ͌ܘZ���̎��߂ɂȂ�Ɠ�̕�����A���r���̖f�ՑD�̗���̂�҂��]��ŁA �אl�������ߌ�ɂȂ�ƒ���ɓo�čs�ăA���[���Ăя������F��܂����B���̉��ɂ͞Վ����ꊔ���Ă����ɐ���ɂ͔����߂�����ł���܂����B �@���̓�̓���O���ƌ���ƂɌ����ĂāA�L���̎s����̑傫�ȑD�Ƒz�������x�ߐl�̍l�֕�����ς������낭�A���Ɋ��S����l�����ȂƎv�Ă����ɋL���܂����B
慎��̔@���@�@�@(���a14�N1���@���{�̐l 1����)
�Â��_�a�̉����ɂ͌͏��t���U�肵���Ă
�C�̕��ւ�����Βi�̗�����
�����͂Ȃ₩�ɍ炫����Ă
�Βi��o�ė��鏭�������Ƃ��ꂿ����
�t�͂ЂƂ����Ȃ������ĉ̂���炷��
���j�T�@�@�@(���a14�N1���@���{�̐l 1����)
���̓��͊�����̓��ł���
���̂��ւЂǂ����������Ă
�R�X�ɂ͔�(�͂�)��̐Ⴊ�����Ă
�K�̎}�ɐ��̉H�ɕ��������Ă
�V��(�e���g)���͂��͂��������ӂĐ����Ă
������m���㗝��x�@������
�����͋}���ŋ�ɔ��ōs��
���̓��͂Ђǂ����̓��ł���
�Ⴂ�y�n�@�@�@(���a14�N1���@���Y 1����)
�����͎��ɒႢ�y�n����
�l����Ⴂ�R�X���Ƃ�܂�
���̏�ɂ͉_������㫂߂Ă
�G�⒎���b�̉Ԃ̐��E�ł���
���ꂩ�瓮���ʐ�������
�����͎��ɂ���ȓy�n����
���X���炻���������ꂱ��ł
�����ē����ʐ�����������
�V�n�C��n���@�@�@(���a14�N1���@���Y�Ę_ 1����)
����͖��Ă�閲�Ɍ���
���疜�̔n�̌Q�����Â��Âƌ���̑�C��n��̂�
�����ޓ��͒����G�炳�����g(�����Ȃ�)�����Ă���
�L���X�g�̂₤�ɕ����ĊC��n��
�n(����)����铍�Ԕn(����)����鎭�т����I�т�A�KḖ�(�����)�����
����(��������)�̖q�ꂩ��o�ė����̂����㍂��˂ɂ�m�n�����
�q���̍��Ɍ����Z�g�l�̐_�n�܂ł����
(�ӂ����Ȃ��Ƃɂ͋��n�̔n���ꓪ����Ȃ�)
�ޓ������݂ɒ����Đg�ɂЂ������@�E(���Ă���)�����ĂɎU���H�̔�����
���Ȃ���o�߂Ă��Y��ʔ������ɕM������̂�
�F���̐� 1 2 3�@ �@�@(���a14�N1���@�R�M�g 80��)
�Ìc�̌�F�̏��߂̉ĂȂ肫
���߂��l�Đ����菢���҂��ꂵ��
�܂������@���̑��傢�ɋN���
���R�i�ۂ����Δs��ƕ�����
���ɑ��Ĕ������ߋ��Ђ�
���L���L沅��蟐��i�����j�̑����������Ƃɉ
�h�����ĎO��ܕS�̕����l�Ă����
�ۗサ�ėk���Ɏ���Ζ����ׂē��ꋎ��
�X�ɂ��s�ɂ��l�e���ɂ��炴�肫
�L���������Čۂ�ł��p(�ӂ�)����
����U�Ђ��ɉʂ��ďo�ŗ����
�n�̗��ɂ�đ傢�ɔj��@�ώr�ڑO�ɑ�(����)���肫
���̂Ƃ����������ЂɌڂ݂�
�u���犯�R�Ɛ�ӂ��ƎƁX�Ȃ��
�@�����ē��ꂴ��͂��炴�肫
�@�����т̏��͂����N�Ȃ邼�v
�����ĉ䂪�����`�W���ĉ]�ւ�
�u���̘V�ꖢ����(��)�Ȃ��肵��
�@���炪���͂����ɏI���v��
�k�R�ɉc���Č�����肽���
�������ɍU�߂Ƃ����
����݂�l��^�ւ���
���ꂪ�s�������܂��e��酂�ɔ���
�w�ǑS�R�����̏肫
���ԓ����~�Ђɕ�������
�l�ԗ݁X�Ƃ��ċ�������͂���
�i���R���s���̊[(�ނ���)�Ȃ�
�����_�Ɏ��肵���@���ꂵ����
�O�X�܁X�@���Ƌi�����ɏo���
���̕��p�Г��ׂ��Ǝv�т����
�Ԃނ�ɑP�����ȂĂ��@�킪�������ւ�
�݂Ȃ݂ȗE�Đ�͂�ƌ��
����W���(�����Ԃ�)��炵�ĕ��Đi�݂�
������������@��������Ƃ���
�݂Ђɑ��H��ł܂��ɒׂ���Ƃ����Ƃ�
�����̂ЂƂ肪�u�����Ȃ���
���ɖC����v�Ƃ��ЖC�ɒe��(����)���߂�
���̋�(����)�̍g���肵�������Y�ꂸ
�C�͔�������ǖC�g�j���
�l�ӂɏɉ����Â܂�����
�䕺�˂��Č����@����ǂПr(��)����
�����@��Ɏ���đ傢�Ɍ䊴(���傩��)�ɗ^(���Â�)��
��Ɏ��ӂɎ݂��ȂĂ����܂Ђ���
������i���R�ɐ[�������т�
�F���͌Ζk�Ȃ̒n���Ŋ����̖k�ɂ��荡�����ςʼn�C�h�̓������Y�����@�����̂Ƃ���ł���B ���̎������̖����ēG���������m��ʂ��̂Ȃ��͊�������̖����̈�l�����ōN���̖��b�Ďv�˂̑]���ɂ�����B
���҂Ɍh�点�� 1 2�@�@�@(���a13�N10���@�R�M�g 77��)
���҂Ɍh�点��
�u�X�Ɖ���(�Ƃق����Â�)�̔@������
�킪�F�@�������я����͋P�̞l�ԗ����
���炫�̋e�@�x�炫�̃_���A�݂Ȕ������ďD�Ђ���
�v�ւ��N(����)�̉ā@�̗��𗧂�
�R���͏d��R�̍�
��(������)�̓G��ł�����@��╪���T��
�͂�腎��R�̍�炵�߂㠈����〈����
���(�ЂƂЂ�)�̕ւ肾�ɗ���
�܌���t�̒��܂���
�R���̎R�����o�ʼn͓�Ȕ������̐퓬��
�땺�̒��ɂ͂��肫
�`�F�R�@�e�@⹂���f���ɓˌ���
�c�̌l�ɝ˂�@��\���Ȃ肫
���炫�̋e�@�x�炫�̃_�����݂Ȕ������ďD�Ђ���
�킪�F�@�������я����͋P�̞l�Ԃ͋����
�u�X�Ɖ����̔@�������\�\
���҂Ɍh�点��
��n�@�@�@(���a13�N12���@�l�G 42��)
���͟O(���₫)�̕��Ȃ�
���͏t�Ȃ�Δ~�炩��m�ƂȂ�
�������ɂ͑�͂̂����
���Ă����ɕz�N������(���Ƃ�)�͂��Â�
���͎₩�Ȃ��n�Ȃ�
�傢�Ȃ��͕x�ҏ��Ȃ�͕n��
�w�����ĒH��䂯�Έ����
���Ə��������킪�F
�Ӎ���������������ނ���
���܂͖���Ă͂邩�Ȃ�
�Ƃ��ĕ�ɓy�̏��
�܂̂��Ƃ�������o����
���W�u�嗤���]�v�o�� �@�R�M�g100��(���a15�N10��)76-79p
�@���̎��W�͎��̑�W�ł��āA���a�\�O�N�\���ɏo�����w���W���N�ȁx�ɂ����̂ł���B�薼�͂��̎��W�����ܑ嗤�ɂ���@�c�P�����ɕ������Ɠ������R�ɂ��B
�������̐��N�ԁA���̍쎍�̎h���ƂȂ��̂͑嗤�ł����B���͂�������]���Ȃ���A����������ӎ��ɒu���Ȃ��玍������A
�����ċ��炭���̐��N�͎��̐��U�ň�Ԏ��̑����o�����Q�֓I�Ȏ���ł����Ƃ��ӂ��ƂɂȂ邾�炤�B
�@����͗F�l�����K�F�������Ĕ������\���ƌ��Ԃ��̐}�ĂƂ�`���Ă��ꂽ�B�Z���͔쉺�P�v�����Ă���āA���炭�B��̌�A���Ȃ����ƂƎv�ӁB
�p���͂��̕s���R�Ȓ�����T���o���ꂽ�͑����ł���B
�@���̏����͑O�̎��W�̂Ƃ��Ɠ�������̌Â����̂قnj�Ɍf�ڂ����B�ꓙ�Â��̂����a�\�O�N�\���̃R�M�g�Ɍf�ڂ����u���҂Ɍh�点��v�Ƃ��ӎ��A
�ꓙ�V���������R�M�g�̐挎���́u�킪�a�����v�ł���B
�@�͂��߂̎��́u�����v�A�����邱�ƂƖ��������͎��l�̊����Ƃ��ėG����邱�ƂƎv�ӁB
���́@�u�c���O�[�X�v�͖k������V�x���������ɂ����ďZ��ł��Tungus�����ނɂ��Ă��B�c���O�[�X�͏��Ă݊͟C�������������������ł��邪�A���͑S�����ւĂ��B
�x�ߐl�ƃ��V���l�ƂɈ�������ĉ���͖S�Ԗ����ł���B���͂��܂��̎Љ�����ׂ��ɏq������S�EM�V���R�S���t�́w�k���c���O�[�X�̎Љ�\���x�Ȃ鏑��F�l�Ƌ��ł���B
����͂��͂��̕��Y���Ƃ��ӂׂ����B
�@�����O�\����͎������́u�a�����v�ł���B���̎��̒�������͂��͂����Ă���i�͐��Y����Y���v�l���炨�ق߂ɗ^���B�����̓ǎ҂ɂ͂��������ꂪ�����f���邱�Ƃ��B
���́uEin Marchen�v����͎q���̂��߂̓��b�ł͂Ȃ��B
�u�������s�Łv�@�̏������s�͌����̕��ˎs�ł���c�s�ł��Ȃ��B����Ђ͓s��S�̕����̎]�̂Ƃ��Ƃ��邾�炤���Ǝv�ӁB
�u�@�B�ɂ��Ă̊��z�v�u�s�g�ȗ[���v�B���̓�ɂ��Ă͕ʂɂ��ӂ��Ƃ��Ȃ��B
�u���N�v�ɏo�ė���͖�͎��͎��͍s�����Ƃ��Ȃ��A�����t�v�搶�́u����I�s�v��ǂ�ōs�������Ȃ�A�Ί݂̑��܂ōs�ē���s���Ȃ��ƒm����Ԃ����̂����a���N�A
���̓�\�O�̎��ł���B���̍��̎��̒q�\��ӎu�͂͏\�Z�Β��x���������m��ʂƁA���܂ɂ��Ċ����邱�Ƃ�����B�A���S���͓�������̈�ł��邪�A
���{���n�ł��^�~�ɂ͂��̎启�J�m�[�v�X�����X������R�B
�@�u���Ҏҁv�A���j���҂͎������߂Â��ƕs�v�c�ƈ�ʂɏ����̊�]����肽����B���Y�x�Y�A�������Y�A���������݂Ȃ��������B
���c���Y���́u���j�v(�O�������Ɂj�ɂ����̂₤�ȋL�ڂ�����B���������̎��ł͈�ʂɊ��Ҏ҂�\���҂Ƌ���҂Ƃ̑������肽�����̂ł���B
�u�����v�͂�߂ł���B
�u�C�l�z�e���v�͒Z���l���̈�����̂ӁB
�u�c�I���Z�S�N�̒��v���̌��ݍc�R�̐�̂��Ă��ȏ�̐����w���Y���I�x�ɂ��̎��\�������ɂ͋�ƊԈ���B�p�������\��̂Ȃ��Ԉ�Ђ����A
�������Ŋo����ʂقǑ�R�x�߂̏ȏ���c�R����̂��Ă�邱�Ƃɉ��߂Ă��ꂵ�����������B
�u�D��v�͒���̖�ɉ�����E�q�Ƃ��̒�q�B���̎��E�q�̑z�N�������́u��(��)�ɔ�(����)���A�Ղɔق��A�ނ̞D��ɗ�(������)�Ӂv�Ƃ��ӎ��тł����B
�u�嗤���]�v�Ƃ��ӎ��͘@�c�P�����̕��Y�������a�\�l�N�������ɂ̂���ꂽ�`���̎��̎��C�̂₤�ȋC���ł���B
�u��N�v�͎��}���܂ށB
�u�C�b�v�A�u�����ɂāv�݂Ȏs���ƒ�̎��ł���B
�u�s�ҁv���̐�R�͍b�M������ނ������R�ׂ̗̎R�ŁA��ΘI�o�����]�����Ƃ���Y��_���Ȋ�������ւĂ��B
�@�u�đ��v�A���͖{���V�q�ɑ��Ă̂ݏ��֏���ɂ͐�A�����͕S�Ə��ւ�ׂ��R�ł���B�u���͑�N�̏�ɂ�������v�Ƃ��ӈ��͂��̈Ӗ��ł���B
�É̂ɂ��N�ɗ����Â�ĂƂ��ӈӖ��̋傪�����B
�@�u�x�m�Ɋ���́v���́u�]���v�Ƃ��ӂ͉̂f��̖��B�������ӂ��͂��̂������Ɏg�ӂ͎̂��͂����Ȃ��̂ŁA���Ƃ����悤�Ǝv�ЂȂ�������̂܂܂ɂȂĂ��܂��B
�u�z�K�v�֍s�����̖�͒��x���Ђ̉čՂ̓��ŁA�[���D�̒��������̂����������B��ϐ_��I�ȍs���ł����v
�u�隬�ɂāv�A�u�ԖɊāv�A�u��v�A�u��ǂ肬�v�A�u�~�������v�A�u����v�A�u�����ЂƁv�A�u����v�A�u
���{�̏t�v�u�����̉�b�v�݂ȕʂɋL�����Ƃ��Ȃ��B
�s������̂��u���l�̐��U�v���ђ��B��̒��тł���B���͌���̎x�ߕ��w�҂ł͂ӂ����ɖ���̂��̂�����ǂ�ł��B�u�n���\�N�v�Ȃǂ���̏o��܂ւɓǂ��A
�u���ᎍ�W�v�͈��ǂ����B�u����W�v�Ƃ��ӂ̂����āA���̒��ŃV���g�����̎������̏��Ĉ��u�������̂ƑS���������̂̂ݖĂ��͉̂����������B
����̋A���̂Ƃ�������͒|���D���̌䋳���ɂ��Γ�т�
�u���l�A�ԐM��`�ցA�����荁�J���u���B�ɋ}�A�Ύނ�J���A����A�������B�g������đבЂ������A����ɂ���ꟓV��]�ށB���ӁA���L���y�A�Q���A
��������މ��B�v�Ƃ��ӌ܌��̂�
�u�����ɕM�𓊂���㗂��ӂׂ��̎��A�w�ɕʂꐗ��e���X����f�B�������ď\�N�A�܌���]���A�M�ɓo�ĎO�h�A�Պ�������B�ӂ�Ŏc���ď��Ăɖ��߂�A
�L���Đ�����f���č������B�l���X�l�Ă����D���A���S������^�߁v
�Ƃ��ӎ��������Ƃł����B�~�Q���ė���������Ȃ̂��R������Ԉ薗��̕������ɂ͋���������B������]�T�^�X���鐹�킢�Ȃ�����]�ւ邱�Ƃł��邪�B
�u�V�v�A�u�~��ⳋL�v�A�u����w���̎��v�A�u�s��ɌՂ���v�A�u�k�Ɍ��āv�A�u�����Łv�A�u�L���̓��v
�����C�ɂȂ邱�Ƃ����A�L���Ƃ��ӂ͎̂��͏Ȗ��Ŏs�͍L�B�Ƃ����[�Ƃ����ӕ����������̂�����A����Ȏ��Ɉꐡ����B
�L���̎s����Ɍ����Ă��̂́w�L���d��x�z�̒��ҋ����(���R)�ł���B
�@�u慎��̔@���v�A�u���j�T�v�A�u�Ⴂ�y�n�v�A�u�V�n�C��n��v�A�u�F���̐�v�͐��̗�e����[��+�A]�́w�����G�^�x����ނ��Ƃ�B
�u���҂Ɍh�点��v�̏����͋P�͑��̏o�g�A�H�������̏������Ƃ��ď��a�\�O�N�܌��\����펀�B�͓�Ȃɂ͖����ɂȂĂ��玩�R�A�����A�����ȂǂƂ��Ӗ��̌����o�����B
���̔������Œ����R���n�̋��Y�R�Ƃ̐퓬�ŗ������ђʏe�n�œ|�ꂽ�B�����Ƃ��Ӗ����ςɏ��ł͂Ȃ��@���B���͂��̈ԗ�ՂɎQ��o���Ȃ������A
�Վ������ŕ\�͂������O��̓���Ɉӂ�p�Ђ��B�ƂɐV�Ȃ��肱������炫�̋e���Ȃĕ\�͂��A���ꂠ��A�x�炫�̃_�������Ȃĕ\�͂��B�A���Տ��{���̋e�ƃ_�������������Ƃ͋^�ЂȂ��B
���a�\�ܔN�A���܋��M�Z�������͂��B
�@�u��n�v�́u�z�N�������v�Ƃ��Ӌ�Łu������ɎN�����肳�炳��Ɂv���v�ЁA������n�ƍ��_���ꂽ���B��̎�͓��m�j�̓����⍲����Y�B
���a�\�N�����ɋg���m�ɐ��s���ĔM�͕��ʂ���Ƃ��Ėk�x���F���N�����@�A�A���㔭�a���Ď����B�����ɞH���u�Ӎ������앪�v�B
�@���łɂ����̎��̌f�ڂ��ꂽ�G���V����S�o���ɂ��邷�B�����������M�����ӏ�������A���̓��ۂȂǍl�ւĂ���������Ƃ��v�ӁB
�����@���Y���I15�N9��
�c���O�[�X�@�R�M�g15�N6��
�킪�a�����@�R�M�g15�N9��
Ein Märchen�@�ނ炳��15�N8��
�������s�Ł@���Y����15�N8��
�@�B�ɂ��Ă̊��z�@�H�Ƒ�w���O�V��15�N5��27��
�s�g�ȗ[���@���V��15�N5��20��
���N �ᑐ15�N5��
���Ҏ� ����15�N4��
�����@�V����15�N4��
�C�l�z�e���@���Y15�N2��
�c�I���Z�S�N�̒��@���Y���I15�N1��
�D��@�������_14�N12��
�嗤���]�@�������_14�N12��
��N�@�F(��A)��30��
�C�b�@�l�G14�N11��
�����ɂā@���Y����14�N11��
�s�ҁ@�R�M�g14�N10��
�đ��@�R�M�g14�N8��
�x�m�Ɋ���́@�V����14�N10��
�z�K�̒��@�a�J���w14�N10��
�隬�ɂā@�R�M�g14�N7��
�ԖɊā@�w�Y�W�]14�N7��
�� �l�G14�N8��
��ǂ肬�@�w�Y�W�]14�N5��
�~�������@�V��14�N5��
����@�V��14�N5��
�����ЂƁ@���Y���I14�N9��
����@�Z�̌���14�N5��
���{�̏t�@���Y����14�N3��
�����̉�b�@�ނ炳���\�l�E�j
���l�̐��U�@�@���̂�14�N2��
�V�@�l�G14�N3��
�~��ⳋL�@�w�Y�W�]14�N3��
����w���̎� �w��������2��3��
�s��ɌՂ���@�l�G14�N2��
�k�Ɍ��ā@�R�M�g14�N2��
�����Ł@�l�G14�N1��
�L���̓��@�����₤14�N1��
慎��̔@���@���{�̐l14�N1��
���j�T�@���{�̐l14�N1��
�Ⴂ�y�n�@���Y14�N1��
�V�n�C��n��@���Y�Ę_14�N1��
�F���̐�@�R�M�g14�N1��
���҂Ɍh�点��@�R�M�g13�N10��
��n�@�l�G13�N12��
�@�ȂٍŌ�ɂȂĂ��܂ċ��k�̎���Ƃ͎v�ӂ���ǁA���̎��W���Y�����p���ɉ��ւĉ��������{���w�̉�̓��l�����̌�D�ӂɌ������\�グ��B
�A���������Y���ɂ͎�X��z����ς͂����B���̑p������͐�Ɉɓ��×Y�́w���W�ĉԁx���o�Ă�āA����ƑɂȂꂽ���Ƃ��Ƃ�킯���ꂵ���v�ӁB
�@���̎��W���̎��͂��y�đO�q�̔@���́X��N���炸�̒��ɏo������̂����A���{�̑������Ă��h���ɕx���̎���ȊO�ɏ��搶���m�F�̌��オ�Ȃ���A
����ȑ����̎��͐���Ȃ����ɑ���Ȃ��B����قǁw���W���N�ȁx�ɑ��Ď�����X�̌�D�ӂ͂��肪�������̂ł����B�@�c�P�����̐�n����̂͂��܂��ɂ́A
���̎��W������邱�Ƃɂ�Ċ��ӂ̈�[��\�͂��������A���̕��X�ɂ͂��̋@��Ɍ������\�グ�����v�ӁB
�@���̎��W���O�̎��W���牽����������i��ł�邱�Ƃ�F�߂Ă���ւ�Ύ��ɂ͑�ϊ��������ƂȂ̂����A�������������i�Z�̒n�ł͂Ȃ��B
���̎��ɂ͂��ƈ���������������v�ӁB���̕����̎w���Ȃǂ�����������ƐɊ�ӂ̂ł���B
�y�Q�l�z
�@�@�c�P���@�u�ʐM�����M�v�@ ���Y�����@���a14�N7����
(�O��)���͊������]��k��Ȃ���A�ӂƘ`���̂��Ƃ�z�������Ƃ�����B���s��M���т͓����������@�o�g�ŁA�����L�҂Ƃ��ď�C�ɂ��݂��l�Ȃ̂Ř`���̂��Ƃɂ��͂����A ���낢���Ă��ꂽ�B���͂ӂ����Ȕނ�̍s�����v���B����͖ܘ_�����̉����Ɛ����I�Ӗ��͔@���ł������A���͂Ƃ肠�ւ����̂₤�ɏ����Ƃ߂Ă������B �����҂̋C���͑��ʂ�����̂�����₤�ł���B
�ނ�͝X�˂���A�`�̖��Ȃ肫
�ނ�͊U�薳���ȒÊC�̔ޕ���
�傢�Ȃ��Ɨ��Ƃ�]���āA
��ւ������肯���
�u�������F�v�̊��������āA
��(���Ƃ�)�ʂ��ʍ��X�։�����(��)�ōs���ʁB
�ނ�́g�S���́h�̗|�ɂ����Â�͂��肵����
������ւĂ߂Ō}�ӂ�҂��܂Ђ������݁A
����債�݂čR�ӎ҂�Ĕ������肫�B
�ނ�A�s�v�c�Ȃ�k(�₩��)�́A������
�嗤���A���ɓ�ɗ��߂߂���A
���͌Ð�(�ނ���)���ɍ�(��)�܂��āA�ԓ��̐F����(����)�����V�����P�ЁA
���͒��]��k��āA�V��V�Ă���Ă�T�肵��
�喾�����R(���ǂ낫)�����āA�h�����ւ�
���{���R�ɐ��ЂĔV�ł���Ƃ��A
�s痂Ȃ鑸�̂���A�v���R�Ɛς݂��肵���A
���ɏ��R�V����ߓ������Ƃ����\�\
�B���ƂȂ��ނ玩(����)��Ɛ��Ɏ��ɍs�����c�c
�ЂƂ�R�c�����Ƃ��ւ鋭��(�͂���)�A
�V�������ɁA���҂̐��Ђ��ق����܂܂ɂ��A
�ł��Ă͂��Ȃ��Ŋ����Ƃ�����ƁA
�j�ɂ��̉�����[���܂�ʁB
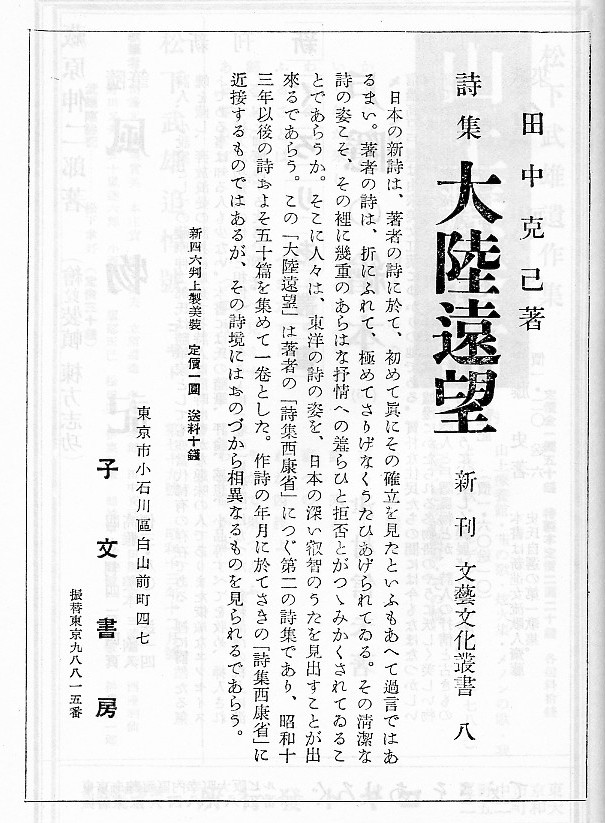
�R�M�g�f�ڂ̍L��