詩集 昧爽の花
高木斐瑳雄 第二詩集
大正13年2月1日 青騎士編集所(名古屋)刊
布装上製函入 19.5cm×15.0cm 8,135p \1.50
装丁:水野義正 限定200部刊行
扉
(2002.11.25up / 2011.10.31 update)
Back
たかぎ ひさお【高木斐瑳雄】『昧爽の花』1924 【全文イメージ】
−第千九百二十三年版
序
「久遠の柳の詩人(うたびと)に」添へて再び「昧爽の花」の著者に。
斐瑳雄君、ずつと前、僕等はよく思い出すことが出来るのだが、
君が「久遠の柳」を書き、僕が 「久遠の柳の詩人に」を書き送つた
やうな、少年らしい美しい時代があったね。
美しいと言へば、今ではお互ひに、あの頃の詩作を隠すやうにし
て、新しい詩作にふけつてゐるのだし、事実、今日、新しい太陽(ひ)
の下に立つて、長い期待に花咲かうとする「昧爽の花」の、また一
段の美しさを飾るためには、僕にしても新しい何かを書くの
がほんとうではあるが、ふしぎに、君もあの時代の心持が忘れられ
ないと言ふし、僕も捨てがたく思ふので、君が言ふままに、机底深
く蔵(かく)された 「久遠の柳の詩人に」の一篇を贈ることにする。
お互ひに、かうして古い昔の心持を出しあつて、ながい間の約束
を新しいものにして進んでゆけるやうになつた悦びだけで、僕は
この詩の詩としてのはづかしさと取りかへてもいいと思ふ。それに
君が僕の思つたやうに汚れなかった柳であつたのみか、今では素適
に自由で快活な詩人になつてくれたことも、このさきまでお互ひに
この一篇の詩を書いたときの心持を証(あか)してくれて愉快だ。
何はともあれ、君が闊歩や爽快で丹精して盛りあげた、君の最初の田園の饗宴
である「昧爽の花」のInvitationの挨拶として、僕はあまり内あけ
話をしすぎはしなかつたらうか、もしさうであつたら許してくれたまへ。
かなかな鳴く日、白壁町の寓居にて
春山行夫
久遠の柳の詩人に
ああ 赤錆びた常几の旋転する人生に
魂の窶(みすぼ)らしい炬火を振りかざしてよ 君!
苦難の石切場を徘徊(さまよ)ふものよ、
黄昏の鉄道線路に歔欷(すすりな)く孤子よ、
常住不断の霊のするどい笛を忘却せず
緑の胸盤にしのばせてよ 蘆の葉もて
絶え間ない寂寞の惝[亻兄](しょうこう)のしのびなきを・・・・・・
詩人(うたびと)よ、永遠に嗟嘆することなく
生の汚穢と濁水に泥(よご)れ傷ついた柳ではなく
自由の喜悦と無根の苦悩の月桂樹(ローレル)を戴きてよ。
君が天賦の霊感と啓示の泉を噴き迸らしめてよ。
霊の雪白い哀愁に翺翔(こうしょう)する児たれよ。
ああ いかに醜陋 燥閙の擾乱に浸るとも
恒に永遠の童心をば傷つけることなく
霊の黄金の菰(ラッパ)を劉喨と響かせて
生の輝耀の征矢をほがらかな天上へと射てよ!
詩のアポロンのニ輪馬車の先導となれよ。
久遠の柳よ
いまは畏怖するなかれ 流れる水のなかの黒い悲嘆に、
うちつけて蘆の葉を固い邪念に泣かしめる黒い暴風に、
また断線(き)らすなよ 君、 いかにこの匆惶とした生の洪水に流さるとも、
かの蓋生の愛のHarpの琴線を
至純な涙の声に囲繞せられた詩の曲律を。
おお 君よ!
諦視、黙念、愉悦、嗟嘆の渦流に
人間の時劫の鉄扉を
詩の繊細な鍵もて捜めてよ、
永劫平和の窮理の聖窟は白い百合と花咲いてよ!
恒にみすぼらしい霊の炬火を振り翳してよ。
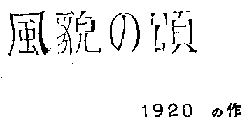

挿画 「天使と冥罰」
《 風貌の頌 》
1.
久遠の柳
万物に先だつて希望の春を告げた柳よ
若々しい幼な子の薫リよ!
今もわたしの耳に眼にあらただ、
かって 真夏 わたしの疲れた魂と肉体の上に
青色の ソーダ水をふりそそぎ
砂漠の廃墟の街道に多くの疲れた旅人たちのために
清涼をめぐみし柳よ。
やわらかい西風は 秋海棠に 葡萄に 無花果に訪づれ
にごりきつた大気を漉しはじめたとき
ジグザグの鋼鉄の刃に身を切られ
甘い夢の楽園から不具者の灰色の魂のくにへ・・・・・・
嘆きと涙のはての・・・・・・無言の闇へ
一瞬のまに運ばれた哀れな柳よ!
私は泣かずにゐられない
私は胸をかきむしり 頭を低く腕にうちのめし
かなしい、かなしい運命を共に泣かずにいられない。
おお されどされど生ける魂を持てる久遠の劇よ!
おお されどされど生ける魂を持てる久遠の柳よ!
試練も後の日の思ひ出 まことに
くるしい 辛(にが)い生命の流の途上を
涙をを湛へて 総てを愛して行かう、
永遠の魂の彼岸に光栄の目録を多く多く書きしるそう
おお 信愛なる永遠に緑の柳よ!
2.
わが旅
冷えながら静もりゆく夜更け
青い電燈の光の中に 溶け
静寂に見守られた わたしの室に、
おお この私の 孤独のこころに
さすらひの旅に上る 汽笛の音が 玻璃戸を軋まし
かなしさ さみしさをみたすとき
わたしは ただひとり ゆめみる。
いかにその門出が喜びでみたされてゐやうと
希望と幸福とが その人をどんなに燃やしてゐやうと
いつまでも音たててゐる足許の車輪の響の中に
ふと、黒い原野のあなたに
明滅する人家の灯を 窓越しにみるとき
そこはかとなく
一沫の郷愁が幻となつてすぎるのであらう。
行商人も妻や子の寝顔を思ひ
軍人も楽しかつた晩餐の欒を 思ひ浮べ
さみしい心を 眠りに紛らはそうとする、
都の空を 憧憬れてゆく女の 窓に倚せた白い腕が
はかない黒と白の糸をもつて夢を結び
危篤の報に接した母親の老いの手は 電報をいぢりながら・・・・・・
彼女は涙に濡れた頬を拭はふともせず 居睡つてゐる
すべては 柔らかい電燈の灯の中に浸り・・・・・・
おちつかない やるせなさを
まどろみに包まふとする
哀れな人々の一行よ!
この一行の行方には
死に瀕しながら母親を待つ 若者もあるだらう
数年振りの邂逅に 想像の翼の ありつたけをひろげ
胸に涙を湛へて待つてゐる楽しい家族もあるだらう、
あてどなく 恋人を待つ男もゐるであらう・・・・・・
待たれてゐるものも 待たれてゐない者も
すべては 今しがた離れた所に心を残し
刻々の幻滅を 悲しむでゐることだらう。
わたしのやるせない心も 夜になると
さすらひの旅につく・・・・・・
かなしい汽笛の音と共に、
あこがれのくにへ ひとりさみしく上るのだ、
わがために 手を展げて待つひとのあれど
わがために 心より心より祈るひとのあれど
わが旅はかなしく
わが旅は さみし。
3.
陶酔
二人はその時 ほんとうに静かでした
心は鼓動の行方をみつめて一途に
手は手に 眼は燃えさかつた炭火に
なみきつたリキュールの
アルコオルの揺曳に惑はかされてゐるかのやうに
戸外、霙をふりまいてゆく風を眺めてゐた。
(ほんの一瞬ではあつたが お互の心に
頬白の飢えた声を読んだのではあつたが)
考えも感謝も何もない春の妖精のすむ室(むろ)で
暖いぬくもりの泉で湯浴みしてゐた
おおその時 二人はほんとうに静かでした。
4.
軽い嫉妬
さすがに私の口笛はふるへてゐた
雨の中をあるきながら
いつになくさみしく出てきた私の亡霊に
やるせない口笛をふいてみるのであつた。
碧色の親和の空はいまも私の胸に展がり
優しい彼女の瞳をみることができるのだが
だが まことに暗鬱な私自身の亡霊よ。
さんざんに雨にうたれるがよからう。
5.
青いらんぷ
おやみなく降つてゐる雨の中で
もえてゐる青い洋燈(らんぷ)よ!
かつて彼女の瞳深くともつてゐるたもの
ああ いまも私の追憶の野辺に花を咲かせてゐるものよ。
ちらりほらり 幻滅の花葩が散つてゆかうと・・・・・・
降りしきる雨 そして
そこに いつももえてゐる青い洋燈
窓帷(カアテン)はとてもひくことは出来ない。
6.
孤独
雨は降る硝子戸に
うすら灯は輝る その滴に
金七宝のやうに窓々は美しい。
おお 孤独よ!
なんといふ すばらしい装飾の中に
私を抱くか!
煮えきつた寂しさの中に慄へてゐる山吹色の愁(うれひ)よ
裸婦!裸婦!ただひとり踊り狂へる裸婦よ
私の手の中にコップはつぶされてしまつた。
おお 孤独よ
おまへは ふる雨だ
扉の外に ふる雨だ。
7.
十月の月と私
忘れられた帆布(きゃんばす)を撫でるやうに
十月の夜風は美はしい月の細糸にからみ
霧は深く沈まうとしてゐる。
− 音もなく水色の軽車(チャリオット)が その時
私を運んでゆくように感ずる−
わたしの優しい人よ!
私は円い丘を 林を、せんせんと迸る流れの上を
葺きかへられたかや葺きの田家の上を
柔い光りとその蔭をみつめながらきたのです。
暫くして 私は
あやしげな小屋の前に下され
そこで その扉を落葉が叩く音をきいた、
「十月の漂泊ひ人だ」と三度繰り返したことを。
扉は音もなくひらかれ
麗らかな水沫がとんで流れてゐるその小屋の中で
私は青い凝視の女の瞳に出会つた
と同時に沫で一杯な私の瞳を彼女は見逃さなかつた
− 限りなく ゆったりと
愛の水車は 廻り初めてゐた−
つと私は大理石の卓子の上の カトリナの花に眼を吸はれ
霧!の国からさまよひ出た人のやうにあたりを見渡す
ああ オリーヴいろの仮睡の室の空気は身にしみる程寒いので。
私はつと立つていって窓辺で囁いた
「お休み、わたしの優しい人よ」
窓帷は月あかりを消してしまつたのです。
8.
しのびよる跫音
工場裏の楡の木で風がバサバサなるやうに
人力車がゆきすぎる真夜中だ、
汽笛が遠くでなつて
こよなくなつかしい思ひは哀愁の跫音となり
しづかにわたしにしのびよつてくる。
可愛らしい言葉が いまは
私の孤独の床に天鵞絨の夜着となり
内海の明るい波頭の間に漂ふ野薔薇
詩情の船は 私を不思議な回想へと運んでゆく。
靄ただ、薄ら明るい靄だ
可愛いひとの残した愛憐の霧だ
しづかに それらの跫音は 私にしのびよつてくる。
9.
秋の幻影
薄絹を纏ふた七人の女がくる
真澄みの空から しみみに流れてゐる陽の中を
桐の実をふりながらくる風と一緒に、
南向きのなだら坂にねそべつてゐる私の心へ
微かに、そして軟かに芝生を渡つて匍ひよつてくる。
アカシアの巻菓を私の耳に投げて
心の底の孤独をゆさぶる七人の女よ!
又彼女等の暖い手は静かに私の頬の上に落ちてくる
しづかに それは慈愛ふかき母の御手のように・・・・・・
私の魂の群は呼びさまされ 遠い日の幼児の心が帰つてくるやうだ、
秋が垂れた無数の銀の梯子をよぢ登り
私は 高くひろく華々しく声をあげる
ああ 喬木の頂上(てつぺん)に叫ぶ勇ましい百舌鳥のやうに。
おお だがその時 以前にもました孤独が私を滅入らせてしまふ
ひらけた展望よ、あまりに明るい世界よ
そしてあまりにも素朴な風景よ
魂よ魂よ私の登りつめた魂よ
彼女等の姿はもはや見えない、
そして 慄へてゐる花弁に一勢に
凋落の鐘が鳴り出したといふに、
木の葉の船は凡て 既に出帆の用意が出来たといふに、
ああ私は あまりにみすぼらしいこの孤独を
どう処理したらいいのであらうか。
微風は私の頬にコスモスの花弁をちらした
そのとき 私は思つた
ここで 此等の花弁に埋まつたまま死んでしまひたいと、
ああ若い生命がその孤独で張りきつたままの顔を
いま 太陽がわたしの上にふりそそいでゐるやうに
そうつと永遠に包んでゐてくれるやうにと・・・・・・
10.
十月の夜
おお夜、十月の夜
さすらひの旅がくる、わが魂(たま)に、
月は静かに かなしく、
老母の三角帽を輝らし 銀の杖の輝きは慄へてゐる。
月光に漉された夜風は 星座に磨きをかけながら
プラタナスの並木道に沿ひ
山毛欅(ぶな)の灰色にとけこんでゆく。
老母は懶く杖をきらめかし 並木道を指した、
おお 二つの魂が
青春のありつたけ陶酔の接吻に涙してゐる、
葉は葉に 熟れた木の実は木の実に
木は成長の希望に 幸福に 誇らしくよふてゐる。
山毛欅の林に杖は慄へながら 指されてゆく
おお 二つの魂が 青白い二つの路に面して
さめてゆくほとぼりの最後まで
惜しみながら手と手を取り交はしてゐるに!
老母は遑しく杖をふつた
おお おお!
プラタナスは後になりとどろき
山毛欅の林は落葉に埋まり
二つの魂は 離れ離れの棺の中におさめられた。
おお夜、十月の夜
わが魂は さすらひの旅につく。
11.
ほりぬき井戸
山あひの谷の 立木の茂みの中に
無邪気な山の娘が銀皿に真珠をころがしてゐるかのやうに、
もり上つて流れ出てゐる水の 透きとほつた響
それにまぢつて柔く縮れた 囁
おお 苔むした ほりぬき井戸よ!
おききよ! そして
膨れ上つた水の乳房に口をあてて
都で荒んだ 血みどろの瞳を洗ひなさい。
碧い空と 深緑との溶けあつた水底に
はしりもつれあふ洩れ陽よ!
少年の日の恋の思ひ出のやうに
いま涙は私の頬をつたふのである
かすかな風も すさまじい暴風雨も
この山あひの谷にあふれ出てゐるほりぬき井戸の
祈りの声に いつも終りを告げさせる、
石割男も 樵夫も旅僧も この水を決して濁しはしない
遠くみれば 青い玉のながし板のやうに
静かに光つてゐる古びた鏡
山あひの谷に「永世へのほろびざる愛」を物語りながら
こんこんと涌き出てゐる ほりぬき井戸よ。
12.
オリオン禮讃
身をも魂をも 心をも涯しない空の中に
青い白刃を額に高く捧げ
寒烈の夜風の中にみつめてゐる私のオリオンよ!
わたしのこの胸にのせた双腕のこの戦慄をしるものは卿等だけだ。
青い花は 卿等の見つむる壺の中に
狐独は青白く私の心象をつつんでゐる
何処かで! 遠い森の蔭にか
黙示録の騎士らが轡をならべて
不思議な使命をもつて待つてゐるやうだ
澱みない碧い玉虫いろの夜の空
わたしの心を透して流れ出てゐるやうな私のオリオンよ
天と地の万象のために
哀しみと憂ひと呪ひとのために
幸福と健康と完全なる愛のために
おお 私のオリオン 私の三つの星らよ。
いつまでも私を守つておくれ。
13.
翹望の西風
くる年もくる年も訪づれる翹望の西風よ!
静かな歩みで 厳かな姿で・・・・・・
聖者の薄絹の外套(ガウン)の軽く擦れあふ音が
荒れ果てた曠野の一端に触れたとき
すべての 空ろな魂の群
すべての さまよへる魂の群が
悒鬱と倦怠の谷から骸骨を擡げてくるやうだ。
祈りの啜泣きを乞ひ願ふ哀れな魂の群よ!
新しい出発を祝福せられ
新しい希望を讃美せられて 再び
西風の訪づれを心より待たねばならぬ 繰返された汝の運命よ!
細い絹糸の束を流してゆくやうな 梢を渡る風のさわやかさ、
いきりたつた嫌悪の血に にじんだ 総ての景物らの上に
洗礼の水を注ぎゆく 西風よ。
いよいよ深く静かに 高く高く広ごりゆく
おお偉大なる宇宙塵の映え!
疲れたるものの魂に精霊をそそぎ
野のポプラに棗に柿に 楓に
畠の葡萄に 林檎に 稲に野菜に 人の子の魂に・・・・・・
ふれるとなく しのびいり
いるともなくふるる翹望の西風よ!
14.
初秋の神経衰弱(ヒポコンデリー)
西風にからんだ夕陽は白亜の洋館を青白く輝らし
夢につつまれたまろ柳のさ揺れさゆれのかいまかいまに
青い あーく燈のほの白み
ゆきすぎる女の青白い顔、顔・・・・・・。
振り返りふりかへり辻に消えた細つそりしたその姿
小間物屋のういんどの雑多な色彩におののきおそれ
わなわなふるへた心やおびえた胸をおさへ
かけるやうにして消えた その長い影。
影のままの柳の 幽霊
ああ それら私の頭にこびりついた疲れた魂の幻よ!
15.
十一月の夜風
瑠璃l紺の空に囁く群星をみまもり
おほらかに流れてゆく 十一月の夜風よ。
私は百姓家ののきに きいた、
辻占売の婆あさんの声を
鐘形の桐の木の実に!
落ちた葉が おぼつかない跫音で
擦りきれた彼女の草履を模似(もぢ)るのを
私は森のくろの椎の木に きいた、
救世軍の涙ぐんだ兵士の福音を
一つびとつの木の葉に、
散つて行く木の葉に
森に福貴せられた木の葉に
忍従と 復活と 愛を!
私は曠原の銀杏に きいた、
光りに充ち 慄へてゐる男の祈りを、
大地に近く走つてゆく霧に。
裸の枝が一つに合して
天に手をさし展べて共鳴きしてゐるのを、私は
涙のうちみやる、
降りしきる霧は再び地から匍ひ上り
静寂と啜泣きの滴の中に、沈みゆく殿堂に、
星々の頌歌を軽く閉じた瞳に眠らせ
十一月の夜風が憩はんとするのを。
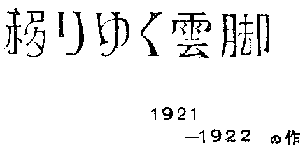
《 移りゆく雲脚 》
16.
桐の木
葉つぱーつない桐の木だ
枝といふ枝をもぎとられた桐の木だ
青い窓帷のまへに黙した
腕のない男の裸身像のやうな桐の木だ
遠い日の私の愁情のままに
ああ いまも その緑いろの皮膚(はだ)刻まれたままの「生」(らびい)よ。
漂流(ながれ)ついた二十五の春近い寒空に
途方もない思ひで つつたつた桐の木だ。
葉つぱ一つない桐の木だ
枝といふ枝をもぎとられた桐の木だ
胸いつぱいの涙をたたへた空に
口をつむいだまま つつたつた桐の木だ。
17.
下弦の月
下弦の月は豫言者か。
冬枯れの野には いま
霙の群が傷ついたまま縮こまり
風は埋もれた街にまで
その冷寂を沁みこましてゆくかのやう。
林なのであらう
まばらな錫の柱の佇立
棟上をしたばかりの家並のやうに、
旅人の心を放つた丘よ
ああ そこには永遠に立ち上りそうにない駱駝がうづくまり
涯しない星座をみつめてゐる。
流星だ! おお
沈黙は一層厚味を帯びて
裸木は一本きり立つたままである
風・・・・・・風!
そうして下弦の月は総てをてらしすべてを見守つてゐる
すべてもの結末を豫言する鋭い刀をもつて
寒烈な風のなかを徐々に歩いてゐる。
18.
静物
それはまことにふくよかな乳房だ、
白い孔雀の胸のやうに
紫檀の卓子の上にうつつてゐる 白いダーリアの花よ。
若い母親の胸に眠る幼な児のやうに
月暈の光輪を戴く白いダーリアの花よ。
真白いダーリア
紫檀の卓子の上に いくつもの光輪が描かれる
わたしは烟草をそうつと消して
ぢつとみつめた、
物音のないひとときだ。
19.
夜の畑
何も下されて以内うな まつ黒い畑だ
誰もこないらしい夜の畑だ。
眼に見えぬ成長があるとは思はれない暗さだ。
ただ丹念に魂の呻き声ばかりが
何物かを創造しやうとしてゐるのだらう。
しかし ああ なんといふ恐ろしい静けさだ。
彫塑家は何をしてゐるのであらう
思索家よ 思想家よ 政治家よ
卿等は何をしやうとしてゐるのか、
又土木家よ 建築家よ
卿等はどこに鎚を下そうとしてゐるのか
詩人よ 卿はこの夜をどうしやうとしてゐるのか?
畑はなにも下されてゐないやうにまつ黒な畑だ
誰もこないらしい夜の畑だ。
20.
菜っ葉の畠
まつさほな菜っ葉の畠だ、
まつさほな薫りでみなぎつてゐる畠だ
ばらつと音を立てて襞をのばした葉つぱよ
そこここ畠全体の低音(バス)よ。
青い空の下ではく素晴らしい若者の魂の虹よ
ぱらつ!青い葉っぱの顫動、
空を擢うにのべられた全身よ、双腕よ。
私も大きく大きく呼吸する
さわやかな光輪を無数に上げて
青い葉っぱの薫りを一杯呼吸する。
21.
四月の夕立のあとの野原で
四月の夕立の通りすぎたあとの
限りない青さに浸つた野をごらんなさい
繊細な雨脚によつて踏まれた青草の薫りと
そこに いまも陽炎が描く華やかな円舞を!
木立の彼方へ消えた青騎兵よ!
針葉樹の いるみねーしよんを透して
私は通りすぎた四月の夕立を切に思ふのです、
そして
黄色な痺薬(しびれぐすり)に酔つた松の花粉を浴び
合掌の手を綻(ほぐ)した杉の芽を感じ
落ちた若楓をふんで そうつと
雨上がりの町の場景を私は空に、野の上に想ふのです、
ああ それは蜃気楼のやうに
草野葉っぱの上に現はれてくるのです。
22.
夕暮
夕暮が 空の薄紫の絹窓帳のすそに戯れてゐるまに
白金の微塵はいつかいろ褪せていつたのです。
ああ そこには、遠くつづいた監獄の黒い木柵
−−ゆるされぬ夕焼けいろの衣をかくす−−
堤には白蒲公英が揺れながら咲いてゐるのです、
中世紀風な読経師と典獄とがその花をさしはさんで立つて、
憐れな女の最後(いまわ)の言葉を繰り返してもゐるかのやうに
低い声で耳打ちして射るうに思へるのです。
夕暮の鐘が烏麦の畑をさわがせ
去りゆくもののみが落とす果敢(はかなさ)は ああ悔ひの朽ちはてた幌馬車
又人気の落ちた曲馬団の天幕(きゃんぷ)の破れ穴!
ああ 虫ばまれた毛繻子の洋傘を天にささげた夕暮よ
妙に 危つかしい足どりで闇への路を辿るものよ。
妙に 危つかしい足どりで闇への路を辿るものよ。
23.
七月のある日の私
雲のない七月の空にみるのは ある日の私
刻々すいこまれてゆく私の眼 そうして眼!
(空虚はこの瞬間(とき)私の頭を占める)
郊外に捨てられた貨物列車と晴れた空は
新しく私に甦つてくる。
堀割にうつつた歪んだ倉庫の影に沿ひ
紡績工場の煉瓦塀をぬけてきた私を捕へたものは
芦のうに騒ぐ褐色の裸麦の群
おちかかつた夕暮れどきのほの明るさ
忘れた風車が立てる一日の消息!
亜鉛葺の停車場の構外
一際高い ヤードの堤上の黒い木柵、
きえていつた彼の姿よ!
一日をまだ私の瞳の奥に光らせる空よ!
雲とてない七月の空
まことに怠惰は空のやうに余りに私に懶い。
24.
秋の会話
急ぎ足にくる若人に私は出遇つた
私の思ひ出の村へ入る道で
彼は壮健でゐて、いかにも悩ましげに見えた。
「君は村から来たのだらう」と私が謂ふと 彼は
「そうだ」と頷いて 溜息をした
「そこで君は何処へゆくんだ」と私は尋ねた。
(沈黙はあたりの霧よりも もつともつと厚かつた)
「さあ、永遠に耕すためにだね」と彼は暫くして云つた、
「何故収穫のあとの落穂の上を歩いて来ないんだね」と再び云ふと、
「花が開いて、営みがたしかとみたら もう用はないさ」と彼は
きれぎれの微笑をもつて言つた。
「村の祭の準備が そこいらの軒からきこえたら
稲の中で愛らしい囁きがきこえたら
もう私は行くんだね」
「何処へ?私はよつく知らないけれど見知らぬくにへ
この霧と共に行くんだ、
耕しつづけることは同じ愉快さだ」
彼の足あとには朝霧がうすれてゆく星を宿して
再びかへりそうにない彼の姿が まつたく霧の中に閉ざされてしまふときに、私は
私の思ひ出の村へ入る道に立つてゐた。
(樫の梢で百舌鳥が鳴子を引き初めたのでした)
25.
小径
柳がこさえた緑の天蓋のもとで
いつまでも動かぬアイスクリーム売の円るい背のやうに、
草深い野つ原の上の月よ
車道との境の溝石野うに
いま 私の足許にまできてゐる小径!
かつて私共とともにあつた美しいひとの跫、
おお 私性質はつく知つてゐた
そのこみちが導いてく先きを。
しかし ああ私は その道をもはやひとり
変わらない昔のままのその道を辿つてゆく
玉虫いろの空はだまつたまま
微風は胸に秋の愁情を唄ひつづける。
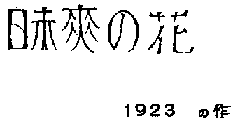

挿画 「HANTINGSの戦のエピソード」
《 昧爽の花 》
26.
小さい展望
矢車草の上には 空
虞美人草の花びらには 微風
そこに私の小さい展望は 孔雀の翼のやうに
悦びの音をたてる
翔けるものは 華麗な都への愛着
元気づけるものは 爽かな六月の太陽。
27.
影
どうむの中に紛れこんだ光りのやうに
深い眠りの室に沈んだ畑、山、野原
そして かくされた家々や木々の中へ
見捨てられたその夜の一方の戸口から
頭を差しいれた月あかりよ。
そのとき 防風林の蔭は
不思議な生命を胸に持つた老人のやう
額たかく のびきつた彼の脛と足と
起伏した原への線を輝かせて
思ひ出の村に長く黙したものの尊い背骨を私に見せる。
あるひは
うしろにうちつづく砂丘は古びた露台
誰とて訪れるものもないに
ああ今宵、薄がすむ そが長き欄(おばしま)に
しのびよる影を見しらぬ私ではなかつた。
冬、冬、冬、
きえてゆく一つびとつの虫の呼吸につれて
小の廃園に誘はれてくる木の葉の囁きよ、
かくて 私のうちなる老ひたるものは
私のうちなる若者に別れをつげてくるのだ
ああ影、影・・・・・・
ああ私のうちなる老ひたるものの投げる影。
28.
ぬかるみ道
それは 雪解けのぬかるみ道
いく日もいく日も 雪解けの快翔音(もつあると)に
苦笑ひする慈父の顔だ。
灰いろの空は天のものとも思はれない
ただ どんよりと
そこをゆきすぎる幼な児の柩のみが落とす投影のやうに
また、窖(あなぐら)に永遠に眠る人の夢の花葩のやうに
薄ら明るいぬかるみの小さい丘々の 片映りの片映り・・・・・・。
薔薇いろの朝を 誰が再びみせようぞ!
野外遠足の少年等によつて歓声の砂埃をあげるこの道に、
ああ いく日もいく日も 渋面つくつた憂鬱の空よ!
苦笑ひする慈父の顔よ。
29.
石炭庫の生ける彫刻
投げられ 又投げられ
生命の川のやうな凹んだ地べたに
象牙の花符(いた)は投げられる。
瞳の瞳の瞳
いりくんだ凝視の底に
又投げられる象牙の花符
郷愁の唄は涙の波浪をつくり
亡国民の無頓着は溝に泡を上げる と
ぱちつ! そうして又 凝視!
石炭庫の彫刻は その石炭庫だけが知つてゐる
秘密な生命が蠢動してゐる と
ぱちつ! 象牙の花符(ふだ)は又投げられた。
30.
扉
夕暮れの中に 私は
扉を閉(た)ててゆく不思議な老人を見た。
廻廊の柱は落葉林の並木のやうに
そこに みえがくれする老人の独言を きいた。
「卿もこれで終りなんだ
俺の室は運命だけが知つてゐる
俺の知つてゐることは ただそれ丈なんだ」
最後の扉が 閉じられるのをきいた
彼の顔はその時 その音とともに消えたんだね
「夕暮が扉を閉(た)てたんだ」と私も考へ直してみた。
31.
感化院の夕暮
夕暮はそばの畑に
うすら寒い微笑を揺がせ
十月のさすらひ人の口笛は
感化院を回るアカシヤの並木の梢に強く
木の葉はさわぎ、木の葉はいたむ。
ほつかり浮いた野霧に
胸までも閉じられてしまつたやうに
私は立つたままである。
アカシヤを透して立つた一人の少年のやうに。
「ふるさと遠い夕だ
悪魔だつてきつと寂しがるに違ひない夕だ」
そう独言(つぶや)いてゐるらしい彼の涙ぐんだ瞳だ。
「ああ ダイヤモンドをまきちらしたやうな
夜の海の街!
まあ!ここは何んといふさびしい荒れ廃てた山峡だらう」
そう考へてゐるらしい彼の蒼白い顔だ。
「ピストルやギラギラしたナイフや
だけど、もう何一つ私はもつてゐない
たつたこの一つの口笛よ、最後まで私の所有(もの)よ」
ふるへる彼の鼓動の赤い唇の顫律よ。
とり囲んだ山々が 特にこの感化院にゆるした窓は
せばめられた西の川口に
野霧はこの最後の川の残んの薄ら明りをうばつて
いま この感化院のアカシヤ並木をも閉ぢやうとしてゐる。
おお 十月のさすらひ人よ。
彼の口笛にいつまでも合はせておやり
限りない魂のために、私と共に口笛を吹かう
いつまでもかぎりなく・・・・・・
この感化院を回るアカシヤの並木の梢に強く。
32.
夜がもつ情緒
火のきえた すとうぶは
とまつた時計のやうに
月かげをとかした窓硝子は
火と蔭ない大通りの見張人のああく燈である。
ただ じつと考へてゐる。
机も 柱暦も 書棚も・・・・・・
恐らくこの世界全体が 途方もない企図(たくらみ)のために
この夜の向ふ岸に ひそんでもゐるのであらうか。
何もこの夜をくづすものがない静けさだ
恰も 深い静けさの底から
遠い遠い海の果てから円んでくる上潮の波浪をひしと感ずるやうに
私は夜の霊魂を身内に そして夜気に見るのだ
陽照りの中で手を翳して健康の実証を捕へるよりも明らかに、
夜はしんしんと夜気にくひいり
かくされたふくよかな抑揚で胸にせまる
ああ それは未亡人の膝の上に眼をとぢ
青いや屋根の上の恋に思ひふける白猫の情緒か!
だが それ以上みえない音だ
また それ以上きこえない静けさだ。
33.
昧爽の花
ものうい夏至の姿で その不思議な千年の枝を
すいすいと展べた若竹よ!
健康そのもののやうな村の子供や 娘たちの
はしやいだ声をもつた竹藪のくろを 私は歩いてゆく、
しんめとりーな六月の空にとつて
それは美はしい昧爽の花
私の頭上に音たてて開くおもひである
34.
西風
碧空には白い雲の岬
容貌(すがた)みめよき木には微風
忘れられてゐた風鈴の立てる音いろのやうに
どこからともなく胸にせまつてくるものよ。
破れた葦の槍旗(ペナント)を翻す西風
虫どもの秋へのおおけすとら
広がつてゆく波紋が石垣に立てる接吻(ベーゼ)
私は静かに、静かに
彼女の崇かな歩みをききとらうとする。
35.
夕暮
夕暮はいましがたいつもの静かな老人の手で扉の握りを採り
室といふ室、街といふ街、野から山から・・・・・・
すべてのものの上に投げる彼の長い影を
克明に私は見送る。
雪解けの春への一つ一つの歩みや
永い冬への哀悼歌やすぎさつた春への遠い思ひ出の数々を。
どうかすると彼の腕をうしろに組み合はしたまま
立ち停つてゐるのに出遇す。
土曜日の公園の元気のいい噴水塔に、
微風が鱗雲の間から夏物売出しの赤旗を翻すあたり、
すばらしい月が子供達の心を欣ばせるとき
花聟が青葉の風を呼吸しながら待ち遠しく待ちまうけてゐるとき。
夕暮は又かげらうの翅の朽ちる音をもち
戦ひ終えた野戦病院の多くの傷病兵の黙示した天幕になりはためき
家出したまま行方しれぬ乱行の妻を思ふ老いたる夫に
異郷に子を失へる息子や嫁の思ひを己が胸にきざむ老母に。
鳴り初めた風車の音とともに
裸麦の畑から畑へきえていつた彼の姿を、 私は
百姓家の朴の梢にうすれた空に眺めた。
おお 老人よ
夕暮をもたらす老人よ、
死の人のあたりに墓場の塔婆に
あたらしいかなしみを亜麻色烏と 小笹薮の葉擦れに共鳴きし、
しめつた壁からとび出す蝙蝠のやうに
あはただしく歩いてゆく老人よ
ふいにおそつた嵐や、地震や、火事や
君はそれらに耳をかたむけるのでもなく
又眼を返へすのでもなく
再び訪づれる変わ果てた扉の前に立つとき
ああ いかに卿は おろおろして手をさしのべることか?
丘に屋根に、海に 野には夕暮!
季節々々の影をひきながら
はるかにも遠い昧爽への闇に消えてゆく老人よ
玉虫いろの夜が祭りをするまで
まだ 見はりをする老いの眼よ 西の地のはてのうすらあかり。
36.
蜘蛛
くいえた花葩を集めやうと
私は回想の夕映えを帯び
一日の私の心をとりもどすために
暢びやかな網をはりめぐらし
そのまなかに私はぢつといのりつづける、
せまつてくる夜気に乗じ
私の広い網糸に触れる鋭い明るい虫を捕へやうと
私は私のすべての触手を集め一心に
詩情への邁進を夢みる蜘蛛である。
37.
土曜日の午後の保姆へ
コスモスの垣の下に虻や黄金蜂の音楽をききながら
優しい夢にぼうつと白い毛並を慄はせてゐる子猫のやうに
土曜日の午後の幼稚園は静かだ
微風が椎の実を通り雨のやうに木の葉から木の葉へ
その看をつし、そしてつひに地へ落としたとき
忍びかなピアノの音いろはぬすむやうに
育児室からきこえはじめる。
保姆 卿は何をゆめみてゐるのか?
ぶらんこ そう鞦韆はかすかに揺れてゐますよ
池に山茶花は落ち
浮び上つた金魚は又つまらなさそうに沈んでいつたのです
ああそのやうに遊動円木の鎖はふと音を波立たせました。
そして私は、ひらけた窓帳を西風にまかせておきます。
ああ保姆さん!
秋の長い影はあなたの足もとまできてゐますね
あなたも年とつた、そして私も・・・・・・
いやに落ちつきはらつた時の冷眼のしづけさ!
「ええ ままよ! ええ ままよ!」
ああ百舌鳥の叫びごえ
あなたは強い鍵盤(きい)へと指を走らしてゆくし
私もあなたの海港へと詩情の舟を操つてゆく・・・・・・。
−−しかし すきとほつた白いかげろうの翅が
ああ いつぱい室へと流れてくるやうだ
どこともしれない初冬の姿が
中庭から、育児室の白いかあてんに
そして そこに瞑想して保姆の心へ・・・・・・
土曜日の午後の幼稚園のしづけさは
ああ それらの影をもつて彩られやうとしてゐる。
38.
私はすいっちょ
私はすいっちょ
西風にくづされ雲の峰や空の天蓋から
れいろうと秋情への落下傘をあやつり
松や白辛樹(あさがら)や芙蓉、又莱(あかざ)の茂みにをりて
沈んだ夜の魂を思ふさま呼びよせやうとする。
私はすいっちょ
破れた葦の葉に乗り 一心に
新しい露を触手にあつめ
湖心への清らかな光りを眩にうつし
天真へのま澄みゆく微塵の行列をみつめて
殉情への哀愁を十月の夜風にふきこめやうとする
私はすいっちょ
折れた向日葵の大輪のかけで
傾いたうつら陽を紫苑いろの空にみつめ
タ暮 木梢(こぬれ)の上に翅の音をぬすむ赤蜻蛉のやうに
遠い日の生活のはろかさを限りなくいとほしみ
ひらけた夕への精神に共鳴きしやうとする。
39.
惜しくもふりかへる
小川の土堤
葉と葉とうちならしあつてゐるポプラの並木道までくると
妙に 私は傾いた十月の日脚を惜しくもふりかへる
寺の正しい屋根や 実つた稲の出来栄えや
秋の素描風な藝術家の百舌鳥や風の
おお それらは西へ西へ・・・・・・うつつてゆくやうだ、
うつりながら 沈んでゆく冬の谷の黄昏!
街から帰つてくる牛車の鈴の音色のやうに
ああ ふりそそぐ空の微塵の眼を過ぎること・・・・・・。
夏の風情がまづ空からくづれてゆくやうに
落ち葉の跫音に先たつて蕎麦の畑におりてゆく
憐れな放浪者の上げる烟草のけむりよ。
かくて 私のまへの柿の木に亜鴉はおりて
私の回想の木の実を啄みながら
色づいた葉つぱを風に思ひ出したやうに投げるのだ。
明るい夕暮だ
川辺のポプラの並木道までくると
ポプラの葉つぱと同じやうに 私は
傾いた十月の日脚を惜しくもふりかへる
畢
跋
陶山篤太郎
昧爽の花に文を求められて、私は何よりも過ぎた或る日、氷をもつ
て私の室の熱風をさました夏の宵に親はしく相識つた折の君の顔を
思ひ出す。雪のやうな白服に房々とのぞかせた黒のネクタイも、君
の若々しい頸の肉線へ風のやうにさつぱりとした印象を見せてゐた
その時君の趣味の温雅が花のやうに静かに君の精神の帆となつてゐ
ると思つた。
私はかすかな甘い哀感をそそられるほど君の若々しさに打たれた。
今でも、あの日の感味を忘れずにありありと思ひ出すことが出来る。
今日、君の新しい詩集を結ぶとき、その跋文を送ることは深かい愉
快である。幸ひにして、この不文が君の詩嚢にあやまちのないこと
を望む。
強めるものは、その純情の飛躍を思ふ存分唄ふ場合に於て、一種な
んとも云へない味感を与へると私に思ふ。
新しく生起した自由詩に対する日本詩壇への論定はまだ早やい今日
君の如く、若い精神の詩人のあることは楽しまなければなるまい。
君も開放された窓の唄人である。その自由と奔放に於いて、一番精気
のつよい群の一人である。朗々と快適な精神を唄へ、こう云ふ方向
を祝福する詩人として、いよいよその交霊の巧みを深かめ、その美
彩を新鮮な詩品に印刻されることを私は心願追慕する。
君の第二詩集を祝ふため、互に精進の純情を昂め、詩字の鈍重を破
り、独創の形律に霊覚の光彩を妙音あらしめることを、ひそかに誓
はんとする君の詩友の秘語を心よく受けられることを希ふ。
一九二三年、十一月三日記。
目次
序
「久遠の柳の詩人(うたびと)に」添へて再び
「昧爽の花」の著者に。 (春山行夫)
風貌の頌 一九二〇の作
1 .久遠の柳
2 .わが旅
3 .陶酔
4 .軽い嫉妬
5 .青いらんぷ
6 .孤独
7 .十月の月と私
8 .しのびよる跫音
9 .秋の幻影
10.十月の夜
11.ほりぬき井戸
12.オリオン禮讃
13.翹望の西風
14.初秋の神経衰弱
15.十一月の夜風
移りゆく雲脚 一九二一 ,一九二二の作
16.桐の木
17.下弦の月
18.静物
19.夜の畑
20.菜つ葉の畠
21.四月の夕立のあとの野原で
22.夕暮
23.七月のある日の私
24.秋の会話
25.小径
昧爽の花 一九二三の作
26.小さい展望
27.影
28.ぬかるみ道
29.石炭庫の生ける彫刻
30.扉
31.感化院の夕暮
32.夜がもつ情緒
33.昧爽の花
34.西風
35.夕暮
36.蜘蛛
37.土曜日の午後の保姆へ
38.私はすいつちょ
39.惜しくもふりかへる
跋 (陶山篤太郎)
目次
附記
附言
いまは 永い願望の過去の日に喜納といふことが出来るときだ。
そして朝紅が齎したこの「昧爽の花」の一巻を世に送りやられる
欣こびのときである。
夜がその顔をかへたとき不思議な風貌が表れた。そして移りゆ
く雲脚が確信を私に与へた。ひそかに自分自身培つてゐた夜の畑に
土壌を破る芽の音をきくやうに。
おおその芽は驚くほどの速さで成長話つづけた、そしてとうとうそ
れ自身、雲を、夜を完全に破つた。朝が立派に私の昧爽の花を迎へた。
そしてそれは私にとつて可成な擽つたさである。いかにもヱ゛ルハ
ーレンの「錯覚の田園」を先きにして「触手ある都会」を後にせる
如く、私はいま、都市雑曲集「黎明の林檎」のために心労してゐるか
らである。
その詩篇は殆ど終り華々しいその光彩図の電気花火をいかにも
配置よろしく綴らうとしてゐるため、どうしても私は過去四ヶ年の
花葩を集めて私の昧爽への花束とせねばならないことになつた。又
一つには「青騎士叢書」の刊行に関して 私は私の過言二ヶ月のバ
ラツク建の前詩集「青い嵐」を中心とした過去及び現在にとつてか
なり深い意義を与へてくれたこれらの詩篇をより先きに刊行せなけ
ればならない立場へきたわけである。
その故に私は或は都市雑曲集「黎明の林檎」のまへにこの「昧爽
の花」に引続いて青騎士叢書の第三編として抒情風なもの、大人の
童謡、そして「昧爽の花」以前の「夜の静かな祈り」を集めてそれ
らに充てやうと思ふ。
順序は概ね作順としたが覚束ない記憶のものは心情にまかせた、
だから作の品姿によつて或は調階に従つて分たれたやうな流暢さを
持たせることが出来ないのは私のぎこちない性情によることで厚く
赦して頂きたい。
近刊する都市雑曲集「黎明の林檎」及び青騎士叢書第三篇と共に
併せ読まれたならば、私は幸ひにして私を見出して下すつた人々に
完全に居住することができると信ずる。
装幀は常々親切を尽くしてくれる水野義正君によつて飾られたこと
燻つた洋燈のかげで劇しい感激の嵐をまき起した春山行夫君の序及
畏友陶山篤太郎君の跋共々私は有難く思つてゐる。その他、井口
蕉花君の助言を感謝する。
近々訪づれるといふ佐藤惣之助氏、百田宗治氏と未曾有
の震災のために東京の街にさまよつてゐる福士幸次郎氏に捧ぐ。
大正十二年十月一日 著者
詩集 昧爽の花 畢
表記は仮名遣ひの不統一などすべて原本に従った。ルビは( )内に記した。
新漢字のあるもの、明らかな誤植はこれを改めた。詩篇には頁の代はりに番号を新たに付した。すべて原文画像に就いて参照されたい。(編者識)
コメント:
四季派の外縁を散歩する「名古屋の詩人達 その1」
Memorandum :高木斐瑳雄のこと
たかぎ ひさお【高木斐瑳雄】(1899〜1953)