
詩集 街の犬
伴野 憲 第一詩集
昭和2年4月1日 新生詩人會(名古屋)刊
152p 19.5cm×13.7cm 上製函 \1.50
著者自装 限定120部
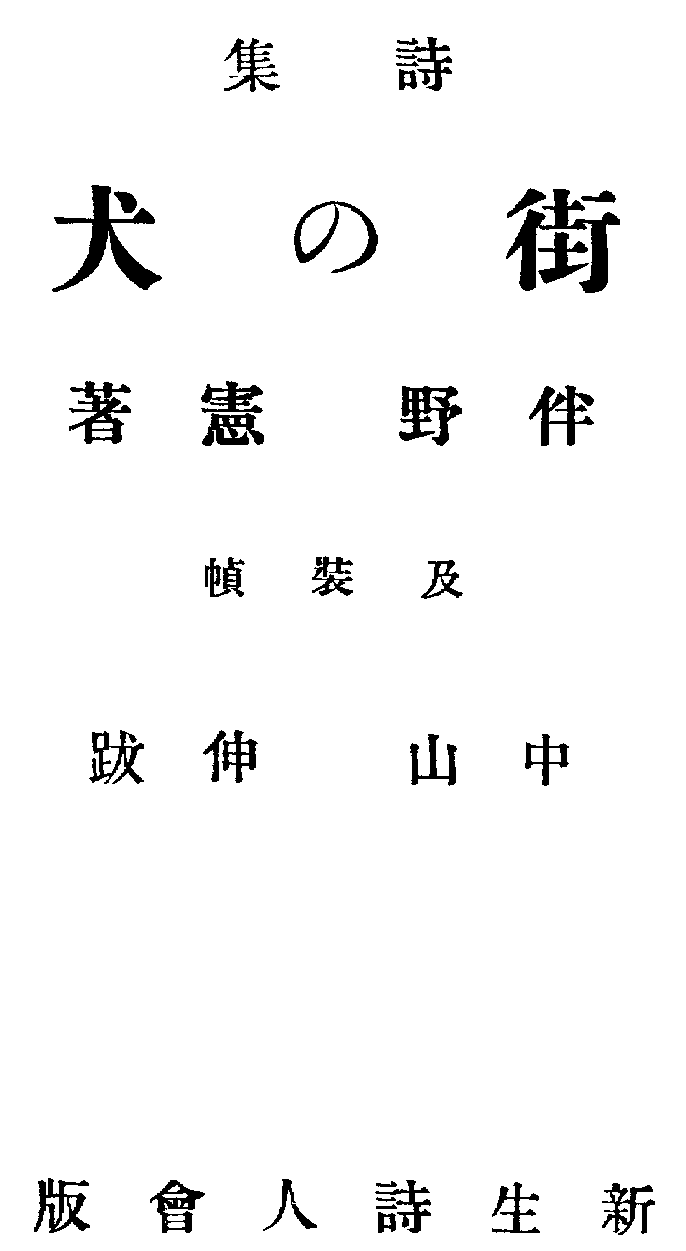
(2002.11.25u / 2022.07.06update) Back
ばんの けん【伴野憲】『街の犬』1927【全文テキスト】
序詩
この牝犬は
バスと呼ぶいぢらしい奴です
英セツター種でもとりわけて
すつきりとした姿体(すがた)がたまらない
生後まだ五ケ月にしかならないが
今に二尺の餘にまで伸びようとする大物です
バスはいつも空腹(ひもじ)そうに
通りすがりに人人の匂ひを嗅ぎます
往きずりの娘さんにたはむれたり
愛撫する奥さんの唇を舐め
または
ご馳走を包んだ風呂敷包を迫ひ廻ります
バスはしかし
それでも
お預けをよくします
そのとき
なさけ無いといふ瞳をぢつと私に注ぎます
歩いてゐてよく方向を違へます
まだ臆病なほんの仔犬ですから
バスは
遊び戯れてゐる小供らの群へ飛び込みます
そして
大きいやさしい瞳を
いつまでもかれらに向けてゐます
この牡犬は
バスと呼ぶいぢらしい奴です
目次
序詩
1 .もの寂た時計
2 .こよい晩餐の卓
3 .五月の草笛
4 .夜来の暴風雨
5 .いろ絵図
6 .寝息やすらかに
7 .ひとつの壺
8 .刻まない時計
9 .伊良湖崎十三唱 イメージ
竹垣
岐路
浅春
砂山
流れ木
天南星
紅い椿の隧道
団欒
神嶋
危険信号柱
鷹
蘇鉄
小魚
10.夢のようなマリオネツテエ
11.秋の行人
12.夜霧
13.行軍
14.化猫
15.蒼白い体
16.落葉
17.路上の六花
18.売られゆく仔犬
19.街裏の犬
20.ジヨル男爵のころ
21.引車
22.憂鬱と犬
23.ヨシの体験
跋文 (中 山 伸)
附記
装飾著者
1 .もの寂た時計
わたしは
ひとつの
もの寂た時計を知つてゐる
燻つた頭蓋骨のベル
ちようどぶらさげた二つの分銅が重い足
奇怪な掛時計は死のやうに
四辺いつぱい沈黙にせずにはをかない
それは自鳴鐘の昔
怪奇な知識であつたにちがひない
黒鼈甲椽の丸眼鏡
こつ こつと時を刻みあげる
新人老時計師の形相が
その
煤びた面のをもてに
計りがたい微笑をみせてゐるようだ
もしも
環つて
鈍銀の針が子の刻をかげさせば
うしろから現れたちいさい金槌が
頭蓋骨を根気よく横擲る
そして
さびしい九つの音が
夢夢(ぼうぼう)として消えてゆく
九つは
真夜中三更を鳴りわたるのではない
醒めやらぬ知識の夢が
塵深いなかから起きあがらうとするようだ
ふるいものがふるい姿で呼ばれたようだ
だるく だるく
ぎりぎりと
さがる二つの分銅
ああ この
ひとつの
もの寂た時計は
ゆるやかにくわへた長煙管
奇に満ちた赤い壁掛をうしろにした
異形の老時計師か
古いものが素直なその古さで
煤びたなかにまさしく起きあがろうとし
夢か絵か
さまざまになつかしさを覚えさせる
2 .こよい晩餐の卓
舶来(わたり)もの玻璃(びいどろ)の酒盃
想ふにさき幾とせかの昔のもの
不透明な空色のがひとつと
をなじく紫のがひとつ
一対の被璃の酒盃とその盃台
これの不可思議なたましひは
日本風に作られた巧な製図の味覚をたたへ
静かにしたしみ深くうるをふ
かつて聖母甲比丹(さんたまりあ)の館で
羅紗と天鵞絨の姿きらびやかに映す
アネン フソロンの酒に夢奇異なる
洋盃のたぐひなどとはひとつでない
それはいにしへの錦絵のこころ
舶来もの玻璃の酒盃は
あの歌麿の絵の姿
また簾車の空色ご紫に憧れるはるかな夢か
たこへば富士のさつそうたる風景
あのメルサンの鐘に
接吻の異風さびしい洋妾のなされを忘れかね
異国で作られた日本のわびしい装ひか
ああ いまそのころの同胞(はらから)を想ひ出でて
こよい晩餐の卓はつねのようにかわりはないが
なぜか想ひ深く哀しみ多い玻璃の酒盃
3.五月の草笛
ああ
まどろめ
まどろめ
桜若葉を風が渡る
水かさみ
みどりふかみ
歎き
いよいよ蔭にこもる
少年(こども)らよ
われも ひとつ
汝(うない)らと
五月の草笛をふかむ
このままに
まどろみ
まどろみて
夢ながらわれも五月の草笛をふかむ
4.夜来の暴風雨
パンの小袋の外
傘をすて
僅な持物をも投棄せよ
足駄も脱げ
素足になれ
そしてこの一切れの防水着にくるまり合つて
ゆうよなく急がねばならない
いまや
黎明が夜のかなたで動きはじめてゐる
疲れきつた歩調
冷えゆく体温
震える腕 頬をつたふ涙
すべてを叩きのめす暴風雨(あらし)
暗い暗い底知れぬ裂目が
いやがうへにも
大地を割り開くのではあるまいか
この大暴風雨の虐げに
なにもかも木葉微塵に
粉砕(くだき)飛ばされてしまひそうだ
裾濡し 脚払ふ暴風
土砂降る雨
天は堕ち地は裂け
荒れ狂ふ暴風雨(あらし)
ごう ごうと乾坤の号叫が
どこまでも息苦しく突走つてゆく
おお
パンの小袋の外
傘をすて
僅な持物をも投棄せよ
足駄も脱げ
素足になれ
そしてこの一切れの防水着にくるまり合つて
ゆうよなく急がねばならない
あの揺れうごく小山をひとつ
海岸(きし)にそそりたつ
険しい松山をうち越へよう
そこには
素朴なひとらの漁村があらう
そこには
孤寂な彷徨ひを打ちあげる
真白な砂浜がながくつづき
看護(みとり)やさしい太陽が輝いてゐよう
そこは
激しい情熱に
安息と慰藉との
祈念と信頼のうつくしい殉情
ひろびろとした明暮(あけくれ)が
まばゆいばかりに
愛の草屋を
なごやかにめぐりはじめるにちがひない
おお
濁り黄ろい漲濤
断たれ飛ぶ暗雲
動乱(みだ)れ
動揺(ゆ)れる海
うちのめされる小松の幹
みりみりと
大松の支幹(みき)がひき裂かれる
おお
脅威 蹂躙 晦冥
暗澹たる暴風雨の奮迅を怖れずに見よ
そこには
傷ましい啓示が微笑むでゐる
なほも
永劫なる腕のなかへ依りかかれと
行かう
南方の
あの慈愛深い抱擁をもとめながら
おお
パンの小袋の外
傘をすて
僅な持物をも投棄せよ
足駄も脱げ
素足になれ
そしてこの一切れの防水着にくるまり合つて
ゆうよなくさきを急がねばならない
5.いろ絵図
いと寂た床しい彩色の絵図に
いさましい彼と
たをやかな彼女の姿があつたのを
ひと知れず思ふことさへある
それは古風な紋服のさむらいと
あでやかな友禅の振袖のたはれ女
射干玉(ぬばたま)の黒髪もつややかに
露はな足の指には激しい力がこもつてゐた
それは春浅い日の
夕まぐれであつたにちがひない
外の面にはうす寒い風が流れ
緋縮緬の座布団の端で
そつと寒さに盗み触れたにちがひない
新らしい障子の真白さ
暖かそうな唐紙の部屋には
ちようどあの青々とした藺畳の匂ひが
焚く香のかほりに染み込んだことだらう
私は私のなみうつ血潮の寂しい流れが
彼と彼女のでもあるかのように
もの寂た
床しいいろ絵図の淫らさを悲しみながら
ひと知れずふと妖夢につまされることさへある
6.寝息やすらかに
睡るときだ
だが 熟睡(うまゐ)過るほど睡られないときだ
もう花分の衣を
そつと脱いだころだ
五更に睡を愁へ
また日日まどろみの夢を
爽かな五月の風にゆだねようか
春餘新緑影濃い風に
睡られるときだ
睡つてくらせるときだ
寝息やすらかに
寝息やすらかに畳の上へ寝そべるときだ
7.ひとつの壺
寂しいではないか
壺
お前は壺
白滋のなめらかなぢ肌の
丸味のなかにも
一味のさび
その光のなかにも
蔭がある
かはたれがある
たつた
ひとつの壺
寂しいではないか
桜
牡丹
紫陽花
そして
女郎花
寒菊
糸のような線描
藍絵のうすさにも
蔭がある
かはたれがある
そのなかにも
たつたひといろ
女郎花の黄花が
それは
若い未亡人の
うち沈んだ首飾のように
楚楚
壺
壺
寂しいではないか
8.刻まない時計
いつからか
思ひ出せない
ながい前から
部屋の分銅引時計が
静止のむくろとなつて
それは 柱によりかかつてゐるようだ
古ぼけたひとつの図体
図体にさがる二條の鎖
ひこつは寅
ひとつはその下方に
重たいふたつの分銅をぶらさげ
埃のなかで
無表情な数字の顔を見せてゐる
その顔は
奇怪な半日の目盛だけで
まるつきり充分してゐるではないか
私は
この静止の時計に
力強いしたしみを感じてゐる
なによりもすぐれて
悠久な知識が
白い象牙の数字を地紋にして
刻まない半日の顔で
いつも私に笑ひかけてゐる
思ひ出せないずつと前から
伊良湖崎は渥美半島の尽頭にして、伊良湖を或は伊良子、伊羅湖とも作る。
西北に知多半島の羽豆崎と相対して三河湾の海門、傍に岩石多く亦潮流の難あり常に舟人を苦しめるとか。
陸行して豊橋、田原、福江、堀切、伊良児の順に依れば、はや保美堀切のあたり、のうのうとし、冬日なれど暖かく陽光は燦々。たんぽぽの花開き、椿紅に小鳥唱ふ。
芭蕉はこの里をたたへて
梅つばき早咲ほめん保美の里
ものなべて南方の夢見ると思へばよし。
また保美はかの杜国がしのびてありけるを芭蕉が訪ひし里なけば清いと深く旅心とみにうるはふ。
ここ過ぎて堀切、伊良児、伊良湖崎へと二里が程の近さ伊良児の里は今在る処昔より稍南の海に近くへ移りしなり。ここはかくれたる歌人糟谷機丸の生没の地いまも尚その孫家を承け居れり。
このあたり仰げば天空晴朗、芭蕉の文にもみえたる鷹の名所。南海のはてにて鷹のはじめて渡るところといふ。
畠中の路、竹林の小径、紅椿のとんねる、しばらくにして、ああ、海見ゆ、伊良湖崎見ゆ、海波近く西南に神島のたたずまひ!
鷹一つ見つけてうれし伊良湖崎 芭蕉
(大正丙寅睦月)
竹垣
南面の
農家の軒先で
犬が大鼾
蘇鉄の蔭で小供が唱歌をうたふ
群道を乗合自働車が走つた
岐路(わかれじ)
竹と
紅き椿の里
一月といへど
麦のみどり
豆の花咲く畠中の路
行くは 右か 左か
浅春
伊良湖崎の手前二里いと安らかなる里あり保美といふ
竹林の小径
割木小橋
のうのうと働く耕牛の眼(まなこ)に
保美の里がかすんでみえる
砂山
てつぺんに
海鳥の足あと
まるまるとした砂山
こんなにやはらかそうに
寂しそうに
たれが盛りあげたのだらう
海よ お前の手あそび
風よ お前の道草
私もお前らと
ちいさい砂山をもりあげて遊ばう
流れ木
波の間と間に沈み
波の背に
流れ木よ
岩間に揚げられ
美しくむかれた素肌のまま
猶
潮騒を聴く流れ木よ
天南星
珍奇なる花あり実に以て花なり
有毒植物天南星科のひとつならんか
あたたかい浜づたひ
かたはらの密生した竹藪の小蔭に
天南星の花がみつかる
珍奇な肉穂花序
赤々 と珊瑚の艶玉をつづつたのは
人魚の忘れものではないのか
紅い椿の隧道
どこやらで
水を汲む気はひ
素晴らしい
濃い影を落す木下路は
紅い椿花(つばき)のとんねる
外では春の光が きら きら
団欒
漁村のまどゐは
やはり浜にてがおのづからならん
綿ネルの頬かむり
流れ木をひろい集めて
浜での焚火
海波とほく大洋の唱が
岬を頬笑みめぐる
なごやかな漁村のまどゐ
神嶋
伊良児の里は崎の手前
伊良児をこせば
見ゆ 見ゆ
空と岬と島
伊良湖崎の端にたてば
ああ 舞ふ鷹よ
波越えて神嶋へ翼をはりたい
危険信号柱
小山の木の間がくれに
陸軍着弾観測所の白い丸屋根
今日は危険信号柱の
赤旗もお休みだ
沖では汽船がひとつゆらゆらと鼻歌
渚へ下りた
海鳥の雛のひと群
そのうへを舞ひながら親鳥がながめてゐる
鷹
南方の空
岬の上
風を流して鷹が輪を描いてゐる
蘇鉄
異邦人のごとく
蘇鉄ただひとり寂しければ
攻められ
落ちぶれて
闇の夜そつと流れ出た
南洋土人の酋長
蘇鉄よ
せめてお前のこころにそう呼びかけよう
小魚
えんやら えんやらな
えんや えんや えんや
地引網が引揚げられた
網いつぱいの大漁
さわさわと躍る綱袋のなかで
小魚の酔ぱらひが勢ぞろひだ
10.夢のようなマリオネツテエ
パイプの火が消えました
明りが加減よくぼやけましたね
期うなると
お酒が寂しまれてさへくるようです
おいしい
コクテールをもう一盃いただきませう
そして しばらく換気してください
隅つこの小窓を開いて
あの月がお酒を吸ひでもするのか
カツプのなかが早く冷えます
ストオブヘコオルを増してはくれませんか
ああ あなたは
あなたは
斜にすこうし瞳をそらしてゐる
そう そして月をぢつと見てゐる
すこうし影つた小闇いところ
あすこが
ちいさいステージになりますよ
ふたつのマリオネツテエが現れます
お酒のなかから
わたしたちの
異様なかなしみが立ちのぼり
あの月のステージへ脱けてゆきます
ああ
夜のように住みよい夜
お酒だ お酒だ
月にみる夢のような少婦(あなた)のマリオネツテエ
11.秋の行人
ああ
秋の真なかを
ときもなく
をともなく
静静と歩いてゆく秋の行人
かれは
いづこから来て
いづこへと行かうとするのか
いとも身軽な旅のよそほひ
いとも長途のみちにあるかのように
はるばると
いつもはるばると歩かうとしてゐる
ぴたりと地に足をつけ
こくめいな刻みで歩いてゆく
あしたの水のように
透いた瞳を見ひらき
寂しげな流眄(ながしめ)をそそいでは
漂揺とて 急がぬもののようだ
旅で目醒め
旅でいねる大旅行家の面持ちで
はてしもない歩みを
しばらくも憩はせようとはしない
ああ
静かな
静かな秋の行人
私はかれをよび留めることができない
かれは聾者のように
私のよび声を聴きつけてはくれない
老人のいち途のように
閑閑とはしてゐるが
また さきを急ぐの一徹
あるときは背をかがめ面を伏せ
重い唱を口ずさみつつゆく
また あるときは
澄んだ空をうち仰ぎ
恍れ恍れと
虚空のどこかへ瞳を向ける
ああ
私はかれをよび留めることができない
私は
流れにある
ひとつの葦の葉の小舟に夢み
かれの自負寂しい歩みに揺ぶられながら
はるばると
いつもはるばると
はてしないものの方を向いてゐる
12.夜霧
夜霧が
都市(まち)にいつぱいたち籠めるころとなると
ほそい小路の暗所や
塵箱の蔭に
それはうらぶれた楽人の口すさみか
寥寥と
懐古のしらべをかなでるこほろぎの寂昔(さびね)
この夜霧のなかで
五彩のイルミネエシヨンがぼやけてしまひ
奇羅美たペエヴメント人が歩みをゆるめ
都市が細少(こまか)く
立体に刻み別けられてしまふではないか
灰いろの分離が行はれようとしてゐる
並樹の葉裏ゆすぶる晩秋の風
ころころ と都市をささやく木の葉
幻なペエヴメントの風と木の葉が
かへらぬ流浪のかなしみをつたへ
都市の奥処(おくが)の夜霧ぶかいなかへ走つてゆく
13.行軍
晩秋の疲労(つかれ)と湿潤の野源へ
ずんずんと歩兵の一隊がさし掛る
をりから雨季の空に
雲の移動があわただしいしたを
蜿蜒 とすすみくるカーキ色の一隊
黙然としてそれはいち様な列
手をふり
歩調をとるのがまるで機械のように
せいぜんとをなじ風にをなじ向へ
ある重さと圧力をましぐらに動かしてくる
むかふの山峡の黄ばんだ杜蔭から
豆科や桔梗料や施花科の
やさしい野の娘らが
逃げ失せた野はらへ
肅粛として押しだされる威圧の太い一線
私はいまさらのように晩秋の点景を眺める
ちぢみ草やあしぼりの
禾本科の草草を踏みながら
鋭い北風に落莫とした展望のまなかへ
玩具のように現はれてくるかれらを
その単調で執拗な一隊の働きが
小刻みに後方で揺れるとみると尾端
続いて杜蔭から
村童(むらこども)らが走りでた
弾み弾み
ぱらぱら とこぼれるように
みる限り疲労と湿潤の野原を
粛粛とすすむ歩兵の長蛇
おお
村童(むらこども)らもはれやかに足踏みし
晩秋の寂しさが
一列に微笑み行軍する
14.化猫
蹲る
とよりとした快眠の猫
やはらかい情痴の触りを夢み
なにといふ昼の寝姿になまめいてゐるのか
やがて夜
それは思春をよばはる屋根上の曲者
ふるい伝説の埃重く
しめつぽい猫の足跡がのこる
赤茶けた日本紙の乾く匂ひ
油煙のほてりに
あの黒一色の影絵の幻妙さ
行燈を覗ふ執念のいきものを
おお 冬
私は炭火を囲ふたびにおぢける
煤びた藺畳の
黒い麻布でへりとつた部屋には
すかし彫の欄間のかげから風が流れる
冬は部屋もうす暗く
屏風をめぐらすにさへ気味の悪さをいとふ
そこにあの幻燈絵を現はす
夕陽にあかい丸窓障子の奇怪な幻影
北風に吹晒される樹樹が騒ぎ
さむ気だつ障子の裂目がうなるころ
私は火桶を抱きながら
隣家の猫をひそかに待まうける
15.蒼白い体
たそがる深山の
白樺の幹が思ひ出される蒼白さ
生毛の感触が粗いタツチでふれてくる
おまへには
いつも
冷たい体温がうづいてゐるようだ
あの冷える夜をいとふ
パンジー
三色菫よりも
痛痛しい神経をふるはせ
しほれ果ててゆく蒼白い体を
抱きしめることが
私には
あく夢をみるよりもうつくしい
そして
おまへは
なにといふたえがたさを
はにかみ草の愁ひのように
寂しい沈黙の姿態にゆだねるのか
なによりも
なによりも
それはみ事なけだものの魂
息をもつがさぬ蒼白い体
虫喰ふ茅膏草(いしもち)の妖しい食欲のように
いつも物の気のちかづくを感じて
おまへは
美しい蒼白い生もののいのち
息絶え 絶え
つひに
私に抱きしめられてゐる
16.落葉
おお 落葉 落葉
落葉は
ときを得た寂しさのひとひらか
落葉は散る花のたぐひ
日がな一日
おお 落葉 落葉
雑木の林の
とんねる小道
落葉の小道で
風吹けば からから
風吹けば からから
蜘珠の巣にかかる落葉も
ただ からから
からからと鳴る
おお 落葉 落葉
落葉は涙
かへらぬ哀別のかなしみ
落葉はとまらぬ涙のしづく
日がな一日
おお 落葉 落葉
百舌が啼き
太陽(ひ)が傾ぶく
材の少年(こども)の草笛小唱に
雑木の林で
夕陽のなかで
ただ さめざめ
さめざめと落葉する
おお 落葉 落葉 落葉
空は澄み
太陽(ひ)は落ちる
風は北だ
日がな一日
雑木の林
落葉の小道で
おお 落葉
ゆけば
荻の小花は ほろろ
露も ほろろ
親しげに音たてて
肩うつは樫の実
あはれ
これもまた寂しき落葉のたぐひか
17.路上の六花
この雪降る深夜
都市(まち)の熟睡(うまい)をそつと押し分けよう
さくさく
さくさく と雪を踏みながら
郁市を蔽ふ奇怪なドームのなかで
寒い
寒い季節の祭礼(まつり)がはじまらうとならば
私は純(ま)白い六花の霏霏たるを浴びよう
出でて
花にまみれ
閉ざされて
踏みながら踏みゆかう
雪の渓谷(たにま)
それは
人里遠いなにといふなめらかな谷底であらう
やぶれ傘は柳のお化け
街路燈は雪をかむつてひとつ目小僧
あの独犬のイルミネーシヨン
そして
うへでの山婆の白元結ひ
電線がしごかれるたびに白いと見ようか
私は
これら
奇妙な仮装者にむかへられ
静かな群のひとりとならう
この雪降る深夜
寒い季節の祭礼が始まらうとならば
さくさく
さくさく と
路上の六花を踏みながら
都市(まち)の熟睡(うまい)をそつと押し分けよう
ただ
私は純(ま)白い六花の霏霏たるを浴びよう
18.売られゆく仔犬
可愛そうな子の犬にはまだ呼名がない
かあいそうなこの犬は盲目(めしひ)
そして牝に生れてきた
たれがよびはじめたのか
「横ちやん」と言はれれば其方へ走つてゆく
それはひどく頭をかしげて歩くから
かあいそうにも横ちやん
横ちやんの眼は白い膜で蔽はれて見えない
横ちやんは
だからまだ見るといふことを知つてはゐない
別の世界にゐるようなものだ
それが
よけいにあどけなく憐れに思はれてならない
をまけに牝に生れてきた
だから
犬屋に売られてゆくといふ横ちやんだ
「眼ぐらひ
これで難渋はない
仔出しさへよかつたらこれで申分はない」と
犬屋は犬屋だけのことしか言はない
横ちやんが売られてゆく朝は寒かつた
犬屋に抱かれて
クンクン と泣きながら
横ちやんは
白い膜のかかつた眼で
ぢつとこららを見まもつてゐた
かあいそうに横ちやんは
盲目の世界のそとが
ほんとうに見たそうであつた
深刻な全身の表情が
まるで燃える瞳のようであつた
19.街裏の犬
こないだ街で
おまへが
うしろ脚の右を
びつこして
私とすれ違ひに歩いてゆつたのを
私はふりかへり見をくつてゐた
捨てられたのか
それともはぐれたのか
そのどちらでもない風態は
いかにもして
私に忘れ難い
そのとき私は
思はず「おまへ街裏の犬」とよびかけた
街裏から街裏へ
街から
街ヘと
おまへはよろめいてゆく
そして
おまへは貧しい食欲が
どこにしつらへてあるかを
たのしそうに
もとめてあるく
ところが今日
この街裏の広い空地を
おまへは瘠せ
泥にまみれながら
しかし
愉快そうに
草中を歩いてくるではないか
ながながと
背伸びをし
首さしのべ
大空を仰ぐではないか
よろよろと
びつこして
草中を
おまへは
をなもみの果実(み)に飾られ
私とすれ違ひ
歩いてゆくではないか
おお 街裏の犬
街のボロ犬
けふはまた
けふはまた
おまへの何たるはれやかな
散歩姿だ
20.ジヨル男爵のころ
いつにこの風態
また荒んだ過去によつてでか
現に迫害されどをしの今が呪はしい
たまらない飢餓
激しい性欲
そして雨露の睡眠と
注意ぶかい歩行
滅茶滅茶な生命が暗く暗く続いてゆく
ひとに呼ばれたことがない
自分に呼名が無いことすら知らない
逃げるといふことを覚え
吠えるといふことの不利なことを知つた
噛みつくことは
ひとに教はつて知つてはゐた
しかしこのごろ
考へることが段々と多くなつてゆくようだ
身体(からだ)にも精神(こころ)にも
恐ろしい程ゆるみを感じ
思ひ出にこころを
放してやる楽しみのなかから
ふと自分の呼名を見つけ出した
たれかが呼んでゐるようにさへ思へてくる
そのころの夢が
狂ほしいまでになつかしくよみがへつてくる
「ジヨル男爵」
そして次の瞬間
この哀れな零落をいち期(ご)に
ジヨル男爵は一撃を喰つてゐた
ひとびとは
このみすぼらしいなれの果てを
ただの野犬としか思はなかつた
そして
かれの幸福な横死をすら
さも
憎々しいといふ風にして見まもつてゐた
21.引車
まめまめしいおまへの労働
おまへは牛馬のように
四脚で路上を引車するように馴らされる忠僕
荷車の下の仔犬よ
よちよち と
まだ三ヶ月の危ふげな足どりさへ
もう
ぴつたりと地についてゆく
私はいぢらしいおまへを
たまらなく微笑で見おくる
22.憂鬱と犬
月光は
瓦屋根の
ひしひしと折重なつた街を
ある角度の調和に
光と闇を形染めにする
そのどれも黒い地質の
晃らかな
蒼白い更紗模様のなかを
一疋の犬がだまつて
この地味な憂鬱を
向ふから動かしてくる
23.ヨシの体験
街から街へ
ひこからひとへ
いまや街のすべてをあげて
いまやひとびとの心のすべてを捕へ
恐怖の幻影がかげさしてゐる
またも
赤や青のビラ撒かれてゆつた
ひとびとはあはただしく
「狂犬予防週間」のなかへ逃げこんだ
恐ろしい
荒びきつた
獰猛な野犬の影を
ひとびとは描いてみなければならなかつた
犬 犬
犬さへ見れば
檻を破つて出た
猛獣よりも怖いものでなくてはならなかつた
またも
赤や青のビラ撒かれてゆく
犬とみれば
ひとびとは逃げ
小供も泣き止んだ
犬といふ犬は
みな野犬でなくてはをさまらない
それでも
「ヨシ」は
不思議に助かつてゐた
傷だらけな体
形相は変り
「ヨシ」は呪はしい体験のひとつをふやし
またもこの街へ
ひとびとに
いみきらはれるボロ犬の姿を現してきた
跋文
中山伸
前に一帯の雑木林を見下し、その向ふの松林を越えて遥かな山脈に対ふ、静かな明るい南面の丘。それは桐林と桑畑と松林にかこまれて、ぽつつりと建つ丘上の一軒家、君の愛する山荘。
去年の夏もこの詩集の稿を、携えて、君が数日の独居をたのしむだ山荘。君を語り、君の詩を語るに離しがたい経歴をもつ、丘の上の一軒家だ。
七八年前の冬、この山荘での幾日の後、君が持ちかへつた数篇の詩のなかに、かういふのがあつた。
煙
黙りこくつてどんどんと
かれ枝を焚火の中へ投げこんだ、
よく拭はれた空だ、
人里はなれひとり私が住む
澄むだ空気の丘の上に、
黙りこくつてする焚火。
太陽は潤つた大地を蒸し
陽炎があがる、
焚火はぱしんぱしんと
小気味よい音をたてて、
たちあがる白い煙は
うへの方で消える、
それでも元気よく昇る煙。
今でも時折り、山荘に在る君からの便りを手にすると、いつもこの詩を思ひ出す。そして、あの丘の上、樹間に立ち昇る一條の煙りを思ふ。 これこそは君の真面目、
侮りない君自身なのだ。
君の愛するあのあたりの松原、ふかい雑木林、小石を洗ふ小川などは、私も屡訪れたものだ。 かつては隔意ない友数人と共に、旬日にわたつて滞在したこともあつた。
夜天の下、一基の蝋燭をかこむで茶を啜り、談笑し、黎明、露を浴びて雑木林の奥深く歩き廻る、あの気侭な幾日を、今もたのしく思ひ出す。
近年、君と共にあの静かなる丘を訪れる機をもたない私であるが、いつも君をおもへば、あの丘陵地帯の木下路を、マドロスパイプを啣へながら、黙々と歩き廻つてゐる君の姿を目に浮かべる。
いつのころか
私は松林のロマンチストである
私は松林の瞑想者である
素影千里の秋の夜
梢の露に身を濡す静観の道者である
或ひは転身の神でもある
悲恋の楽手でもある
芳叢の蝶でもある
─「松林に行吟するもの」の一節─
六七年前の作、いささか美辞めいてはゐるが、君の君らしさが髣髴としてゐていい。君は実にひとりをたのしむ。いかなる環境のもとにあつても、
君は君みづからの世界を失はない。その世界の中の君は常に瞑想者であり静観の道者である。そして、それ故にさびしいロマンチスト!そうだ。おそらく君は、
これら山荘の詩をもつて裕に一巻の詩集を編み得るだらう。おそらくそれは、あの丘の上にたちのぼる煙りのやうに、君の面目をあやまりなく示し、昨日から今日への君の歩みを、
最も明確に描きだすものであらう。この詩集の中には、それら古い、しかし私にはなつかしい幾篇のよき詩を、見出し得ないのを惜しく思ふ。
「行軍」「落葉」など、比較的近作である詩篇をもつて私は我慢せねばならない。
君は元来寡黙、時によく対座する者の舌を奪ふ多弁家であるが、それは稀だ。いつも君はよく考へ、そして行ふ。信じたことはどこまでも仕遂げずに置かない。 気迷れと感情的言動は君の最も嫌ふこころ。線が太い!一部の人に傲慢の感を与へてゐるのは、この不羈な意志と、寡黙の所由であらう。
ウエヴスター大辞典、本屋の看板にしたいあの尨大な辞典が、遠来の偉容を君の書斎に現はしたのは、おりバイロン熱が最も熾烈な頃であつた。 それ迄屡「曼珠紗華」誌上にバイロンの詩論や評伝を発表してゐた君が、いよいよ長篇「カイン」に訳筆を染め初めたのも、その頃であつたらう。 あの大辞典は、それがどれだけ君に有用であつたかと云ふことよりも、あの頃の気味の意気込みを髣髴させる恰好のものだ。君とバイロンとウエヴスター大辞典……。 あれはたしか、バイロン百年祭にさきだつ数年、世上にまだその名を聞かない頃であつた。
君の詩に就いては、私がここで讃するよりも、この詩集を手にする人々に問ふことにしよう。所謂多感の詩、或は靄がかる情緒の詩は君に求むべきものでない。 ここには圧縮された感情が、床下を匍ふ火のやうに、あるひは地熱のやうに詩の面を熱つく熱つくしてゐるが、決してそれは、目にみえて炎々たる焔ではない。 風に狂ふ焔ではない。みづからは石の如く、しかも熱火を蔵するもののやうに、君の詩は深く、そして熱い。
私は今、君に就いて書きたいその十分一も、ここでは尽せない。しかしながら、おそらくこの詩集は、他の人々に依つて、より多くより深く価値づけられるであらう。 「願はくば影ふかき手に開かれよ。」私が自分の詩集に願つたやうに、しかしこころあらたに私はこの詩集のために祈る。
伴野君、君の第一詩集「街の犬」も、いよいよ書斎から街へ出る。私は非常にうれしい。出すなればいつしよに出したいと云つた少年の頃の希望がそのままここに実現されるのだ。 君の最近の傾向に就いて、私はいささかも記すところなく、殊に犬に関する詩篇に於いて、人々はこれを了知するだらう。
ところが今日
この街裏の広い空地を
おまへは瘠せ
泥にまみれながら
しかし
愉快そうに
草中を歩いてくるではないか
ながながと
背伸びをし
首さしのべ
大空を仰ぐではないか
よろよろと
びつこして
草中を
おまへは
をなもみの果実に飾られ
私とすれ違ひ
歩いてゆくではないか
そうだ、おなもみの果実(み)に飾られ、をなもみの果実に飾られ、君の街裏の犬は、やがて再び、昂然と私達の前へやつて来るであらう。
附記
星移十歳、いまこそ私は、それら古りたるもののなかより、襟を正して自らの第一詩集のために、詩三十五篇を挙げて寂しい微笑とせねばならない。
これこそは、私に優曇華の開花か。つひにあらうとも思はれず断念の闇ふかく葬つたこのことが、現にいまのものたらうとは、
むしろ自らを訝りのこころで眺める私の心情をよけいかなしいものにする。なぜなら、なみならぬ私の怠惰なる性情に、これはまた何たるの決意か。私には、それが寂しい。
さきに私は、したしき友等と感動詩社を起して、大正八年詩歌雑誌「曼珠紗華」を世に出して以来、
「独立詩文学」「先鋒」「風と家と岬」「清火天」そして現在の「新生」に至るの歩みのなかからの、三十五篇。このうち発表したものは三十二篇であつて、
餘の十三篇は挨の裡、あやうく煙滅に終らんとしたものによつてひろひ集めたもの、
即ち「こよい晩餐の卓」「五月の草笛」「寝息やすらかに」「刻まない時計」「秋の行人」「化猫」「落葉」ならびに「売られゆく仔犬」以下の五篇がそれである。
みな、大正十二年以後の作品ばかりで、それ以前の作品は、多く青春の夢ふくいくたるもののたぐひで、凡て懐かしく愛惜のものではあるが、今に到つてはむしろ涙と共に放棄するに餘儀ない。
昨日の花、昨日の花束を飾る心尽しのリボン ─装幀─ は、どうにも自らの手を煩したく、かなりな労苦をも、いとひなく甘んじた結果、
私の思ふものを完全に近いまでに出すことができた。ただこれが全部名古屋での仕事であるがため、不馴れがもたらす仕事の手際にいかんの点あるは痛恨のいたりである。
私は、いましたしき円陣をめぐらす友情を周囲に感する。友等の熱き愛情の前に、新しく私は感謝限りないこころを捧げなければならない。
この「街の犬」はさらなり。さらに、遥けき明日のいとなみを約して、静かに「有難う」といはねばならない。
昭和二年三月二日
宵雛の部屋にて
著 者
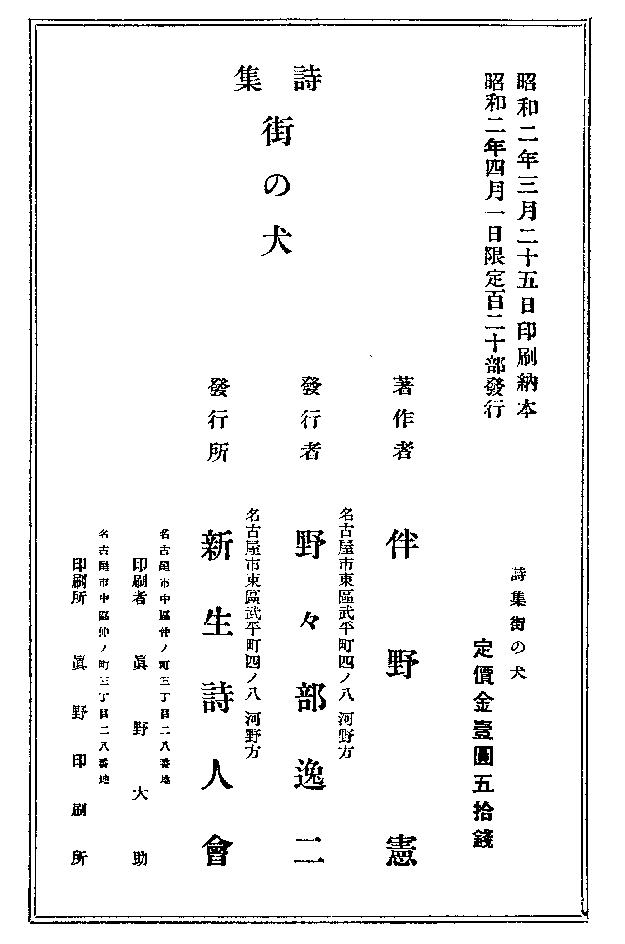
奥付
本詩集のテキストをことわりなく転載することを禁じます
凡例
表記は仮名遣ひの不統一などすべて原本に従った。ルビは( )内に、また表示上該当漢字がないものも( )に読みを記すにとどめた。(追って改良します)。
新漢字のあるもの、明らかな誤植はこれを改めた。詩篇には頁の代はりに番号を新たに付した。(編者識)
コメント:
四季派の外縁を散歩する「名古屋の詩人達 その1」
Memorandum :詩集「街の犬」について
詩誌『新生』昭和2年5月号 :詩集「街の犬」を読む(鵜飼選吉、棚木一良) 「街の犬」出版記念会 2007.2.23update
ばんの けん【伴野憲】(1902〜1992)