
詩集 北の窓
中山 伸 第一詩集
大正15年11月10日 新生詩人會(名古屋)刊
23.3cm×16.6cm 130p 上製箱入 \1.50
著者自装 限定150部


(2002.11.25up / 2022.07.06update)
Back
なかやま しん【中山伸】『北の窓』1926【全文テキスト】
序詩
私はいま これらの詩篇を君におくる
これは私の昨日のうただ
すぎし日の私の生だ 夢だ
ともかくも今に到つた私が
人生の小径の上におとしてきた私の影だ
しかしながら 私は君に告げねばならない
昨日のうたは今日のうたではない と
今日のうた
それはつねに私の心のなかにある
そして それは永遠に私自身の 私自身の秘密である。
私はいま 私とともに住みふるした
この北の窓の樹々をながめる
(それは昨日の樹々ではない 吹く風もまた昨日の風ではない)
そうだ それは昨日の樹々ではない それは昨日の風ではない
現在──それは樹々みづから風みづからの秘密である
それは種子のごとく嬰児のごとく
それみづからの新生であり 出発であり
又結実であり 継続である一点である
それはつねに新らしき私のうたの材題(テーマ)であり 私自身の秘密である
私はしづかにあをい空をみる
屋根と樹と 軒端にはばまれたあをい空を
それは昨日の空である
(それは昨日の空ではない)
そうだ それは今日の輝きにみち
そこには昨日の雲影はない!
私はいま これらの詩篇を君におくる
それは樹々のごとく空のごとく
それみづからの捕捉しがたい現在に生き
それみづからの現在の影と 現在の幻想を持つてゐよう
ああ しかもそれらは昨日のうただ
今日のうた 現在のうた
それは 永遠に私みづから知り得ざる 私自身の秘密である
目次
序詩
1 .時代錯誤の花
2 .異邦人のごとく
3 .見馴れない顔
4 .月の出
5 .かなしき擬容劇
6 .落葉
7 .春の夜
8 .めざめ
9 .夜明けの雨
10.窓に咲く花
Ⅰ窓の花
Ⅱ一日の窓
Ⅲ風
11.谷間の道
12.口笛を吹く
13.冬の日
14.保美の里
15.空中楼閣(或ひは、惨めな都市人の夢)
16.白鳩
17.忘却の恍惚
18.かなしき秋
19.ダリア
20.秘められた庭園の小径
21.雨の日の窓
22.孤独の殿堂守
23.文字
24.扉
25.飛行機
26.心像を刻みゆく
北の窓 Ⅰ─Ⅵ
跋(伴野 憲)
(附記)
【拾遺】彼
装幀 著者
北の窓
1.
時代錯誤の花
───紫陽花のありあ──
しづかに しづかに君よ
この花を北の窓に置きたまへ
こころすさみ こころ堕ちたる吾等の胸に
この花のおくるさびしき匂ひを置きたまへ
この花のいろと この花のすがたと……
君はかなしくこの花にゆく蜜蜂
君はそのうれはしい羽音を聴くであらう
さびしき日は
この花を胸にかざりたまへ
遠く忘れた吾等の夢の
そのいろと その匂ひと そのすがたを
君は夕暮れのうれひのごとく思ひ出づるであらう
かなしき日は
この花を君の頭(かうべ)にかざりたまへ
吾等のたましひの直ぐなる驕りを
君は古き物語りの王女のごとく
ほほえみのうちに思ひ出づるであらう
ああ 月光のごとく匂ふ花
驕りたかいたましひのごとく驕れる花
そして 吾等のいのちの古き夢のごとくいろあせし花
君はここに
花々のさびしき歌調(ありあ)を聴くであらう
君はここに
吾等の思想のかなしき時代錯誤(あなくろにずむ)を知るであらう
この花のむくろは 君手づから
あをい月光のうちに葬りたまへ
2.
異邦人のごとく
ぼくはかの あをいがうんに身をつつむ
異邦人のごとくあゆまふ
手には花
口にかむ太巻きのしがあのけむりに
くろぐろと巷に夜の霧をよび
ぼくはかの あをい額を霧に洗ふ
異邦人のごとくあゆまふ
ぼくはかの 水のごとき永遠の思想と
空のごとき久遠の郷愁を胸にたたへて
ちまたちまたをたちこめる夜霧から生れ
風のごとく彷徨ひ 行きすぎるもの
かのあをい瞳(め)とあかき唇と
また 灰色の髪ながき異邦人のごとくあゆまふ
今宵 都にふかく夜霧たちこめ
ふかぶかと流るる風は水のやうにつめたい
街燈の光り すぎゆく行人の背を濡らし
空には消えてゆく広告燈のふるびたれ幻想……
ぼくはかの いろ哀しきりきゆーる
哀哭の涙をここにもとめない
またぼくは はなやかな休憩室
かの倦怠をうづむる長椅子をもとめない
ああ 願はくば夜風のごとく霧をわたり
夜風のごとくこころなき愁ひをたたへ
閉ざされた窓々 ちまたちまたを
無言のままに行きすぎる旅人──
手には花
あをじろい額を霧に洗ふ
異邦人のごとくぼくはあゆまふ!
3.
見馴れない顔
だあれもゐはしないが
さびしくもない
見馴れない部屋ではあるが
べつだん不思議にもおもはれない
“もう夜明けなのかしら
硝子障子がほんのりしろんでゐる
“ぼくに未来があるだらうか
計画(プラン)のない未来といふものがあるだらうか
考へることがそれが未来にすぎないのではないか
そんなことが泡のやうに意識のおもに明滅する
“ぼくに過去があるだらうか
思ひ出のない過去といふものがあるだらうか
記憶 ただそのなかにある空気のやうなしろぼけた埃のやうなもの
それが過去といふものではないのか
ぼくのかたへに眠つてゐる見知らない女性の顔に
とほいとほい視覚を呼びあつめながら ぼくはつぶやく
“現在だつてつまりはそうなんだ
過去も未来もない現在といふ考へが
闇に花咲く白い大きな芙蓉の花のやうに
ぼくの気分をすこしく明るくする
“現在だつてつまりはそうなんだ
わびしい疲れはてた孤独の霊といつしよに
かうしてぼくは寝てゐるんだ
いつまでも寝てゐるんだ
思ひ出もなく計画もない夢のやうな現在
だからこの現在は永遠であつて 又絶対なのではないだらうか
疲れはてた霊よ
闇に花咲く白い大きな芙蓉の花のやうな
お前の顔は ぼくの心を蜜蜂のやうに包んでゆらゆらゆれる
ああ ゆらゆらといつまでもゆれてゐるよ ぼくはねがふ
人生の忘れられた片蔭を吹きゆく風に!
4.
月の出
空ばかしみてゐるとかなしくなる
夜明けだか日暮れだかわからなくなる
夢のやうなひとひら雲が(ああ遠き愛人の頬のやうな!)
いつのまにかちぎれてしまつて
しろじろと流れてゆく
空ばかしみてゐると
ふわふわと吹いてくる夜風も
妹のやうに可憐に
やさしく ものとひたげに吹いてゆく
いつとなく空が明るんできて
星達が羞づかしさうに消えてゆく……
たれだ この秘密の神殿に近づくものは?
至純な闇を隙見するものは?
空はまひるのやうに照らしだされた
聖なる庭のやうにうつくしい
白衣の懺悔僧のやうにしづしづと
祭壇にちかづく犠牲(いけにえ)の処女(おとめ)のやうに影もなく
光りのかたへすべつてゆくひとひらの雲
ああ 月の出!
団々と金色の月がのぼる!
子供らがとほくで歌ひだした
風が歌のふしぶしをのせて
東の方へ走つてゆく
練兵場の砂地にねころんでゐる私の
両足(あし)のあひだからいつのまにかすべり出た月
聖なる庭をひとりわたる
聖母マリアのやうなこころになつて
ながめてゐると いつか
たかくたかく月は中天にのぼつてしまつた
そして かうかうと私の胸のかなしみを照らす
私の足からすべり出た月
月は私を忘れない!
誰しらぬここの砂地にねころんで
いつまでもかうしてぢつとしてゐる私を!
私の涙にくもるあつい胸を
月はかなしげに照らす!
5.
かなしき擬容劇(みいむ)
うつうつと岸打つ波が
汀の枯蘆をゆすぶつてゐる
灰汁のやうに濁つた水のいろ
潟いちめんにうすびかる水のいろ
ああ 魚麟のやうに波が起き伏しする
窓 窓は今朝もにごつた水と
雪もよひの空を透してがたがたふるへてゐる
──今朝早く彼等は私を呼んだ
ぐつすりと眠つてゐる私を呼び起した
私は夜着をとほる寒さにふるへて立つてゐた
何故彼等は朝はやくから私を起したのだらう
唖のやうな彼等の身振りは
何を悟れと私に云ふのであらう
ああ うれはしい無為の仕草を繰りかへし繰りかへす
お前等のみいむの意を私は解くべきか
それどもお前等かなしき無生物の
無意の仕草をみてゐよといふのか
うつうつと岸打つ波が
汀の枯蘆をゆすぶつてゐる
潟いちめんに魚麟のやうな
灰色の波の起き伏し……
──片山津にて──
6.
落葉
空にはもう夕焼けの残映(なごり)もあせて
幽か 薄の穂のやうな月がかかり
夕風は暗く吹きあれて
たかく 白楊の梢に平安の夢をかみ裂いてゐる
ぼくがゆく公園裏の小径の上に
ちりかかる無数の落葉
ながいたかい板塀を越えて落ち散る木の葉
ここに晩秋のうれひを衣(かさ)ね
ぼくは暮れてゆく今日の日影をみつめて立つのです
ああ さむざむと身に迫る木枯の音
つめたく指をかすめて散りゆく木の葉
心はいつかふりつもる落葉の下に病み
ぼくの想ひはいたづらに朽葉の髄をかむのです
木枯よ 旅人の旅路を奪ふ吹雪のやうに
ぼくのためには かつてあゆんだ
すべての道々を落葉でうづめ
朽ちてゆくこの生命の病ひ葉を
ひと葉のこらず吹き落とせ!
ああ 木枯よ されば一夜の窓に
ぼくはお前のうたをなつかしく聴かう
とびちる落葉のなか 幽暗の路上を
たましひの痛みにふるへて歩ゆみながら
遠く動物園の山羊のなくをぼくはきいた
7.
春の夜
蛙のないてゐるのが 今夜は
とほくからきこえてくる
いかにも泥くさい なつかしい声だ
耳かたむけてゐると
風が
もちの木の葉をちらしていつた
蛙の声がきこえてくる
ほんとうに田舎びた郷土的な声だ
いざなふやうな 呼びかけるやうな声だ
立ちあがつて
縁側から空を仰ぐと
星がいつぱい光つてゐる
銀砂をまいたやうな といふ
古い言葉が身にしみて思ひ出される
ああ 蛙の声!
なんといふ古い血の秘密がこもつてゐるのだらう!
それは 思ひ出せない血縁の声だ!
泣いてゐるのか 訴へてゐるのか
歌はないではゐられないのか
あの声のする方に
ほんとうの故郷があるやうにおもはれる
その声は
とほいとほいとても行けない程はるかな彼方のやうにも思はれる
そして いつかあつたかい涙が瞼にたまる
8.
めざめ
お前がそのながいまつげを伏せたとき
私はお前のきよい泪を感じた
ひややかにひとり燃えしきる
あの不滅の火影を
つひにお前はみとめたのだ
そのとき私は
しろい貝殻のやうなお前のまぶたに
しづかにかぎりなき愛隣の唇をふれた
お前がその渇きはてた唇を
ぶるぶるとふるはせたとき
私はお前の見失つた言葉を感じた
それは私への言葉ではなく
それはまた誰にかたらうとした言葉でもない
ああ それはただ彼と私のみ知つてゐる
彼──けむりのやうに二人の間をすりぬけて
風のやうに消え去つた彼と私と……
やがて思ひ出したやうに 私は
冷えきつた小さなお前の手をとり
かすかなお前の微笑にこたへたのだ
9.
夜明けの雨
雨にたわむ南天の葉
風吹けば 風にゆれ 風にゆれ
ぱらぱらと雫をおとす 光る雫を……
そのしづくかげ しののめのうすらあかりに
三つ咲いたどくだみの花
しろい ちいさな薬草の四弁の花
ああ 夜明けの雨はしづか
眠りたらぬ目にはかなしい庭の風情!
濡れて吹く朝風のなかに
ひとり 恋人をおもふ
10.
窓に咲く花
Ⅰ 窓の花
窓際の
くれなゐの一輪の花
その花の名を私は知らない
窓は五月のあをぞらに展け
カーテンは南風をはらむで白帆のやうだ
おお くれなゐの一輪の花!
その花の名を私は知らない
ただ 静謐な中世紀のひるの青海を
ツルバドールの夢を!
Ⅱ 一日の窓
威勢よくりんを鳴らして
朝がとほる──この窓下を
ものうげに喇叭を吹いて
ひるがとほる
やがて
おもく沈んだ足音とともに
夕べがとほる
窓に置かれた可憐の花
一日の無言の傍観者よ
お前の運命はじつにしづかだ
お前はよき忍従を知つてゐる
Ⅲ 風
あをい窓の
しぼめる五月の花を
吹きちらすみなみの風
風よ
私はお前を讃歎する!
ああ かくもひとり
かくもしづけく
かくも無心に
花にうつらふ
いのちさびたる殉情よ!
11.
谷間の道
山と山とのせまい谷間を
ひとすぢの道が通つてゐる
うねりくねりの白い静かな道だ
前後左右に立ちせまる山々のいただきから
なだれ落ちた青葉にのまれ青葉に埋れて
この道はどこまでも続いてゐる
行けば行くほど山々は深く
陽光(ひかり)はいよいよに晃らか
しんしんたる深山のしじまの中に
青葉に溺れた山鶯が啼いてゐる
山と山とのせまい谷間のひとすぢの道
青葉にかくれ陽にあらはれ
うねりくねつてどこまでもつづくひどすぢの道
白い道 しづかな美しい道
もう幾時間歩きつづけたことだらう
ひとひとり逢はず 人家ひとつみえず
前にも後ろにもそびえ立つ青葉の山々
浪のやうに押しよせた左右の山々
やがて僕も青葉に溺れてしまふのか
けれど この静かな道は
すこやかに 美しく
青葉を潜り 山をめぐり
どこまでも どこまでもつづいてゐる
ああ 何といふロマンチックな道であらう
怒涛のやうになだれ落ちた青葉に溺れんとして
しかも冷静な美しい道
晃らかな道
僕はひとり
散歩杖を打ち振り打ち振り
この谷間の道を歩いてゆく
12.
口笛を吹く
水脈(みお)のやうに しろく ながく
金色(こんじき)の野面(のづら)をはしる細道で
たかだかと私は口笛を吹く
地平をめぐる藍色の山脈に
私はどんな言葉で語ればいいのか
口笛を吹く!
少年のやうに ながく忘れてゐた口笛を吹く!
かなた村里のあたりから呼ぶ百舌の声に
応へるため つたないかすれた口笛を吹く!
ああ 野路は はるか
垂穂をわたる風は はるか
ああ 麗日よ 私の額に燃えよ!
青空よ 私のこころを染めよ!
ああ 流れゆく風よ もぢやくれた私の髪を梳け!
鳴れよ 口笛!
秋冷の虚空をつらぬき
高く 高く 高く 碧空に沁みゆけ!
ああ 閑寂な十月の野に立つて
私は悲願の口笛を吹く!
13.
冬の日
枯葉いろの冬の日が
けふも暮れようとする
わすれられた公園の池では
樹かげをなくしたスワンのむれがなく
おもはずも見上げた空に
病院の煙突の
茶いろのけむりがひとすぢ……
おお スワンよ!
お前らもまた堕ちたる霊魂がかなしいか
14.
保美の里
保美(ほび)の里は
風ふきすさぶ十丁の刈田のあなた
こだかくしげる竹薮の中に……
みあぐるさむぞらには
鷹が二羽三羽舞つてゐる
ああ 芭蕉よ
ぼくもまた里人に道をたづね
小手をかざして
しづかに思ひ入るげなその里のあたり
落莫たる冬のいろをながめる
15.
空中楼閣
──或ひは、惨めな都市人の夢──
その日、幾年の風雨に汚れた葦簾(よしず)の幕が、すつぱり取りのけられた。つひにその日が来たのだ!
高層尨大な白面のビルデイングの素顔は、揚々として五月の中央街路の一角、みなぎる陽光の中に立ち現
はれた。幾十万の都市人の、一切の希望と期待を一身に集めて。そうだ、幾千日、幾万人のかくれた努力の
結晶はこれだ!みたまえ!一階、二階、三階、…五階、七階、八階、八層閣だ!堂々たるものぢやないか。
雄大なものぢやないか。 さすがに黄金の力ぢやないか!
人々は立止り、人々人は仰ぎ、群集は去り群集は押しよせた。「何階だつて?」この言葉は幾千度繰り返さ
れたことだらう。「何階だつて?」「何階だつて?」……
しかし乍ら、読者諸君。無数の仰ぎみる人々の顔に、ひそかに立ち迷ふ失望と倦怠の表情に気付かなかつ
たか?集ひ来る人々の跫音と、立ち去る人々の跫音に、何か違つたものがありはしなかつたか?何故だらう?
僕も亦群集に交つて、群集とともに立ち去り乍ら、この暗い影のことに就いて思ひ耽つた。
やがて僕は、とあるカフエーに疲れた身体を憩め乍ら、友に消息書いた“それはかうなんだ。あの建物が起
工されない頃、古ぼけた見苦しい家々の前に、立派な板囲ひが張りめぐらされた。間もなく古い建物は取り毀
ち、運び出された。その頃から既にその頃から、この中央街路を行き交ふ群集の心裡には、完全な、荘大な
空中楼閣が描き出され、組み立てられてゐたのだ。
やがて仕事が初つた。幾十台の荷馬車は、連日土を運び出した。“地下室なんだ!“──人々は心に叫んだ。
赤い樹が立つた。コンクリートが流れ初めた。そうして数ケ月たつた。鉄筋と砂利とバラスと、それらは何処
からとなく無限に運び込まれた。工夫は毎朝幾十人となく、その板囲ひの中に消えた。……数ケ月たつた。
コンクリートが中空に流れ始めた。建物は地階の仕事を終つた。二階……三階……その年の夏も去つた。
酷熱と干天の夏も去つた。秋も……それらは何処からとなく無限に運び込まれた。工夫は毎朝幾十人となく、
その板囲ひの中に消えた。葦簾囲ひが、高く高く高く張りめぐらされていつた。コンクリートが行人の頭上をお
びやかし、人夫の声がそれに交つて聞こえた。
中央街路を行き交ふ人々、朝夕の幾千人幾万人。──月日は移つた。街路樹の柳は芽ぶき、また落葉した。
彼等の或る者は死んだ。或る者は妻を持ち、或る者は職を解雇され、或る者は昇給した。しかも、これら流
転の行人の目は、常にこの街角にそびえてゆく新建築を仰いだ。 その顔には、誇りと感歎と期待とが溢れ
てゐた。そして、彼等の心はいちやうに叫んだ。「もつと、もつと、もつと、高く高く!」
友よ、君は不思議に思ふかも知れない。けれど、事実私はかういふことをたしかめた、自己表現の、すべ
ての道を失つてゐるみじめな都市人の、──彼等の殆どは、ダンテの「希望を捨てよ、汝等、此処へ入り来
るすべての者は!」といふ標札のかけられた門を潜る者だ。 モオパツサンの云ふ「彼が此処へ来た日に、
美くしい口髭の生えた若者としての姿を写した、その同じ小さな鏡で、免職された日の、頭の禿げた、白髭
になった自分の姿をつくづくと眺めてゐる……」ところの者だ──唯一の表現が此処にかけられてゐる。彼
等の生活、彼等の家庭、彼等の仕事、それらすべては、既に既に自由なる想像、自由なる表現を彼等から
奪ひ去つた!何も残つてゐない。束縛と、鋼鉄のやうな範疇を除いては……そうだ、ここに唯一の表現の吐
き口が出来たのだ、ここに彼等の自由なる空想は甦つた。ここに、この素晴らしい建築に、せめて都会人で
あるといふみじめな意識の中に、光りが投げ込まれた。誇りと、感歎と、期待と、フアンタヂイと……
かくて冬も去つた。破れ戸、薄い蒲団に、彼等行人の気も重る冬が去った。悪性流行病が彼等の幾百人
を殺し、彼等幾百人の妻を殺し、幾百の嬰児を貧中に殺した冬が去つた!ああ!、依然として高まりゆくビ
ルデイングよ!金権と人力のピラミッドよ!彼等都市人のみじめな誇りと空想と期待を、一日一日と実現し
ゆく偉大なスフインクスよ!五階だ!……六階だ……七階だ!
ああ 友よ、今にして私は思ひ当たつた。この板囲ひ、この葦簾張りが、いつまでも、いつまでも取り去られ
なかつたならば、彼等はもつと幸福であつたらうと。「もつと、もつと、高く、高く!」といふ彼等の空想、彼等の
期特は、いつまでも破りたくなかった!
今、彼等は憂鬱だ。失望と、永い期待の後の倦怠が、彼等の心を蝕む。こんなことを聞いたならば、このビル
デイング所有者は腹を砲へて笑ふだらう。ああ その笑声が聞こえるやうだ。その笑声が、この建築の無数の
窓から群集の上に浴びせかけられてゐるやうだ。思ひかへせば、既にあのコンクリートの流れる轟音が、その
嘲笑の声ではなかつたか!
やめよう。既にすぎたことだ。私はただこの言を君に告げれば足りる。行人は建物を打ち仰いで初めて知つた。
空がこんなに青いこと、明るいこと、そして、どんなに高くはるかなこと!又、この白色の建築に添ふて、どんな
に柳の新緑が美しいこと、今や春がすぎて、初夏の季節であるここと!おそらくは彼等の心に、あのまるいま
るい青天井と、ひろいひろい野つぱらのことが、古い日記を繙くやうに、思ひ出されてゐるに違ひない。“
──大正十四年六月十日──
16.
白鳩
はたはたと白鳩がとぶ
精霊のやうに白鳩がとびまよふ
仰ぎみる紺碧の空のさなかを
ただ一羽
白き蓮(はちす)の花ちりかかるひとひらのやうに!
ああ 澄みてあをく
玻璃器(グラス)に匂ふりきゆーるの色か
一抹の雲さえみえず
ひとすぢの煙すらけふは流れぬ
めざむるばかりうるはしい
大空の素顔の一点!
はたはたと白鳩がとぶ
かなしみのいたみを耐へて白鳩がとびまよふ
そらのあを きはまりて
こぼるる雫のやうに ただ一羽
放鳥の白鳩ゆきまよひ
墓地の上をなきながらとぶ
ああ おそらくは
白鳩よ
過ぎし日の彼の女のために!
ひとたびは恋にほほえみ
ひとたびはおののくその手われにあたへ
ひとたびは泣きぬれ
やがて去りゆきし彼の女のために
ああ 白鳩よ
かなしみを耐へてもとぶか
はたはたと白鳩がとぶ
精霊のやうに白鳩がとびまよふ
あをぞらのあをさにいたみ ただ一羽
白き蓮(はちす)の花ちりかかるひとひらのやうに!
17.
忘却の恍惚
夜は ものみな
ものみなを忘却のさびしさに酔ふとき
人はねむり 人はわすれ
水はながれ 水はわすれ
月は照り 月はわすれ
ものみな ものみなをわすれ
ひとりにかへり
ひとりをみつめ
そのさびしさに酔ふとき
夜はものみな
ものみなを忘却のさびしさに酔ふとき
水はわすれ 水はながるる
人はわすれ 人はねむる
生ひしげる樹々おのづから蔭をなし
ものみな ものみなをわすれ
ひとりにかへり
ひとりをわすれ
虔(いた)ましき黙祷の姿にかへる
月は照り 月はわすれ
ああ この十六夜月(いざよいづき)くらき曠野に
径はのび 径はわすれし小径をたどる
われもまたわがみをわすれ
ものみなをわすれ
ああ わがおもひ君にかへる
君をわすれわがみをわすれ
ただひとりの霊(たま)にぞかへる!
18.
かなしき秋
ほのあをむ幽愁の瞼
幽かにみひらき
秋はまづ深い静思からかへる
その瞳(め)
幽遠のおもひこもるその瞳
澄みて光るその瞳
いざなふ風
ほのぼのと吹きゆけば
匂ふその瞳
さゆらぐ目縁(まぶち)
ああ ふともみる哀しみのいろ!
秋──
崇高(けだか)くうつくしく
叡智に冴ゆる秋の額を
あをぞらにみる!
秋──
ありとしもみえぬ
霊魂(たましひ)のつかれのいろを
逝く水にみる!
ああ 秋思の楽は森の奥処(おくが)に!
清怨のうたはをとめの唇(くち)に!
さらにみる
秋は
いろあをざめた恩愛の手を
黒髪に捲き
人々の上にさしのべ
かつ おののきふるふその手!
さらに聴く
秋は
すぎゆく「時」の楽人を
地の上になげき彷徨はせ
こころ飢えさせ
かつひそかにもらす吐息を!
ああ 幽遠のおもひこもる秋の瞳は
大空を流れゆく白雲のゆくかた
とほい地平のかなたへ──
おののきふるふ恩愛のその手しづかに
大地の上におきながら
かなしき唖──秋の唇のあたり
たゆたふただ一言の真理!
19.
ダリア
わづか数日の間
私の机の片隅にあつて
うつとりと幻想を含みながら
静かな生をたのしみ
つつましやかにその足らひを微笑むでゐた
きいろのダリア
それも今は
がつくり垂れ凋んで
はかない姿を
私の目にかなしませる
私の愛する日本の女のやうに
宿命の忍従に
殆んど苦悩ももたない
哀れなダリア
そのながい生育は
澄んだ秋の空の下で
短い青春を微笑むための
ただそのためのやう
美くしい着物のために
祭の日を待ちこがれる
少女心と何の差があらう
ただ そこにさびしさがある
幼ない頃からあこがれてゐた
青春のすぎゆく悲哀がある
待ちあぐんだひとときが
おお 何気なく消えてゆく!
力弱い焦燥と反抗が
禧びのこころにかげつてゐる
けれど ああその面には
泪ぐましい微笑がうかぶ
ためらひながらも
心ひそかに待ちのぞむ
いとしい媚がある
わづか数日
私の机の片隅で
ありえないものを夢みながら
静かな生を楽しみ
つつましやかにその足らひを微笑むでゐた
きいろのダリア
それも今は
がつくりと垂れ凋んでしまつた
その姿に
寂滅の法悦が
宿命の忍従が
うつくしく漂つてゐる
20.
秘められた庭園の小径
公園のくらい小径を歩いてゐた
小径は私の背よりもたかく生ひ繁る萩や薄の下蔭をのびてゐる
ときをりその繁みのあひまから
黒い池の面に映るあーく燈の灯影が
私の目にちらちらとみえた
しづかに しづかに歩いてゐた
肩や手にすれてさらさらと鳴る草の葉の
一葉一葉にふかい愛着をおぼえながら
くらい小径を歩いて行つた
公園へくる誰もが気付かないこの静かな池
池をくまどる寂しいうつくしい小径
数年前私は親しい友等とこの小径を愛し
毎夜のやうに歩いたものだ
事実その頃 この小径で誰ひとりみかけたことはなかつたので
それは私達の秘められた庭園であつたのだ
そらんじて 目をとぢてでもたどれたこの小径も
今はおぼろげな記憶とともにたどるので
どきどき叢に足を踏み入れたり
みちばたの捨石につまづいたり
それがたとへないさびしさをもつて
私のこころをおもらせていつた
やがて径は汀につづき
そこのひともとの柳の樹蔭に
粗末な木製の腰掛けがある
私達はいつもそこで休むならはしであつた
今ものこるこの置き忘れられた腰掛けに
私は記憶のままに身をよせて
池の向ふにともされた一本のあーく燈と
それが池水にちるあをい灯影を
味ふやうな心地でながめてゐた
ああ
かつての日 この池を愛しこの小径を愛し
粗末なこの腰掛けによつて
語り合ふ のぞみや恋のかなしみを愛した私達
ひるがへすすべもない失はれた数年の月日が
私達の秘められた庭園の夜に
いつとなく刻んだそれらの形ない群像を
まざまざとかたはらにみたとき
「昨日」の自分の死を
さびしい微笑のうちに私はうなづいたのだ
21.
雨の日の窓
雨の降る日 私の部屋はいつも夕暮れだ
午後は北向きの窓に机をはこび
私はしづかに読書しまた黙想する
降る雨の冷寒は頬にさみしく
降る雨の顫音は
こころをかろく踏み去りゆく哀慕の跫音
して 私の胸に残るものは
その繊細な白い爪先のおもひしる痛みの接触(たつち)
そして 砂上の足跡
せまいほそながい庭のながめに
八つ手 つつじ 南天 そのほか自然生(ひとりばえ)の雑草は
濡れそぼち濡れ光りながら動かない
ああ それらの光沢のつめたさ
すべて 冬のかはたれの薄光の
するどさ あはさ 魂にしみ入る蒼ざめたしろさ!
五月も終らうとしてゐる
私の人生のそれもまた!
ああ 何といふ平凡で
そして 何といふうれひの言葉であらう
春は逝くのだ
咲かない花は それでも散らねばならない
そして 夏を迎へねばならない
ああ 聖なる母よ
私の魂の母胎よ
かかる日 私のおもひは
はるか 私の背後に閉ざされた
永劫の鉄門を飛びこえ 飛びこえ
あなたの宮居のあたりを彷徨ふのです
私をへだてる越えがたい未知の高塀に身を寄せながら
今私の机の上にあるは
ストリンドベルヒの「痴人の懺悔」
そして壁にかかげてあるは
ロダンの「スプリング」
ああ 悩みはそも何のために
いたみはまた何のつぐない?
母上よ
吾々の暴君(たいらんと)「時」の持つ計り知れない絶対力
その胸に湧く千万の して一様なる非情の憎しみとは?
雨の日午後三時となれば
ならはしのごとく 私は湯を沸かせ
ひとり紅茶の用意をする
このたのしみ このさびしきたのしみを
わかつべき誰も
その誰も今日また訪れては来ない
22.
孤独の殿堂守
つひに私はみつけだした!
かの女は
あをじろい森を通り抜けて
寂しい草原をすぎ
小山を越へたかなたの
寒い入日の孤独の殿堂に
そつとその身をかくしてゐたのだ
私はみつけだした!
その殿堂の
秋色の壁の蔭に──
おお あなたよ!
胸にしつかと抱きしめて──
そのときお前は
踏みしだいたダリアのやうに
私にかなしい誠実をみせてくれた
私はお前に語つた あをじろい森を
又夕墓れの野道を
森のかなたの愛憎の海を
お前はだまつてきいてゐた
しかもお前の頬は私の頬に
うるはしい夢の陶酔をつたへ
お前の瞳は
静謐他な孤独の中にぢつと輝いてゐた
ああ 寂寥よ!
お前の頬はいつも夢みてゐる
お前の唇は
いつも無言の語らひをつづけ
お前の指は沈丁花
その匂ひのごと深き哀愁の腕(かひな)よ!
ああ 汝(なれ)の夕暮れの袂は
私をふかくお前の胸に沈ませる
お前は心の香をまとひ
感激の涯を逍遥する
又は愛憎の海面に
夕和ぎの裳裾をひき
失意の沼にその瞳を映す
私がかの女の腕をはらつて
煩悩の海にあるとき
かの女は岸にあつて微笑みつづける
私が愛憎の浪に捲かれるとき
かの女の眸は星のごとかなしい
私が自嘖の鞭打つとき
かの女は白い両腕をのべて
不倫の身を支へてくれる
ああ あなたよ と
草原を 夕暮れの小山を越えて
私がかの女を
あの灰色の壁の蔭に抱いたとき
そのときからかの女は私の聖母
日もすがら 夜もすがら
孤独の殿堂の扉を
私のために守り
私のために開閉する
23.
文字
たとへば 唇 頬 瞳眸(ひとみ)──
文字は夢をいざなふ香炉
愛恋の血潮みなぎる象徴の心臓
情緒を結晶(かた)めた稀世の寶玉
たとへば 薔薇 白百合 沈丁花──
文字は封じられた香水壜
心の臭覚を魅する春夜の貴婦人
あるひは白い素足の曲線
文字はみえざる想像のプリズム
感情を色分けする仮説の試験管(ビーカー)
たとへば 紅 淡紅 青 黒 灰色
ああ 文字は
心から心へ訪れまはる情感の微風
魂の窓から窓へささやきわたる詩想の翼
空間を波うつ不滅の血潮
みえざる流れの韻律 その象徴の楽譜
たとへば 悲哀 吐息 苦悩 歓喜
久遠の泉 不死の伝令
万人の胸に置かれたピアノの鍵(キー)
おお 打ち叩け打ち鳴らせ みえざる楽人
忘れられたるピアノの鍵を
呼びさませ 万人の胸より睡れる熱情を
恋 血潮 反逆──
みえざる楽人
おお 精霊なる詩人よ!
24.
扉
“ただ一歩!”
迷悶の闇をつらぬく
光りのごとき声を聴いた
おお ただ一歩!
私は希望にふるへ乍ら大胆に叫ぶ
ただ 一歩!
永劫不滅の憧憬の世界は
扉一重のそこにある
さつと押し開けば
押し開きさへすれば!
おお 扉 扉
いつまでハンドルを握りしめてゐるのだ
手が錆びついてしまつたのか
力が萎えたのか
どこかで啼いてゐるのは小鳥だ
囁いてゐるのは小川だ
あのものやさしい衣ずれの音は
花園をさまよふ風にちがひない
押し開くのだ
恐れることはない!
扉の彼方が更に真暗な部屋であったら?
であつたら介ふことはない
その扉も押し開くのだ 押し開くのだ!
おお ただ一歩
そこに久遠の希望が賭してある!
悪魔の創つた迷宮?
それでもいい
その部屋部屋を突き進んでゆけ!
まがふかたもない
あの声は小鳥の歌だ
小川も流れてゐる
風もふいてゐる
おお どこかに!
そこには
空も森も
草も
花も
夢も!
25.
飛行機
いつもすこやかなテノール
この秋晴れのしづかな午后を
どこから飛んで来たのか
ほんとうに健康なテノール
季節をしらぬ優美なテノール
大空のあをさのなかに
しみ入るやうな燻銀の翼を張つて
気侭に舞ひあがり 滑りおち
喉ふるはせて歌ひまはる
あの自由で勇敢なテノール!
鉄いろにすすけた屋根瓦の下の
はてしない労苦にほろびゆく都会
凋落の前の
かたくなな黙しに耽つてゐる秋の樹々 秋の草園
みんな一斉にこころ奪はれ
この大空の寵児の
明るいすこやかな楽に聴きほれてゐる
ああ 秋の悒鬱をうらがへし
壮快に飛び歌ふ大空のテノール
湧きたつみづからの悦びに
哄笑して宙返る快心のテノール
陽光(ひかり)の洪水に翼濡らせて
たかくたかく 又低く飛び
飛びながらも歌ひやまぬ
健康と自然と科学の謳歌者!
おお、いつもすこやかで大胆なテノール
この秋晴れのしづかな午后を
どこから飛んで来たのか
あをく あをく 限りなく明るく
澄み切つた大空のさなかを
真一文字にすべり
弧を描き
悠揚として鳶のごと輪をつくる
おお、何といふ自由!その何といふ剛気!
大空と太陽と空気と
それらの限りない寵愛一身に集め
それらの限りない享楽をほしいままにする
天空の翼持つテノール
お前の声は大気をふるはせて疾風のやうに
お前の楽は地上いつさいのものを溺らせて海瀟のやうに
おお、健康と自由と科学の謳歌者!
みよ!
はてしない究理の沼に沈潜して
永遠の翼捩ぎとられた都市人の上を
煤煙と煉瓦に窒息して
いつか健康と運用の王座をすべり落ちた都市人の上を
ああ 遠い遠い人類の歴史の
燦欄たるタイトルペーヂの裡に
彼等が置き忘れて来たあの雄美な天馬(ペガサス)は
ふたたび健康と美の 力と智恵の
限りない饗宴の謳歌に酔ふ!
ああ、いつもすこやかで雄美なテノール
この秋晴れのしづかな午后を
どこから飛んで来たのか
26.
心像を刻みゆく
深い深い魔睡の淵から
浮きあがつたとおもはれた
底のない真暗な洞窟から
やうやうに匐ひ出たとおもはれた
なにかしら執拗な魔術の恐怖に追はれ
ながいはげしい足掻きののち
おとろへはてた意識は毛布に包まれて
船室のなかに横たはつてゐた
ああ、いつからとなく
意識の涯にたゆたつてゐた
浪の音 ヱンヂンのひびき!
泣くやうに またののしるやうな
たえまないそれらの脅威とともに
次第にめざめ 湧きひろがり
おしせまつてくるたまらない旅愁!
ああ、いつの日か旅立ち
いつの日か流浪の夜をかさね
今はまた見知らぬ人々とともに
間ふなく雑魚寝してゐる身には
昨日もとほく
とほい日のおぼろの記憶もよみがへり
すぎ去つた月日 すべては
ただむなしい
たださびしかつた
ながいながい流浪の一日の記憶!
おお いかばかり果敢ないことも
私には 引き寄せ抱き締めたい愛しい記憶!
それも永遠に
地にはかへらない昨日の幻影だ
空に描き
空に動かせ 物語らしめ
ああ けれど
耐へて来た悲しみや苦しみ またよろこびは
すべてこの胸 この私の胸のみには
今も鮮やかによみがへつて来る!
──湧きだつ波の音 ヱンヂンのひびき!
おお 船よ 行け!
涯しない闇の船路を
今もすぎゆく「時」の面(おもて)に
不滅のわが心像を私は刻みつけよう
ああ 永遠に未完成のこの心像!
けれど私には唯一無二 畢生の希願(ねがひ)なのだ!
揺れあがり揺れ落ちる船
いよいよに高まりゆく潮騒
漂ふ液体のやうなムードにたへかねて
起きあがり私は船室の窓をひらいた
さつと吹き入るつめたい夜風!
真夜の太洋は闇におほはれて
外にはただ挑むやうな浪の音ばかり……
午前一時 船が熊野灘へさしかかる頃だ
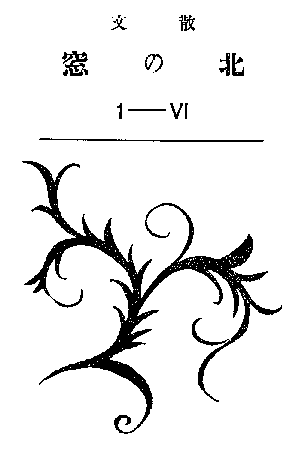
散文 北の窓 Ⅰ─Ⅵ
北の窓──Ⅰ
晴れては曇り、明けては暮れ、この北の窓にもやうやく春の気が見え初めた。永い間、といふても去年の暮れから、すつかり不在勝ちで、はたきひとつかけなかつたこの硝子障子の、 桟に積つた白い埃が、今日はひとしほ目立つ。埃と云へ桟ばかりでなく、一閑張りの机の上に、すかしてみればつもりつもってゐる埃。 取りちらした書籍の間からは、 年賀状ものぞいてゐるし、旅行きの折々に持ちかへつた、その地その地の名所案内ものぞいてゐる。 いつもの事ではあるが、新年といふ奴は、来る度毎に何か異つた足跡を残してゆく。 大尽日の夜までは、何の新年ぞと馬耳東風、けれどもいよいよ明けて、年賀状の一束も机上に載り、さて年賀の客の応接もうるさし、仕様ことなしに迷惑と知りつつ、 友の部屋をのぞいても見、借りても見、そのうちにはいつの間にやら新年らしい気分にもなり、一盞が二盞となり、二言が三言となり、酒もよからう、旅もよからうといふことになる。 今年も亦その手だ。その手で明けてその手で終らうとしてゐる。今日は二月の十五日、私はひつそりと机に対ひ、硝子障子から庭の竹を眺めてゐる。
閑寂といふ言葉があるが、此の頃の私の心持ちは、それ程にもゆとりなく、又それ程にもさびてゐない。あわただしい旅を終つて、その翌朝、ひとり雪曇りの空をみてゐるやうな、 どこかまだ旅情の消えやらぬ侘びしさ。言ひたくもなく、聞きたくもないといふ心地。見たくもない、見せたくもないといふ心地。とは云へ、時にはよき聴き手も欲しくなる。 それがいけない、云つてしまへば何もない、ただあはい悔ひだけが残る。 詩、詩ばかりがかうした折のよき話し手であり、よき聴き手でもある。悲しき玩具である。けれど尚耐へやらぬ心地、ぢつとして居れない心地、全く反響のない別世界に居るおもひ、 かの古ぼけた泥壁の中に住むといふ、時をのみ喰ふ時計虫のさびしさ、いらだたしさ。
夢、夢こ云つてしまへばそれだけだ。あの酒が、あの女が、あの放肆な思ひが考へが──さらば、吾々はいかに夢のみ多き生活者であらう!あの素晴らしい計画、 あの夢想、あの焦心、あの自尊……ああ それらすべてが夢?夢だから消えると云へばそれまでだ。 そうだ、消えてしまつた。私はいまひつそりと机に対ひ、硝子障子から庭の竹を眺めてゐる。
なれはあそびめ いつもたはむれをたはむれてゐる
私はそれをながめ そしてほほえむ
いつはりのはなばな いつはりのゆめ
なれはそれらをまきちらす いつはりのヴヰナス
私はいつもそれをながめ そしてわらふ
いつはりをいつはりとしてあそぶに
なにゆえの傷心ぞ
おろかにも
いつはりを こころすでにいつはりてありしといふか
友達よ!私は今真実に呼びかける。淋しいからばかりではない。情けないからばかりではない。私の傷心のよき相棒になつてくれといふのでもない。友達よ、 私はいま四旬にあまる自分の、とり乱した生活をかへりみて、この心を、この生活をやぅうく静かに整列させようとしてゐる。何ものに向つてこの倒れた心を立て直すべきか、よし、 たとひ日暮れて道遠しの感ありとしても、私はその遠き遥かな道に向つて、静かに鞭を振らう。
野々部君、君があの山中の宿で、すつかり酒に苦しむで、四時近くまで私を眠らせなかった夜、私は雪解の水のしたたる音を聴きながら、 いかに物思ひに耽つたことだらう。十二時近く、あの石油缶のやうに三味を鳴らす女達を迫ひかへして後、いや、君が苦しみあがき、疲れ切つて寝入つてしまつた二時頃からの二時間、 私は青ざめて時々苦しげに歪める君の顔をみつめ乍ら、今更のやうに人生の旅といふことに就いて想つた。その時、私には君の顔が、つかひふるした青い手袋のやうにおもはれた。 履きへらした草履のやうにおもはれた。運命が、みえざる鞭を持つ運命が、履きへらした草履、つかひふるした手袋……。そうではないか、人の寝顔といふものは、 誰が履いたとも分らない路傍に捨てられた草履! 希望が、輝く理想が、その寝顔をまで明るくしてゐるといふやうな、そうした人、そうした顔に私は未だ会はない。
私は、蒼ざめ汗ばんでゐる君の額に、そつと手を触れながら聴いた、あの水の音を今も忘れない。おそらくはいつまでも忘れないであらう。それは真夜を過ぎゆく時雨の音か、 あるひは雪解の水のしたたる音であつたか……私の心に、犯しがたい神秘な或るものを囁くやうにおもはれた。よもすがら、じつにそれは不可思議な声をもって、私の耳を、 私の心を領してゐたのであつた。静寂のきはみに、したたり落ちるあの水の音、それはまたダヌンチオの聴いたものではなかつたらうか?あの時、私は何故ともなく彼の詩をおもひ出してゐた───
われはきく、よもすがら、わが胸の上に、君眠る時、
吾は聴く、夜の静寂(しづけき)に、滴(したたり)の落つるを将(はた)、落つるを。
常にかつ近み、かつ遠み、絶間なく落つるをきく、
夜もすがら、君眠る時、君眠る時、われひとりして。
──上田敏氏訳、ダヌンチオ「声曲(もののね)」──
ああ 二月十五日、私の月に二日の休み日も暮れてゆく。
風が出た。庭の竹がさやさやと鳴つてゐる。
──大正十五年二月十五日──
北の窓──Ⅱ
五月の初めであつたか、高木君が伊豆の湯ケ島からたよりをくれた。「石楠のまつさかり、蝶々花もいいですよ」などと。その日は雨が降つてゐたやうにおもふ。 石楠のことから、藤村氏の落梅集の中にある「草枕」といふ詩など思ひ出して、静かに吟唱したり、旅の君をおもつたりしてゐるうちに、自分も旅に出たい想ひにみだされて、 それからといふもの、この北向き六畳の部屋が私の心を落ちつかせなくなつてしまつた。 「漂泊のおもひ止まず」と芭蕉は云つた。藤村氏は、「エトランゼ」の中で、巴里の客舎にあつても、芭蕉のものは手放さなかつたやうに書いてゐられた。 オークランドの街の上、 ハイトにミラーを訪れた十九歳の野口氏も、やはりそうであつたとか。風狂芭蕉は、やがて旅窓に聴く雨のやうに、旅を恋ふ心の裡に、不滅の影となつて彷徨ひ入つてしまつた。 かてて加へて、この二十八日に私の友の一人が、巴里へ旅立つことになつた。その別れの夜、私には到底素面では心耐へがたく思はれた。西へ、西へ、港から港を辿りゆく彼をおもへば、 私のせまい庭に迷へる夜風をみても、此の頃はただならぬ思ひにみだされがちだ。
一昨年の夏であつたか、友と二人で紀州を船で下つたことがあつた。串本の旅宿の二階から、いつもなつかしく定期船を眺め、又いつまでもいつまでも、 港の空に消え残つてゐるやうな汽笛の響きに、心かたむけて聴き入つたものだ。雨の多い旅であつた。 私は又あの朝のことを思ひ出す。しろじろとさ霧の漂ふすがすがしい海の朝明けであつた。船は日高川の河口に止つた。幾人かの船客は、まだほの暗い船腹の梯子を降りて行つた。 私は寝不足の目にしみる海気をたのしみ乍ら、甲板に立つて、はしけとともに船を去りゆく人々を眺めてゐた。その中には、大阪あたりからの帰郷らしい美しい女学生一人みえた。 はしけはやがて波頭に埋つてゐる日高川を遡つて行つた。そして本船もヱンヂンを響かせ初めた。黎明の峯に美しい紀洲の山脈、そして、美しい伝説の土地、河の名、私はあの朝のことを忘れない。
私はこの城北にゐて、折々汽船の笛の音をきく。それは真夜の十二時、名古屋港を出る紀州廻りの定期船の汽笛だ。夜ふかしをして机に対つてゐるとき、 寝苦しく床の中に眼覚めてゐるとき、南の風の吹いてゐる夜などは、殊にはつきりときこえて来る。そんなときは、この身も追憶の中に息づいて、私は浪の音を聴くやうにおもふ。 遠く親しい人々を離れてゐるやうにおもふ。そして、私の心は旅愁のうちにその身を伏せる。 ああ、追憶は遠く去るに従つていよいよ美しく、なつかしく、情あるものとなつて来る。しかも私の筆は次第に枯れてゆく。私は旅に出たい。
──大正十四年五月十九日──
北の窓──Ⅲ
「菊の咲く頃に、また便りをせよう」と云つた友が、「菊の咲く頃がきたので、いつか約束した如くお便りを致します」と云つて、そのなつかしい手紙を寄せてくれた。 それは十一月の初めであった。 ああ、菊の吹く頃! 庭にその花の影すらなく、部屋にその花の香りさへ漂はない私の家にも、それはしんしんと深んでゐた。友の便りを手にしてからは、 一輪の垣間の花にも、何故となく、殊更らに心ひかれるやうになつた。菊の花──とりわけて中輪の白菊の花、それはなんといふ高雅な清純な香りと姿をもつてゐるのであらう。 十一月の朝空の匂ひも、到底この花の香りに如くべくもない。 それにしても、私は友の約束を思ひ出す毎に、その友の環境、心情がしのばれて、一層したしみを感ずる。 おそらくは友の書斎の窓の外、ささやかな竹垣の下の乱菊は、かの頃、つぶらな蕾をもたげてゐたのであらう。 おそらくはこの頃、乱れ咲く白菊の香りは、友の書斎にみちみち、朝な朝な、その窓に晩秋の青空映り、百舌鳥も亦その朝をしきり啼いてゐるのであらう。北日本の田舎に住む友よ、 私も亦菊の花を愛する。
菊の花の栽培は、かなり専門的な技術を要するといふ。にもかかはらず、私は到るところで数多い鉢植えの大輪の花をみる。むさくるしい豆腐屋の店先で、会社員の玄関で、 裏長屋の軒下で、──それらはすべて、一年の配慮の後に咲き出でた花を、人々とともに愛楽しようとする、その家の主人の美しい心づくしなのだ。それはなんといふ美事な彼の心の表現であらう。 彼は気短かである、彼は吝嗇である、彼は不潔を意に介しない──よし、それらの批難が、あるひは彼に当てはまるかもしれない。けれど彼が手づから一年の愛育の後、 咲き出でた花々を多くの人々と楽しまふとするとき、ああ 決して彼はその批難にふさはしくない!
──大正十四年十一月──
北の窓──Ⅳ
新らしき明日の来るを信ずといふ
自分の言葉に
嘘はなけれど──
今夜、啄木の歌集を読んでゐたら、こんな歌が目にとまつた。自分の日毎の記録の中に屡々記したことのあるかういふ言葉を、啄木の歌の中にみいだしたことが、 何故となく自分をなぐさめてくれたやうに思った。 半ばの真、半ばの嘘──信じようとするが故に真であり、「到底在りがたい」といふ心中の懐疑怯懦の声の、その拠るところを充分認め知りながら、尚信ずといふが故の嘘。 云ひ得れば積極的の真、消極的の嘘。態度の真、事実の嘘。事実よりも態度の中に真があり、態度の中に未来があるのだ。勿論、つづめて云へば、事実と態度とを分けることが、 既に怯懦なのかもしれない。
昨年、H(編者註 春山行夫)が去り、今月初めS(編者註 佐藤一英)が東都に去つて、この城北の地に又侯僕だけが取り残された、不定往者のさびしさ、 定住者のさびしさ。 どうせ居ても、毎夜逢ふといふ訳でもないが、居るといふ意識と、居ないといふ意識とは、かうして自分の部屋にひとりゐても、 こんなに強く異つた心地を味はせるものかと思ふと、平常何の不思議もないこととして片付けてゐる事だが、存在といふことに対する絶対の信仰の力強さが、しみじみ感ぜられる。 考へてみれば、宗教家の神に対する信仰の強さも、ここにあるのであろう。形而下の存在に対するこの信仰を、形而上にまでしつかり押し進めて行かねばならない。 孤独の裡に、その甘さや、調和を感じ得ても、真の充実を感じ得ない自分をさびしく思ふ。
「生ける無」だとか「死せる有」といふことが、よく考へられる。そしていつも、自分をかへりみる毎に、せめて「生ける有」の中にありたいと願ふ。 ある雨の晩だつた。僕は読書に疲れて、何故ともなく燈を消し、端座し、瞑目した。そのとき、さんさんと音のみして、目にみえず、手にとれない雨の音を聴きながら、 この雨の音こそ生ける無ではないかとおもつた。ここに悟入の道が拓けてゐるやうに思はれた──いや、その道は何処にも開かれてゐる筈なのだ。
「月はあれど留守のやうなり須磨の夏」と芭蕉の歌つた、あの須磨の海岸の警察署の横の立札に、こんな民謡が書いてあると友が感心してゐた。 うろおぼえに記しておいたもの──
須磨のまへだのかきつのなかに
あやめ咲くとは知らなんだ
咲いてしほれて又咲く花は
須磨のまへだのかきつばた
誰が歌つたのか、いつ頃の作なのか知らないが、心さびしいときなど、ひとりしづかに愛誦してゐる。
──大正十四年六月十二日──
北の窓──Ⅴ
けさの朝戸あけしめて空のま青(さお)さよ
泪しづかに目見(まみ)ににじみ来(く)
網干場にかつがつ伸びし草の葉の
夜はかそけき露もつあはれさ
誰か ひとたび短歌を愛し、短歌を学んだことのあるものが、短歌への愛着を忘れることが出来るだらうか。
誰か、且つて君が少年の時殊に愛誦したいくらかの短歌を忘れることがあるだらうか。そして、君が今に至るまで折にふれて思ひ出し、口づさむいくらかの歌がないといふことがあり得るだらうか。
そうだ、こうした一首の歌をも持たないものはいかにも不幸な人である。それらの歌は、日常生活の煩忙と悲惨の時を通じて吾々の心への、詩人が送る無二の慰藉と救ひであるとも云ふべきだらう。
それらの歌は、日毎に萎びゆく吾々の心葉におりる、朝毎の露でもあらう。
或る時は、頑固に荒んだ吾々の心を少年の如くに泣かしめるもの、短歌は何故にこのやうな力を持つてゐるのか。勿論、そこには軽々に云ひつくせない複雑な、
微妙な理由があるけれごも、その最も大いなる理由は、その秀れた単純、純真さにあると云ふことは否みがたい事であらう。私が最初に記した二首も、この純真さに於て秀れた作品であり、
亦私の愛誦歌でもある。敬愛する歌人、鎌田敬止氏のこの短歌が、どんなに湿ひない私の此の頃の心を和ごめてくれることであらう。「彼等の藝術は極めて単純だ……然し単純だからとて、
それは無内容といふ意味でない。外面的な単純は、真実な単純でない。単純な藝術で始めて此処に暗示的藝術たることが出来るのである」(野口米次郎氏、東西文学論)そして、
若し諸君が、私が最初にかかげた二首の歌を、よく味ひさへすれば、諸君は私の云はふとすることを最もよく了解してくれるだらうことを信ずる。
藝術の究極は感動にある。それは騒々しい紛雑な感激でなくて、心静かな感動にある。私は野口氏の詩境を切に思ふ。けれど、この心静かなる感動を求めるためには、
吾々は詩を生きなくてはならないのだ。生活の詩人、態度の詩人でなくてはならないのだ。そして此の事の至難を思ふ時、私はメーテルリンクの次の言葉を思ひ出さずにはゐられない。
「例令諸君が一つの小さな室しか持つてゐないとしても、諸君は神はその中に居られないと云ふか。亦多少なり崇高な生活はその中で送ることは困難であると考へるか。
諸君は孤独なことや、変つ事件のないことや、何人をも愛せず、何人にも愛せられない事やに就いて不平を云ふ時、諸君はそれらの言葉を真実であると考へるか」
現在の多数の詩人は、私にとつて何の意義もない。何故ならば彼等の詩を読むことと、朝毎に私が読んだ新聞の記事との間に何の差も見出し得ないからだ。では、 私の心の門に消しがたい位置を領してゐる詩人は幾人あらう。それは極めて僅少の人々に過ぎない。それらの人々の詩は、いつも私の思ひを人生に誘ふ。常に多彩な衣裳と紛雑な暇面の中に、 神秘の裸身を隠して吾々の服を偽る人生に触れしめる。人生そのもの、生命そのものの真の姿を暗示してくれる。それは、吾々が宿命を読まふとして凝視する、 かの西空に落ちゆく上弦月の如く、吾々の心眼を厳粛にして最高なる問題の方へ向けしめる。
──大正十四年三月十六日──
北の窓──Ⅵ
──編輯を終えて──
小泉八雲が、あんなに嘆称した日本の空、それがいよいよ霊的な青さを深めて来た。神智にも比ふべきその明徹さ、幽遠さ、森厳さ、──何人がこの秋空のもとで、 己れの感情を弄び得ようぞ!──ああ その中にひそむ一味の寂びをしみじみとかみしめるべきときが来た。 ヱ゛ルレヱヌの秋が来た。百舌が啼く、鶫も啼くであらう。黄金色にみのる稲田、紅葉する森。万物みづからの一年を、みづから飾るときが来た。蕭々と降る秋雨の中に、 みづからを問ふべきときが来た。
私は今、処女詩集「北の窓」を上梓するための、最後の筆を採つてゐる。これらの詩篇を、輯めることに費したこの数ケ月、まして、一束の過去のうたを机上にみる今、 私はみづからの貧しさを切に切におもふ。かかるおもひ、かかる心境は、人生の途上に於ける或る機会に於いて、おそらくは何人も感じ踏むところのものであらう。 しかしながらかかる心境にあって、ワイルドが彼の名著「獄中記」の中に刻むでゐるやうに、「何たる始めぞや、何たる驚異すべき始めぞや」と叫び得るや、いなや。 私はただ頭を低くして、しづかに云ふ。「これは結末ではない。これは新らしき出発である。」と。そして私は彼の銘すべき言葉をおもひだす。 罪人が悔悟しなければならぬのは云ふまでもないことである。けれども何故であるか。外でもない、悔悟することなしには、彼は自己の為したことを実現し得ぬからである。 悔悟の瞬間は啓蒙の瞬間である。一歩を進めて云へば、人は悔悟に依つて、その過去を変更するのである。(本間久雄氏の訳による) 秋──九月も既になかばをすぎてゐる。昔ながらの部屋に座して、仰ぎみる空はあをい。 友達よ、私は今十年に近い、この北向き六畳の部屋のなつかしい思ひ出をたぐる。 それは私に対してとひとしく、君等にも又なつかしいものであらう。昔ながらの一脚の椅子、昔ながらの机、そして君等の目にも見馴れた庭のながめ………ここに十年の春秋を経て、 いま私のする回顧は苦い。 北の窓──私の焦心や苦悩や感傷や、それらのあらゆるときを通じて、心をやり、心をなぐさめ、みづからをかへりみ、 みづからを痛んだこの北の窓……せまい庭に、私とともに住みふるした日蔭の樹々よ、もちの木、つつじ、南天、八ツ手、竹、つげの木、そうして、いつも春になれば芽ぶき、 秋雨に濡れて消え去る美しい雑草。空、屋根と樹と、軒端にはばまれた多角形の空、そこにも煙は流れ、雲はゆき、小鳥は飛ぶ。ああ それら、それらすべてのものも、 これらの詩篇の中に彼みづからのところを得てゐるであらう。
この筆を採る私の心はくらい。だが……友達よ、あの夕闇の海の、浪風にひらく白薔薇のやうに、いま私の心の面に浮ぶたのしいおもひがある。 私はこの詩集の出来た日に君等を訪れよう。そして、君等の掌上にこの詩集を置かう。私は想像する、この無言の贈りものは、その名のために、先づ微笑の禮をもつて、 あつく遇せられるであらう!と。
──大正十四年九月二十日──
跋
伴野 憲
まづ、精悍。純情。熱烈。
私はよびかへす昔の日に、そう三つを挙げて中山君を思ひ出す。そして、それを蔽ひ包む深い孤独が、いよいよ君を、憂鬱にしてしまつたといつてよい。
いつでも君は、酔えばよくうたつた。今でもうたふ。恐らくそのやうに、いつまでも、朗々とうたひいづるであらう。
ここに、君がながき自らの藝術節操に設らへた美しき墓標「北の窓」が、世のなつかしき人々の前に捧げられる。それはなんと君にとり詩に於ける厳粛な、また寂しい祭礼であらう。
このとき、君の多くのしたしき人々に立ちまぢつて、同じやうにこの「北の窓」をうちめぐり、うちめぐり、あるひは、よろこび、あるひは讃へ、また花束のひとつを、
そつと傍らに飾ることのできるのは、私にとつて、感慨無量、君の昔を思ひ出させ、ひとしほのよろこびに打たれずにはゐられない。
想へば、交遊十指の年を数へ、渝らざる友悌のうちに、あるときは、恋を描き、またあるときはうれはしき青春を歎かふ、また只ならぬ憧憬の一途に狂ひなど、まことに、まことに、
よき回想は血のいろ鮮やかなるがごとく、はつきりと、君の古き詩生活を私によびさましてくれる。
おお、極光のなかに浮びでた陰鬱なる思想! そしてまたかの重厚なる律動(リズム)、熱烈火のごとき詞の焔、精悍豹ににる表現の姿! そして君の詩は、 かの冬ながき北方の国に咲く花のこころ。君の朝夕、北の窓辺に、なんとそれは強靭なるいとなみであつたであらう。
しづかに しづかに君よ
この花を北の窓に置きたまへ
こころすさみ こころ堕ちたる吾等の胸に
この花のおくるさびしき匂ひを置きたまへ
この花のいろと この花のすがたと……
君はかなしくこの花にゆく蜜蜂
君はそのうれはしい羽音を聴くであらう
──(「時代錯誤の花」のくだり)──
この最近作にみるやうに、今や君は、素晴らしい眼を転回させようとしてゐる。この技の円熟、語の駆使の妙、新らしき象徴のさえ、悠揚、恍れ恍れとうたふあたり、 ながき君の自重、念々練磨の力の恐るべく、触れば忽ち斬るの一鋭鋒、またなき詩壇のかがやきではないか。 また、「月の出」にみるやうに、 君は美しい夢の世界に不思議な程も少年の日の誘惑をもつてゐる。君自ら汚れなき夢の潔い潔いプライドを胸に秘めてゐる。
空はまひるのやうに照らしだされた
聖なる庭のやうにうつくしい
白衣の懺悔僧のやうにしづしづと
祭壇にちかづく犠牲(いけにえ)の処女(おとめ)のやうに影もなく
光りのかたへすべつてゆくひとひらの雲
ではある。雄大なる、美しいひろさではある。
またかの「忘却の恍惚」をみよ。「かなしき秋」をみよ。君のすぐなる孤独のうたをこそ静かにきかま欲しいではないか。あるひはまた「雨の日の窓」をうかがへ。
このおもひゆたけき君の日常をなつかしまずにゐられやうか。でまた、私はひとつ、痛快なる君の心情、をあらはにしてくれる「飛行機」を見逃がしはしない。
剛快一挙よく天空を飛ぶ飛行機に、これはまた実にその侭なる君を見出すことのうれしさ。
また「空中楼閣」のもつこころ、集末の「北の窓」のうるほひに及んでは、かくべつ、私の辞を待つべくもない。
なつかしく私は今も昔のやうに、くつたくのない精悍、純情、熱烈を君にみる。君のそのながい間の詩作のうちから集められた「北の窓」が世に出ることは、 私をよろこばせるの無上のものだ。君の華やかなるべきこの祭礼を、待ちこがれたしたしき人らよ。私もそのひとりとなつて供に祝ひたい。
附言
ここに二十七篇の詩、多くすぎたであらうか? しかしながら、おそらくはかかる仕事に直面した、すべての者が陥るであらうヂレンマ、私もそのためには、
幾度びも稿を更へねばならなかった。 「北の窓」六章を加へたのは、私の心の記録たる意味に於いて、私にとつては詩と何ら異るものでなく、一面、読者が私の詩を理解せられる上に於いて、
又私自身を知られるために、無駄事ではないと信ずるからである。これらの雑文は、詩誌「新生」誌上に於いて、同じく「北の窓」の題下に、折々発表したものの中から採つた。
大正八年、親しき友等と感動誌社を起し、詩歌雑誌「曼珠沙華」を世に出して以来、同誌改題「独立詩文学」名古屋詩人聯盟のパンフレツト「先鋒」及び詩誌「風と家と岬」
同誌改題「清火夫」同じく「新生」に、私は私のすべての作品を発表して来た。それ以外に於いては、一篇の詩も発表してゐない。
「時代錯誤の花」は本年七月の作、「孤独の殿堂守」は大正十一年二月の作。ここに収録した詩篇のうち、最も新らしいものと、最も古いもの。「保美の里」までが、
「風と家と岬」(大正十三年十月)以後の作であり、「白鳩」以後が「独立詩文学」誌上に掲載のものである。 「曼珠沙華」(大正八年─同十年)に発表した詩篇は、
私にとつてはなつかしいものであるが、ここには収めなかった。 二三のものを除いては、発表当時のものを、そのままここに移した。不備ではあつても、
今になつて筆を入れるといふことは、始んど私には不可能事に思はれる。
この詩集の装幀は、友、柳亮に依頼して、その快諾を得てゐた。必らずやそれは、この詩集一層引き立たしてくれたに違ひない。しかるに、私の本詩集出版の意図の決定より、
今日に到る日時の短少と、彼が現在巴里に在るといふことが、つひに、私自らに不馴れな装幀の筆を採らせることになつてしまった。彼に対して済まないと同時に、残念でたまらない。
私達の所謂曼珠沙華時代、独立詩文学時代を経て今日に到る、私のかはらざる友、伴野憲、柳 亮、荒川 元、吉田浩三、その他の親しき友等に対して、私はここに過去のあつき友愛と、
よき鞭撻を衷心感謝する。
大正十五年十月十日
北の窓に倚りて
著 者
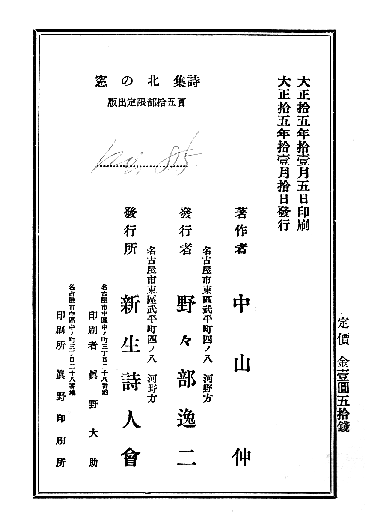
凡例
表記は仮名遣ひの不統一などすべて原本に従った。ルビは( )内に、また表示上該当漢字がないものも( )に読みを記すにとどめた。(追って改良します)。
新漢字のあるもの、明らかな誤植はこれを改めた。詩篇には頁の代はりに番号を新たに付した。(編者識)
【拾遺】
彼
五月幟の鯉だ
がばがばとそらに躍つてゐる
屈託がない
日もすがら風を呑み風を吐いてゐる
光をたべてゐるにちがひない
生きてゐる
躍動してゐる
風が強ければ強いほど元気だ
いつも常夏の國を目指して泳いでゐる
輝く青空こそは彼にうつてつけのステーヂだ
大きな口を無意味にそらむけて
だらしなくあの圖體をもてあましてゐる
風のない曇り日の彼の姿は
然し おかしいといふよりもむしろあはれだ
退屈はそして陰鬱は彼を殺す毒瓦斯なのだ
五月幟の鯉だ
機に乗じては呑舟の魚ともならう
不羈の精神(スピリツト)!
あの威勢のよさ!
朗らかな 朗らかな彼!
(寺下辰夫『ゆめがたみ(抒情小曲集)』交蘭社1931年刊行より)
なかやま しん【中山伸】(1903~1991)