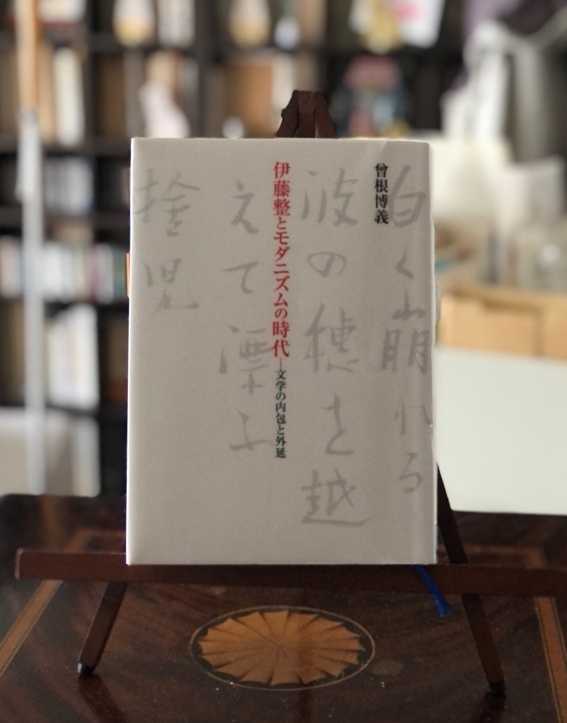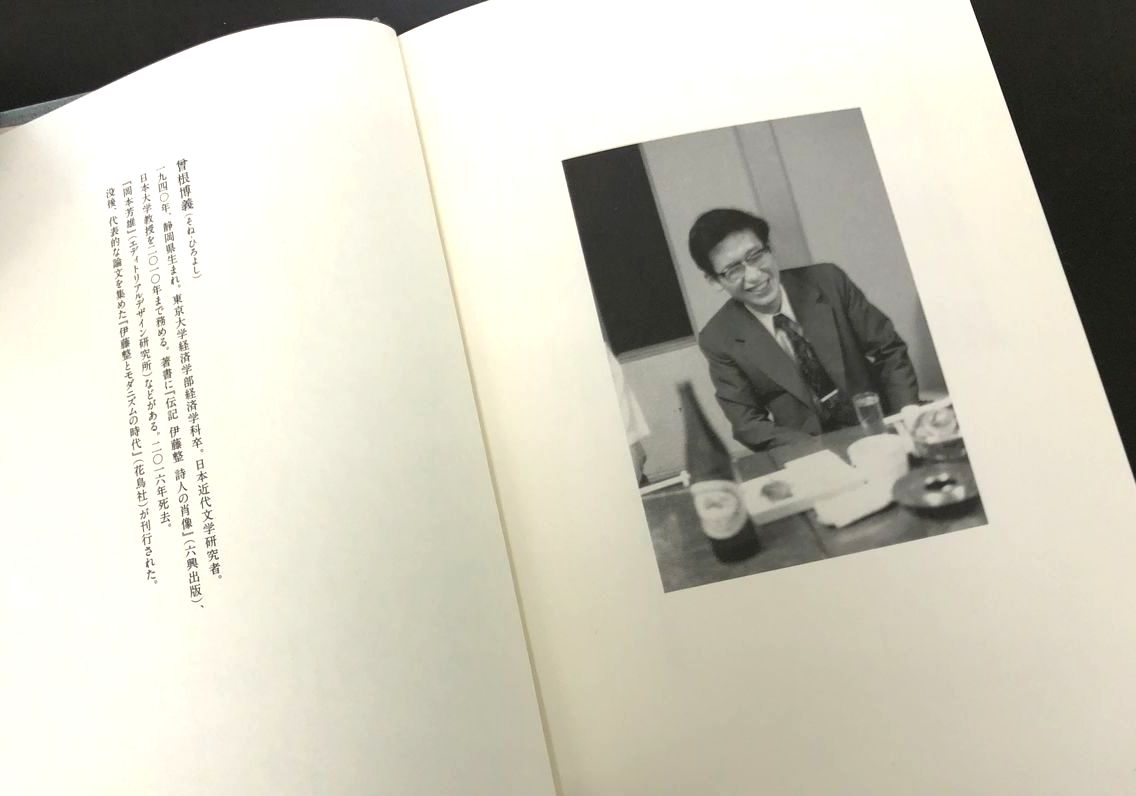永松定といふ英文学者のことは全く知りませんでした。辻野久憲は『四季』の歴史のなかで、真っ先に結核に斃れて追悼号を出された同人ですが、詩人的資質・批判力のゆたかな人であったらしいのに単行本の業績は翻訳ばかりで自説の印象がはっきりしない。追悼号では潔癖症で孤高の人格を持したことが一様に取り上げられてゐますが、最晩年に伊東静雄との密な人間的交流があり、萩原葉子氏が『父・萩原朔太郎』の中で記してゐる昭和11年二・二六事件のあった大雪の日の出来事
(保田與重郎と連れ立って訪問した彼を朔太郎の老母が忌み嫌ふさま)などは、とりわけ強く印象に残ってゐます。第一書房を去るべく後釜を東大在学中の田中克己に打診してゐたことも、私は田中先生より直接聞いてをりましたが、キリスト教に親炙しリベラルな印象の強い辻野久憲が、『四季』よりはむしろ『コギト』の人々と交流が濃かった背景には、西欧文芸の翻訳ものに多くの誌面を割いた初期の高踏的な『コギト』の雰囲気が、伊藤整が追悼文で記してゐるやうに、潔癖で高尚なものを好む彼と性が合ってゐたからかもしれません。