(2024.05.20up�@update)
Back
���Ȃ����݁y�c�����ȁz�U���W
�u���������D�����l�v�@�@(�P�s�{�w���E�ÓT���w�S�W ��25��
������/���S踗��x����3-4p�@���a43�N�@�}�����[)
�@�S���Ȃ����O�D�B������͂�����y�ŁA�����킽���̂��Ƃ��C�ɂ����ĉ����������A���c���̌Ö{����(�Ƃ������珺�a�\�܁A�Z�N�̂���
�ɂ������Ȃ���)���������ł́u�����ʊӁv�𑗂��ĉ��������B����ɂ킽���́u�����ߐ搶���v�Ƃ����l���{�������ĎQ�サ���B�^�Ђ���u����
���v���o���Ƃ����\�����o�Ă�������A�����ɗ��Ǝv���Ă����ĎQ�������A���ł��������͖Y��Ă��܂������A�i�v�{���Ȃ킿�v�ł̎ʐ^�ł�������
���Ɏv���B(�O�\�N�߂��̔N���������Ă��邱�Ƃ䂦�A����邵�肦��Ǝv�����A�킽���͐����A�L���͂ɂ͎��M���Ȃ�)���̎��͎O�D���ǂ�����
�����������D���ɂȂ����̂������Ȃ��������A���c�������̑���̂قƂ�Ŏ�������ł����ł̂Ƃ��������ƁA�₤�K�v���Ȃ��悤�Ɏv���āA����
�������܂��ƂȂ�A���ƂȂ��Ă͎c�O�ł���B
�@�킽�����g�͊�g���ɂŏo���̎��R���l�Y�搶���߂́u�������v�ňꉞ�͑��Ƃ�������ɂȂ��Ă����B�������������w�j���u�`���Ă���ƁA���Ƃ�
��đ傻�ꂽ�b�ł���B���R�搶�̖͐���łɂȂ��Ă��邪�A�̗�ؕ^���搶�́u�����������v�₱����̐l�ƂȂ�ꂽ�z�g�Z�Y���m�́u������
�����߁v�ȂǍD�����߂��o�Ă���A��C�m�`���́u�������v�̑I�����Ȃ��Ȃ��悭�ł��Ă���B���������̏��搶�̖�⒐���݂ȓǂނƂǂ���������
�������āA���ƂłȂ��킽���Ȃǂ͓��f�������ł���B�����O�D����̖{���o�Ă���A�g��K���Y���m�́u�������`�v�̂悤�ɓ`�L�����˂��A
���̑I�߂������낤�Ǝv���B��߂��ɂ���O�D���g�̎��̑I�W������ƁA�u�R�ʏW�v�Ɂu���v�Ƃ�����̎�������A���̌���́u����Ɏ��́@�d��
�̗߁@���������Č��ɑ��v�ł���A�܂��u�����v��
���͈ꊪ�����W
�ʂ͈����S�ڊ`
�q�ɂ̖锼�̐Õ���
�n�ǂЂ̂��Ă߂��邩��
�@�Ƃ����̂ł���B�u�R�ʏW�v�̊��s�͏��a�\�N�̂��ƂŁA���e�͂����ނːM�B�̔��M������œ���ꂽ�S�ۂ��Ƃ����B�O�D���Ō�܂Ŏ����D�܂�
�����Ƃ͂悭�m���Ă������A�킽�������肠���ɂȂ�܂��̂��̔N�ɂ́A�_�o���S�����i�ŁA����f���A�������͒f�Ƃ��Ƃ��āA�悯�����������D����
�Ȃ�ꂽ�̂��ȁA�ȂǂƎ������܂Ȃ��킽���͓��Đ��ʂ�����B
�@�����������A�������̏W���ɑ�����������̎��͂킽���ɂ͂悭�킩��Ȃ����A�����~�߂鎍������A���̊Q������A���������~�߂��A�Ƃ����ӏ�
�ȂǁA�킽���̍D���ȃ^�o�R����ސ����āA����ɑς��Ȃ��B�������ǂ������̂��Ǝ��l�͂܂��������݂������̂ɂ������Ȃ��Ƒz�����āA�قُ܂�
�����Ȃ�B
�@�O�D����Ƃ̂��Ƃɂ���x���ǂ�ƁA�킽���̖K�˂����A��x�͍�����Ⴓ�������Ă����łŁA����������ŏo��ꂽ�̂ɂ́A�ܑ̂Ȃ��ĕ���
���B��x�߂̎��͂��k�������悤�Ɏv���B�����ł킽���̍D���ȓ������̎��́A����̃W���������A�z����ĂȂ�Ȃ��B���Ȃ킿���̎��D���ŁA
�����̐����ɂ͂��Ƃ��A�܂����Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă����������ɁA�u�q�ɖ����v�Ƃ������ƁA�u�q��ӂށv�Ƃ����������̎������邱��
�ł���B
�@�H�삳�D������������̏����u�m�q�t�`�v�ł́A�������͂Ȃ��u�𗧂Ă����A�q�ǂ��ւ̈���̂������Ő�l�ɂȂ�@����������A�Ƃ�����
�Ȃ��Ă���B���̘b�Ɠ�������\���Ƃ�̂͂��₷����߂�ꂽ���A���͂����ȁA�q�ւ̈��͂���ɋ��������ȂɂȂ������Ɏv����̂��������ŁA����
�ɂ���ׂ�ƍȎq�ƕʋ��ł����O�D����́A�����Ƃ��\�ʓI�ɂ͓�������苭�������悤�ȋC������B�Ƃ��낪���͎O�D����ɂ��u�܁v�Ƃ�����������
�āA���܂ꂽ����̌䒷�j�̗܂ɁA���Ƃ��Ă̋���������̂��Ă����łł���B�������Č����������ŁA�Ђ���Ƃ����瓩������������̂��̐�y��
���Ƃ́A��肾�����肪�Ȃ��B
�@�������̓��{���w�ւ̉e���͐��쐴�F���m���A���́u�������v�̉���ŁA�Ȗ��ɏ����Ă����łŁA��Íc�q�ⓡ���F��(���܂���)�ɂ��łɖ͕킳
��A�m�ԁA���Ȃǂ݂Ȃ��̎��l�����������Ƃ����炩�ɂ���Ă���B���Ē����ł͂ǂ����������ɂ��ẮA�킽�������āu���y�V�v(�W�p�Њ�
�s)�ŁA���̑��L���X�A�y���ƍl����ꂽ���l�ɂ��āA�Ȃ��������ւ̌X�|�������邱�Ƃ��ȒP�ɂ��邵���B���Ƃ�肱��ɐ悾���ہA�Ѝ_�R�A��
�����A����ɑ厍�l�m��A���������������ɑ��Ă͓��������Ă���B���Ƃ��Η����́u�Õ��v�̑�O�\���u�A�q�����ցv�Ƃ������́A�u�ꂽ�ѓ���
���ɉ����A��t�A�������u�v�Ƃ�����ŏI���Ă���B�������́u���Ԍ��L�v�ɂ���Ă��邱�Ƃ����炩�ł���B�勫���Ԍ��͂܂��u�aḎ���ʓ�
�ȁv�Ƃ������ɂ��r�����Ă��邪�A�����ł͎���j��Ḗ^�ɂ���ĉ̂��Ă���ʓ��Ƃ����y�n���A���Ԍ���肳��ɂ悢�Ƃ��낾�Ƃ����āA������
�̂��߂ɁA���Ԍ�������������B�������������ē��Ԍ����o��悤�ł́A�����̓������ǂ͋^���Ȃ����ƂƂȂ�B
�@�Ăѐ��씎�m�ɂ��A���l�̓����������͏����̉��тɂ͂��܂�R�ł���B���������łɗ��̏������q�J��(�u���I�v�̕Ҏ�)���������̓`����
���A�܂��������W�̏��������Ă���̂ŁA�����̐��q�͂��Ȃ炸�������тɂ�����Ƃ͂����Ȃ��B�Ƃ܂�m�Ԃ��u�m���v�����E�ɒu�������Ƃ��A������
�g�ӂɂ��������W�����������ƂƎv����B�u�������k���N�v�Ƃ������Ȃǂ́u���ߎ��d��v�Ƃ�����ł͂��܂�A�k�^�����ɂ������Ăق߂Ă�
��B���̗k�^�̌o���͂킩��Ȃ����A���l���ׂĂɓ������̓`�L��i���悭�m���Ă������Ƃ����炩�ł���B�܂��u�����ɐl�Y�v�Ƃ�������
���A�����͐��q����l���Ƃ��Ďӈ��������A����Ɠ������B�����Ă����̂��A�꒩�A���@�ɗp�����āA��ނ��C���������A�ӊO�ɂ��ނ����ď\
�N�ɂȂ�B���͂�Ăїp������]�݂��Ȃ�����B�����邪�A���x�͂��̌Â��̓����̒n���镐�˂ɂ킽����K�˂ĉ�����A����ł���ƁA�܂���
�Ԍ���炤�C����f�I���Ă���B���������Ԍ��ł̍ĉ�͏]��(���Ƃ��̎q)���܂ɑ��������ɂ�������B
�@�킪�t�����t�v�搶�̏����u�������v�ł́A�����͓V�ɓo���Ă䂭���ƂƂȂ��Ă��邪�A��������́u�V�v�͓��Ԍ��ł������悤�ł���B�����Ɩ���
�ɓ��������q��\�킵�������̎��́u�Y���A溧�z�v�ŁA�u���߂͓��������A�ܖ��̏t��m�炸�v�ɂ͂��܂�A���̋Ղɂ͌������炸�A�����h���̂ɓ���
��p���A�����̐����k�̑��̉��ŁA���Â̐l�Ǝ���������Ă��邱�Ƃ��L���A�u������̎����I��(�������̏Z�܂��̂�������)�ɓ���A�ꌩ���ĕ���
�̐e(�펞�̂�����)�����v�Ƃ����Ă���B���ƕ��������Ƃ��������ɂƂ��āA�������͎�����قɂ����m�ȂƂ����悤�B(����勳��)
���Ȃ݂ɕ����̊������ȉ��Ɍf����B
�@�u�Õ��v��O�\���u�A�q�����ցv
�A�q����萁A�s�s���\�߁B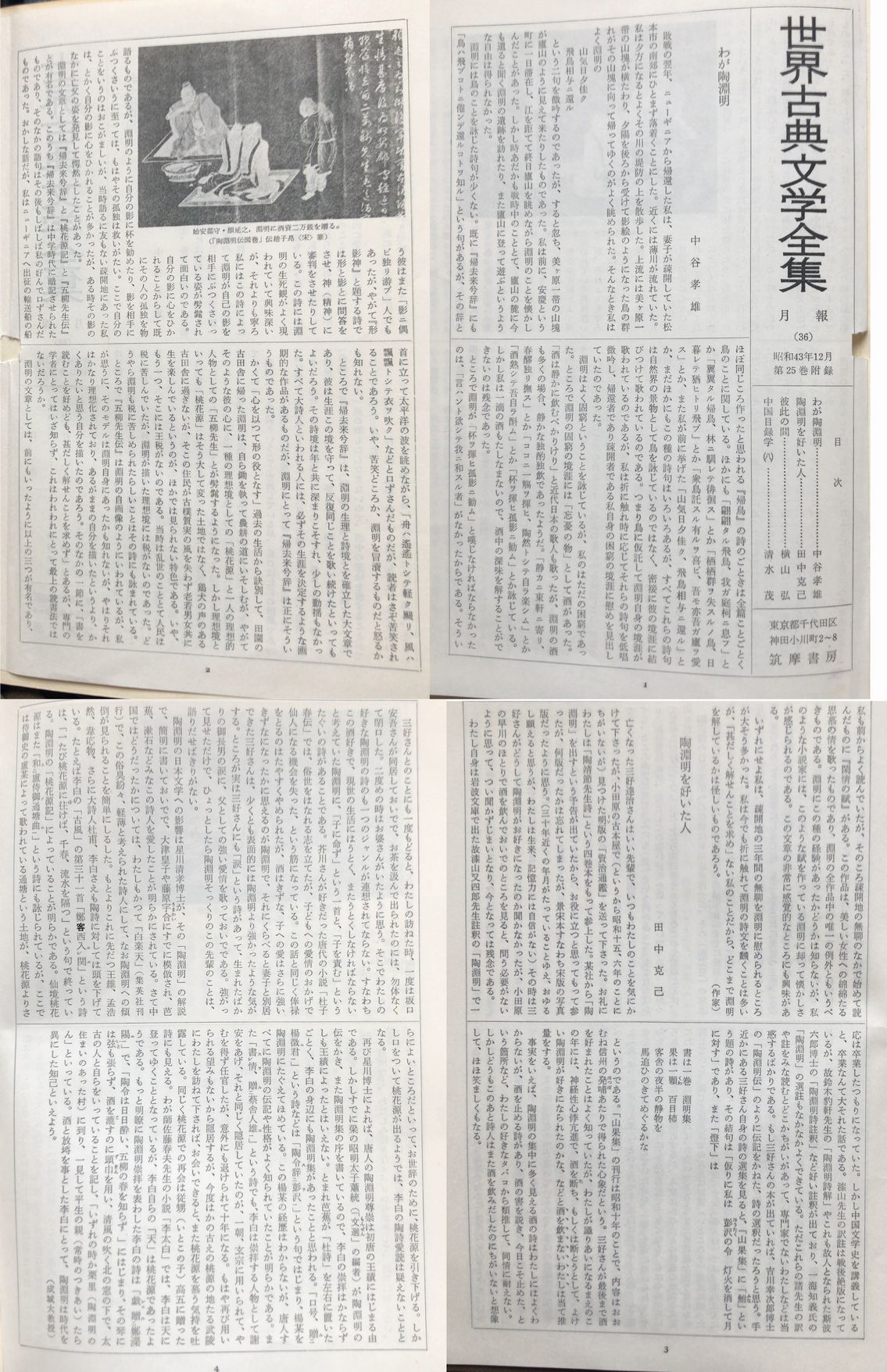
���n�؎R�N�A�����������B
�����M�r�N�A���N�c�����B
�`�l�����H�A�ᛢ����B
�ꉝ���Ԍ��A��t�u�����B
�@�u�A�q�A���̂���萂ɓ���v
�A�q�A���̂����(���J��)�ɓ���A�s���s�������߂ޔ\�͂��B
���n�؎R�̌N�A���Ј��ӕ���(����)�̗��B
�u�����M�r�N(�u���������ɔ䂷)�Ɉ��A���N�A�c��(�n�c��ɔ䂷)�͎�����v�ƁB
�`�l�A���Ј��ЂĞH���A�Ⴊ��(�ő�)����ׂ��ƁB
�ꂽ�ѓ��Ԍ��ɉ����A��t�A�������u�B
�@�u�aḎ���ʓ��ȁv
�N�֒ʓ��D�A�ʓ������B
�ʓ��݉��|�A���ݐq�z���B
���f�]�]�k�����A��鷴�|�|�ڍ���B
�Ζ咆�Е��Ώo�A�S����K�Ɖ_���B
���|��Q���މ��A���D���̎���B
�����s�����A�o��ㅒʓ��B
�Y粐������f���A�ʗL���ь����Y�B
�s����K�K�z�H�A�^�����ˏt�ɗ��B
�`�l雞�����ԗ��A����ʓ�����㵁B
�ʓ��s�E�ʁA�\����等�B
�����S���ˁA���L�꒹�n�V�ҁB
���o�R���s�q�A�l粋�|�H�ߋN�B
���ᔒ��]���́A�Ԑ��_���g�f�g�B
�������s���m���A�J�m�����َ����B
�@�uḎ���̒ʓ��Ȃɘa���v
�N�͌ւ�A�ʓ��̍D�����A�ʓ��͖��ɏ���ƁB
�ʓ��A���|�ɂ��݂�A�����q�z�̐��ɍ݂�B
���f�͛]�]�Ƃ��ĉ����ɝk��A��鷴�͙|�|�ɍ�����ڂ܂�B
�Ζ�͒��Ђ��ĕ��Ώo�ŁA�S��̋��K�A�_�����Ƃ��B
���|�̟�Q�Ȃ�ނ̉��A���D�̋��́A���ɔ�́B
���Ј��ӂ����Ў��炸�A�o�v�ɂ͒ʓ���ㅂ��B
�Y粂̐����A�f�������ɁA�ʂɎт🯂ӌ��̏��Y�L��B
���K���s��ᶂ����K�A�z(����)���H�Ȃ�A�^�ӂ͐��ꕐ�˂̏t�ɂ̗��ꂩ�ƁB
�`�l��雞���A���Ԃ̗��A���ɒʓ��ɔ䂷���(����:������)㵂����߂���Ƃ��B
�ʓ��A��(�킩)���ɔE�т��A�\���ы����ċソ��等�(�p�j)�B
��܉����Ɉ��ЂĐS�͛߂��˂ЁA�����꒹�̓V�n��҂�L��B
���͐R�ɏo�ōs�q�𑗂�A�l粂̋�|�A�H�߂��N���B
(�^���̖���)����Ⴕ�Đ��͂�]�݁A�_����Ԑ����āA�f�g��g���B
�������s(���c�邩�瓦��B�����Ă)���m�̓��A�J�����َ̞�������m���B
�@�u���j���k���N�v
����熜d�V�A���������m�B
��q���m�B�A�N�o�ÐlꎁB
�_�痯�O�فA�V���~���D�B
�s�m�k���N�A��晚��萐��B
�@�u���j�A�k���N�ɑ���v
���߂͜d�V��熂��A�����͘��m�ɓ���B
��A���m�B��q�ʂ�ɁA�N�͌Ðl��ꎂ��B
�_�炵�ĒO�قɗ��܂���A�V���A(�M������������)���D���~���B
�m�炸�A�k���N(�k�k�ɂ��䂹����M����)�A��晚�A萐��Ɍ��ӂ��B
�@�u�����̐l�Y�v
�����ӑ����A���W���R��B
�^���˕ɉ_�A吳�̝А����B
�b�������N�A�k�Έ��t���B
�]�������l�A�O躙b��|�B
����������A���i���S���B
�����퉽烁A��墐����l�B
�꒩�������A�\�ڋq�����B
�Ҍ��i��萁A�E�l�������B
�c�u��l�]�A�����J�����B
���K��夔���A�����������B
�|�C�������A���R�̖F蓀�B
��������A虛���J�I���B
�ՎӉ_�i�t�A�S笓V�n�v�B
�v�q�����ˁA�������N�_�B
�w�I�U�Z翮�A�s���v��鶱�B
���s�܌Ξ��A���������z�B
���ގq�˟A�p���ɗP���B
�k��q���B�A��A�s�����B
�痢����A�ݗ��꒷�́B
黃�ߕs���ҁA�����ޏD���B
�M���n���A�R�|����g�B
�����ΌÐl�A�Ս����V�a�B
�Վ��c�����A搔�w�q�P�@�B
�ʗ��𑊖K�A��ݕ��ˑ��B
�@�u����������q�l�Y(�q�l����Y)�ɑ���v
���č����Ƃ��ӑ���(�ӈ�)�A�W���g�ӓ��R(�H��)�̖�B
(�ޏ��B��)�^���͕ɉ_���˂ЁA���̂�������ЂB
�b������(�l��)�Ɉ����ċN��A�k�A�t��(�S��)�����B
�]���������̐l�������A�O躂ɔ�|�����b�ӁB
�����̎�ɑ�������A���ċ��S�̌���i����B
�����A��ɉ���烂��A��墁A���əl�𐬂��B
�꒩�A����������A�\�ځA�����ɋq����B��槌��ɑ����ė��̒n[�{��ɋ[�ւ����]�ɉ�����
�Ҍ��A��萂ɖi���A�l���E���Đ������炵�ށB
�c�u�A�l�]��Ⴌ�A�����A�������J���B
���K�A夔��(���b)�A�����A�����ɖ����B
�C��|�܂ɂ��Ė��������߁A�R�𗽂��ŖF蓀���̂��B
(�������Ȃ��玄��)���ÁA����̌�����虛�����J�I�̉��ӂ��B�����݂������Đi��
�Ղ͉_�i�̊t�Ɏӂ��A�S�͓V�n���v��笂͂�B
�v�q(�̂��Ȃ���)�����̍ˁA�����A�����N���_����B
�w�I�A�Z翮��U�ЁA���Ȃ炸���ē�鶱������v�ӁB
��A�s�Ɍ܌ɞ������A�����A���ɕ��z����B������̂₤�ɏ������炤
���Ɏq�˂̟ɒނ�A(�B�Ҍ����̂��Ƃ�)�p���͖ɂƂ���(������)�P�ّ�������B
�k��ɋq��(����)�͉B������ӁA��A(������̜��)�͉�����ɑ��炸�B
�痢�A�ꂽ�ю�(������)����炵�āA�ݗ��A�꒷�̂���ǁB
(��l�����)黃�߁A�����҂炸�A�����A�D�ӂ��މ���B
�M���n�Â̌��ɕ��сA�R�͓���̔g�ɓ|�܂ƂȂ�B
���ɓ�����Ðl(����J�Ӌ���)���ӁA(���q�̂��Ƃ�)���ɗՂ�œV�a��B��
�Վ��A�c���̒��A�w��搔�����P�@��q����B
�ʗ��A���ЖK�ӂ�������ƂȂ�A(���)��ɕ��˂ɍ݂邱�Ƒ�����ׂ��B
�@�u�E���A溧�z�v
���ߓ������A�s�m�ܖ��t�B
�f�Ֆ{�����A����p���ЁB
�����k�����A����㺍c�l�B
������溧���A�ꌩ�����e�B
�@�u�Y��ɓA溧�z�ɑ���v
���ߓ������ЁA�ܖ��̏t��m�炸�B
�f�ՁA�{�ƌ������A���������Ɋ��Ђ�p�ӁB
�����k���̉��A����u㺍c�̐l�v�ƈ��ӁB
����̎����I���ɓ����A�ꌩ�A�����̐e���݂��Ȃ���B
�܂��Q�l�ɓ������ڂ̒��J�F�Y�ɂ��u�킪�������v���f����B
(���J�F�Y�ɂ́w�������i�V�I���l�p���j�x�앗���[, 1948.6 204p�A�w�킪�������x�}�����[, 1974.12 281p������B)
�u�킪�������v�@�@�@���J�F�Y
�@�s��̗��N�A�j���[�M�j�A����A�҂������́A�Ȏq���a�J���Ă������{�s�̓�x�ɂЂƂ܂����������Ƃɂ����B�߂��ɂ͔��삪����Ă����B���͗[��
�ɂȂ�Ƃ悭���̐�̒�h�̏���U�������B�㗬�ɂ͔�������т̎R�������A�[�z����납��ĉe�G�̂悤�ɂȂ������̌Q�ꂪ���̎R���
�����ċA���Ă䂭�̂��悭���߂�ꂽ�B����ȂƂ����͂悭������
�R�C���[���N
���^�j�҃�
�@�Ƃ���������Ⴗ��̂ł��������A����ƍ����A��������т̎R�I�R�̂悤�Ɍ����ė����肵�����̂ł������B���͑O�ɁA���c�Ƃ������Ɉ��
�؍݂��A�]�����ĂďI���I�R�߂Ȃ��畣���̂��Ƃ����������Ƃ��������B�����������������펞���̂��ƂƂāA�I�R�̘[�ɍ������ƕ�������
�̈�Ղ�K�ꂽ��A�܂��I�R�ɓo���ėV�ԂƂ����悤�Ȏ��R�͓����Ȃ������B
�@�����ɂ͒��̂��Ƃ��r�������傪�����Ȃ��B���Ɂw�A�����a���x�ɂ��u���n��u�R�g�j�����f�҃��R�g���m���v�Ƃ����傪���邪�A���̎��Ƃقړ���
���������Ǝv����w�A���x�̎��̂��Ƃ��͑S�т��Ƃ��Ƃ����̂��ƂɊւ��Ă���B�ق��ɂ��u���ǃ^���A��K��h�j���t�v�Ƃ��u�����^���A
���A�уj�郌�e�p�j�X�v�Ƃ��u�����Q�����X���m���A���郌�e�P�q�g����u�v�Ƃ��u�O�����X���L������r�A�Ⴢ���Ⴊ�I�����X�v�Ƃ��A�܂������O��
�������u�R�C���[���N�A���^��҃��v�Ƃ��A�܂��ق��ɂ����̎�̎���͂��낢�날�邪�A���ׂĂ����̎���͎��R�E�̌i���Ƃ��Ē����r���Ă�
��̂ł͂Ȃ��A���ڂɔނ̋��U�Ɍ��т��ĉ̂��Ă���̂ł���B�܂蒹�ɉ������ĕ������g�̋��U���̂��Ă���̂ł��邪�A���͐܂ɐG�ꎞ��
�����Ă����̎����Ꮵ���Ⴕ�A�A�Ҏ҂ł���a�J�҂ł��鎄���g�̍����̋��U�ɈԂ߂����o���Ă����̂ł������B
�@�����͂悭�ŋ��Ƃ������Ƃ��r���Ă��邪�A���̂͂����̍����ł������B�Ƃ���ŕ����̌ŋ��̋��U�ɂ́u�Y�J�̕��v�Ƃ��Ď����������B�u���͐Â�
�Ɉ��ނׂ��肯��v�Ƌߑ���{�̉̐l���̂������A�����̎��������̏ꍇ�A�Â��ȓƎޓƈ��ł������悤���B�u�ÃJ�j�����j���A�t�Гƃ����X�v�Ƃ�
�u�R�R�j���[�����q�A���R�g�V�e�����y�V���v�Ƃ��u���n�V�e�Ꭹ��酙���v�Ƃ��u�t�����ƌlje�j�����v�Ƃ��r���Ă���B���������͈�H�̎���������
�܂Ȃ��̂ŁA�𒆂̐[���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��͎̂c�O�ł������B
�@�Ƃ���ŕ������u�t�����q�lje�j�����v�ƒQ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂́A�u���n���g�~�V�e��j�a�X���ҁv���Ȃ���������ł���B���������ނ͂�
���u�e�j��r�ƃ����u�v�l�ł����������A�₪�āw�`�e�_�x�Ƒ肷�鎍�ł͌`�Ɖe�Ƃɖⓚ�������A�_(���_)�ɐR�����������肵�Ă���B���̎��ɂ�
�����̐����ς��悭���Ă��ċ����[�����A��������J�뎄�ɂ͂��̎��ɂ���ĕ��������Ȃ̉e��ɂԂ��������Ă���p���霂���Ėʔ�����
�ł���B�����̉e�ɐS���Ђ���邱�Ƃ��炵�Ċ��ɂ��̐l�̌ǓƂ����̂ł��邪�A�����̂悤�Ɏ����̉e�ɔt�����߂���A�e��ɂԂ�����
���Ɏ����ẮA���͂₻�̌ǓƂ͋~���������B�����Ŏ����̂��Ƃ������̂͂������܂������A�������ɗF���Ȃ��a�J�n�ɂ��������́A�Ƃ��������̉e
�ɐS���Ђ���邱�Ƃ������������A���鎞���̉e�̂Ȃ��ɖS���̎p�����Ĝ��R�Ƃ������Ƃ��������B
�@�����̕��͂Ƃ��Ắw�A�����a���x�Ɓw���Ԍ��L�x�Ɓw�ܖ��搶�`�x�Ƃ��L���ł���B���̂����w�A�����a���x�͒��w����ɈËL������ꂽ���̂ł�
��A���̂Ȃ��̌��͂��̌�������Ύ��̍D��Ō��������̂ł������B�������Șb�����A���̓j���[�M�j�A�֏o���̗A���D�̑D��ɗ����đ����m
�̔g�߂Ȃ���A�u�M�A�ꡃg�V�e�y�N颺���A���n�G�G�g�V�e�߃����N�v�Ȃǂƌ��������̂����A�ǎ҂͂��������邱�Ƃł��낤�B����A��
�ǂ��납�A������`瀆������̂��Ɠ{�邩���m��Ȃ��B
�@�Ƃ���Łw�A�����a���x�́A�����̐����Ǝ����Ƃ��m�������啶�͂ł���A�ނ͐��U���̋�������āA�����������Ƃ��̂��������Ƃ����Ă��悢����
���B���̎����͔N�Ƌ��ɐ[�܂肱������A�����̓��h���Ȃ������B���ׂđ厍�l�Ƃ�����l�ɂ́A�K�����̐��U�����肷��悤�ȉ���I�ȍ�i������
���̂����A�����ɂƂ��āw�A�����a���x�͐��ɂ����������̂ł������B
�@�����āu�S���ȂČ`�̖��ƂȂ��v�ߋ��̐������猍�ʂ��āA�c���̌Óc�ɂɋA���������́A���珛�������Ĕ_�k�̓��ɂ������ނ��A�₪�Ă��̂悤
�Ȕނ̐S�ɁA���̗��z���Ƃ��Ắu���Ԍ��v�ƈ�l�̗��z�I�l���Ƃ��Ắu�ܖ��搶�v�Ƃ��霂���悤�ɂȂ����B���������z���Ƃ����Ă��u����
���v�͂����債�ĕς����y�n�ł͂Ȃ��A�{���̐��̂���Óc�ɂɉ߂��Ȃ����A�����̏Z�����Þ������̕������킸�V��j���������y����ł���Ƃ�����
���A�ق��ł͌����Ȃ����F�ł���B����A������A�����ɂ͉��ł��Ȃ��̂ł���B�����͗����̂��ƂƂĐl���͐łɋꂵ��ł������A�������`����
���z���ɂ͐ł��Ȃ��̂ł������B�ǂ���畣�����łɋꂵ�߂�ꂽ�炵�����Ƃ͂��̎��ɂ��r�܂�Ă���B
�@�Ƃ���Łw�ܖ��搶�`�x�͕����̎��摜�̂悤�ɂ����Ă��邪�A�����v���ɁA���̃��f���͕������g�ɂ����������m��Ȃ����A��͂肻��͂��Ȃ�
���z������Ă���A���邪�܂܂̎�����`�����Ƃ������A�������肽���Ǝv��������`�����̂ł��낤�B���̂Ȃ��̈�߂ɁA�u����ǂނ��Ƃ��D�߂�
���A�r�����������Ƃ����߂��v�Ƃ��邪�A���̊w�҂ɂƂ��Ă͂����m�炸�A����͂����ɂƂ��čŏ�̓Ǐ��@�ł͂Ȃ����낤���B
�@�����̕��͂Ƃ��ẮA�O�ɂ��������悤�Ɉȏ�̎O���L���ł���A�����O����悭�ǂ�ł������A���̂���a�J�n�̖��ւ̂Ȃ��Ŏn�߂ēǂ���
�Ɂw�Տ�̕��x������B���̍�i�́A�����������ւ̖ȖȂ���v��̏���̂������̂ł���A�����̑S��i���̗B��̗�O�Ƃ������ׂ����̂ł���B��
���ɂ��̎�̌o�������������ǂ����͒m��Ȃ����A���̂悤�ȏ����Ƃɂ́A���̂悤�ȕ�������Ă��镣���ɋp���ĉ�����������������̂ł���B��
�̕��͂̔��Ɋ��o�I�ȂƂ���ɂ�����������B
�@������ɂ��掄�́A�a�J�n�̎O�N�Ԃ̖��ւ��ɈԂ߂���Ƃ��낪�傻�����������B���͍��ł��܂ɐG��ĕ����̎������ʂ����Ƃ͑������A�u�r
�����������Ƃ����߁v�Ȃ����̂��Ƃ�����A�ǂ��܂ŕ����������Ă��邩�͉��������̂ł��낤�B(���)
Back