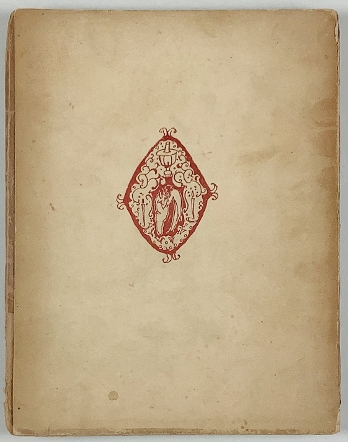
詩集 『月の出る町』
春山行夫 第2詩集
大正13年7月5日 地上社出版部(名古屋)刊
上製函 18cm 79p \1.00
装幀:松下春雄
序に代へて
――生ひ立ちの記から――
私はいつも竹籔と風車のことをかんがへると、詩が書ける。だが風車それ自身のことは、いまだ私の詩には現れてゐない。思ふに、風車と私と私自身とは餘程距離があるらしい。
元來、私の生れたのはうらぶれた士族町で、そこにはたくさんの竹籔があつて、私の生れた家にも裏に竹籔があつた。
いつの頃、私がそれを知つたのかは知らない、が私の一家は、私が生まれた年に、その家からものの三十歩とはない隣地へ引越したと言ふ。
それ故、そこには竹籔がなかつた。がその代り三方を圍んだ桑畑と大きな榎の茂つた廣場があつた。
それで私のこころおぼえでは、幼ない時、私は竹籔が好きで、いつも附近の竹籔へ遊びに行つたものだつた。また憶ひ出す、それらは私自身によつて柳の聳えた竹籔や、幽霊の出る竹籔や、雀の多い竹籔や、狐の隠れてゐる竹籔などと呼ばれてゐたことを。そして私はかづ多いそれらのうち私が生れたと言ふ家の裏の竹籔がいちばん好きであつた。
それで私の少年時代は随分さびしかつた。
附近に家もあまりなかつたので、友達もなかつた。そのうちの数人は薄幸にも死んでいつた。私はいつもうすら寒い蜜柑の青葉の下で、竹の葉の搖れる音に耳を澄しながら、いろんなことを考へてゐた。
そしてそれは私に、さびしいと言ふことをなんとも思はない性質にしてしまつた。
私は竹籔のことを考へる、各々の竹籔がそのなかにいかにたくさんの物語を私のために語らうとしてゐるやうであることを。
そして、それにもかかはらず、私の、ものに無関心であることについては、私は竹一本の成長についても、私自身の成長と同じやうに、いつもぼんやりとしたものより知らないのである。
それに較べると風車のことでは、私自身がよりはつきりしてない。住んでゐた町から暫くはづれの方にゆくと、かなり激しい傾斜地がある。 それは恐らく一里ぐらゐは一直線につづいてゐるつもりである。
その傾斜地の上には随分異國的なものがあつた。
私は不幸にして、その上を通つたことはないが、傾斜地の下はしばしば通つた。
このごろはすつかり異つてしまつたが、その傾斜地のだんだん畑には、棉の畑や麻の畑があつた。
それから、坂の上の通りの裏にあたるあたりには白壁の師範学校があつた。三階建の和蘭商館があつた。黒塗の倉庫があつた。
そして、私の記憶に新なことには、そこにたつたこの都市(まち)に一つぎりの古風な風車があつた。
だが、私の言ふ風車とはその風車ではないらしい。それには私は餘り興味を持たないから。勿論、近來その附近の風致がひどくくづされて、 私がそこに行くことを怖れてゐると言ふ理由もあるが…………
私は結局、かやうなことに、いつもぼんやりすぎるのであらう。
私は、べつにその竹籔を、風車を思ふことによつて、印象を記憶を喚び起すのに神経質になることは出來ないから、またそれ故、いつまでも、ぼんやりした世界を苦労なしに考へることが出來る理由でもあらう。
私が詩を書くのは、そんな状態に於いてである。
それ故、私はいつも詩を書かうと思つて書いたことはない。従つて、詩を書くために特別の苦心などをしたこともない。私はそれゆえ、私のもつとも氣安げな時、さうだ、いちばん心の純粋な時、樂しくはればれて筆をとるのである。
私にとつては藝術と言ふものは、平凡な常識である。
由來、私の一家の風が示したものは、藝術的生活とか生活的藝術とかの異論を別にして、藝術と生活とが一致した生活であつた。それ故、私の一家は對社會とは没交渉な生活をしてたらしい。
私の父は、特に氣質の上にそうしたものが甚だしかつたらしい。
私は私が季(すえ)の子であつた故だらう、私は私自身のぼんやりしたもので考へてゐる外、私の家系のこと、父自身のこと、母自身のことに就いてはちつとも知らない。
あるひは幼ない時に聞かされたことがあつたかも知れない、が思ふにそれらのものは、父母が私に與へる最上のものではない。
寧ろ私は、父母が與へるに、世にも美しい生活をもつてしたことを幸福とする。
それ故、私はいつもそれをぼんやりと考へることに満足してゐる。
何故なら、さうすることが、私のいちばん好むところであり、恐らくは父母にとつても差支へないものであらうから。また、それほど、勝手に私の思ひどほりになるものも外にない故である。
私の知つてゐる範圍では、その頃、私の家の業であつた陶器に絵をつけると言ふ仕事は、いまとは思ひもよらない藝術的な仕事であつたらしい。
それで、職人と言ふものは随分苦心もしたし、随つて、随分立派な仕事をしたものであつた。
私の家にも幾人かのさうした人がゐた。
彼等は殆んどがそうであつたが、遠い山國から、十二三歳から甘歳までを年期として、総て都市へと奉公に來たものであつた。彼等は毎日陶土の出る山や、陶土を挽く水車小舎や、または赭い陶器竈の煙の下で、自分たちの手でつくられる陶器に、たつた一本の筆で自由に美しい繪を描いて生活すると言ふことは、さう言ふことを修業するために都市へ出ている師匠に就くと言ふことは、よほど立派なことだとかんがへてゐたのであつた。
私の生活は、さうした人達の雰圍氣のなかにあつた。
私は彼等が私を大切にし、また厳格で、しかも親しみ深い彼等自身の仕事をいかに忠実に、満足に果してゐたかを知つてゐる。
事實、彼等はかくして、彼等の師匠の知るすべてのことを習得し、立派な腕前となるばかりでなく、彼等自身また若い弟子を養ふに足る人格をこしらへるのである。
そして私は何故に必要以外にこんなことを書かうとするのか、實に、私の信じるところに依れば、かくして彼等のもつ生活がいかなる外の立派な生活に比しても劣らなく立派なものであるかと言ふことを言ひたいからである。
また私は、それがつひには私の一家の幸福を破壊したところの、近代の産業組織の罪悪を、また彼等をして人間以下へと堕しめてゆく苦痛の生活を知るゆえである。
いかにPrimitif(プリミチフ:※原始的)な人格の愛らしかつたこと、だが、それらは彼等とともにあれ、結局、私はそれらのものを今にかへさうとは思はない。
それは私が芭蕉について微笑するがごときものである。
私は私の生活をもつ。彼等と違つた意味で、私は私の信じる人格の成長にふさはしい生活に向ふのである。
かくて、私は私の詩に就いては、詩の古典のことも考へたくはない。また近代のさまざまの詩風についても同じである。
ただ、かかるが故に、私は私の詩に特別ななにものをも望まない、世に言ふ藝道とか匠氣とか言ふものを崇ばない、また私は粗雜な、真實のないものを疎んするものである。
私の父はいつも細い(それは何の毛でこしらへたものかは知らない)で竹林をさらさらと書いた。
それは父が幼ない私達に書き與へたものであるが、或日、私は父の所有(もつ)てゐた明治初年の和蘭陶器を見たことがあつてから(それは白耳義(※ベルギー)のものであつたかも知らない)私は異國のもののもつ不思義な雰圍氣を樂しむことを知つた。
私の中にある一つの世界は、かかるひまに私の裡に育まれたものかも知らない。私が風車を思ひ、美しい海を思ふのも、じつはそんなところにあるのかも知らない。
私の一家は、その後、それはもう数年以前のことになるが、彼等の新らしい田舎へとかへつてしまつた。そこは私がかりに故郷と呼んでゐるところである。
そして私は再び私の本來の孤獨に残された。私の詩の生活はそこに始まつたのである。
私はいつもその故郷を思ふ。そして私はそれを思ふとき、ふしぎに大きな原始の力をそのままに、根強く伸びた竹籔をおもふ。そこに幸福をとりかへした父母をおもふ。そして私は、私のなかに遠のいてゆく一つの世界を、あのやうに美しい世界をひたすらに歌ふのである。
春山行夫
(跋文)春山行夫と僕
「月の出る町」によせる
僕が春山行夫を知つたのは、そんなに昔のことではない。だのに僕らは生れおちるとから離ればなれに育てられ、生活してきた二人の兄弟が二十幾年の後、奇遇したかの心情を経験することになつた。
その頃、名古屋で起した宗教革新運動に興味をうしなひかけてゐた僕は、同志がまたそれぞれ宗教中心といふことに不自由を感じてゐることを知つたので、二號まで出した雜誌も廢刊にし、「宗教改革同盟」といふものも解散することにした。
その頃、福士幸次郎(人も知るように彼と僕とは兄弟關係に立つ。)が名古屋での詩歌講演のために來名した。(一九二二年二月のことだ。)
彼は「樂園」の創刊號を持つてゐた。(この若さそのものの詩中心の雜誌は僕が早稲田の文科にゐた頃、即ち四五年も前から計畫してゐてやつと、しかも予期せずに、その顔を見るものであつた。それを兄が弟にずつと昔に約束したものを弟が忘れた頃、不意に興へて喜ばせる快感から、福士はさうしたのであつた。)
僕の情熱は再び詩の世界に燃えたつた。僕が春山を知つたのは、これ以後三四ヶ月を過ぎてからのことである。
その頃、春山は、名古屋のある會社に勤めの傍ら、彼の竹馬の友、井口蕉花君ともに「赤い花」といふ雜誌を出してゐた。
ところが間もなく「樂園」も「赤い花」もともに廢刊か休刊かになつてしまつた。その春、高木斐瑳雄君から話があり、「赤い花」の連中と一諸に雜誌(※『青騎士』)を始めようと思つてゐるが加はつてくれないかといふのだ。
──僕と春山との友情・生活(フラテエツア・ヴイヴオ)はこれから始まつた。
春山は會社のかへりに、殆んど毎日のように、僕の東新町の假寓(いまもこれを書いてある)の扉をたたいた。
彼の姿が見えない夜は、僕が出かけて行つた。あのいかめしくたち並んでゐるブルヂョアの住宅におしつぶされさうな一間きりの裏座敷へ。
そしてこのどちらかの部屋で僕等は語りあつた。──英佛の象徴詩を、東洋の古典詩歌を。彼の書齋のボンボン時計が夜中の二時を打つたりして驚ろいて立ち上つたこともあつた。(が彼のドコか異國的な、それでゐて、祖先伝來と思はれるやうなその時計は、いつも二時間位はすすんでゐた。そして今もすすんでゐる。)
彼は風呂手拭を振り乍ら、またいつも風呂屋の前まで、おくつてきてくれた。あやつり人形の鋒鎗持ちの格好で(願はくば彼から一切の和服をとり去ることを!)。
人通りの少ない電車道から入つた、廣い屋敷町の月の出は変つてゐた。
その月は黄ろく疲れた顔を出した。どこか、文明のおとぎばなしのお姫様を思はせた。
“gisimilsalvirinoelirantaeltombo"(※それ[月]は墓から蘇った女性のようだ)などと「サロメ」の文句をエスペラントで口づさんでみたこともあつた。
が、春山はその月を僕と同じように眺めたのか、どうかは知らない。ともかくかかる月の出る町で、彼の隣りの門前で僕がウリーニ(※小便)したことだけは忘れてない筈だ。(かかる町ではまさに噴泉の趣興をそへる!)そして彼は僕にその家がポリつイステエヨ、マーストロ(※警察署長)の屋敷であることを警告したのだから。
彼の洋服姿が脇に二三冊の詩集をかかえて、廣小路のページメントの上をやや背をこめて足早に通りすぎるさまを見たものは、彼の脊高がいかに調和的な映畫の主題であるかを思ふであらう。
かかるとき、まさに彼のエキゾチシズムは、彼のボンボン時計の響とは全く異つた響と速度とを起す!
そしてまた折々僕とともに歩くのだが、僕の黒いトンビに山高帽姿(これはポオを失神させたレエヴン(※Raven大鴉)である)は彼の文明のものの姿としていかに野人くさく見えることであらう。彼の言ふがごとく村長の赤毛布ぶりといふところであらう。
しかり、彼は文明人型であり、僕は野蠻人型である。「青騎士」同人のすすめによつて僕は五六年間の詩の一部を一九二二年十月に發表したのだが(※『晴天』)、彼は僕が五六年の間に開拓した詩歌の分野を僅か五六ヶ月で自分のものにしてしまつた。そして彼の豊かな天分は、なほ彼獨自の世界をあまた探索、開墾しつつある。
彼こそはまさに出藍の天才であらう。が僕はダヴィンチがラファエルに對して抱いた嘆をいままたくりかへしはしない。むしろよき才を弟に持つた兄の喜びが僕の胸をしめてゐる。
ただ彼があまりに文明人であることによつて、彼の將來に多少の杞憂を抱きつつ、一世紀にごくまれにあらはれることをゆるされるであらう天才の選詩集を世におくることに、誇りと喜びを持つものである。
一九二四年三月十六日
日曜日の晝、田舎の家でかきをはる
佐藤一英
――生ひ立ちの記から――
私はいつも竹籔と風車のことをかんがへると、詩が書ける。だが風車それ自身のことは、いまだ私の詩には現れてゐない。思ふに、風車と私と私自身とは餘程距離があるらしい。
元來、私の生れたのはうらぶれた士族町で、そこにはたくさんの竹籔があつて、私の生れた家にも裏に竹籔があつた。
いつの頃、私がそれを知つたのかは知らない、が私の一家は、私が生まれた年に、その家からものの三十歩とはない隣地へ引越したと言ふ。
それ故、そこには竹籔がなかつた。がその代り三方を圍んだ桑畑と大きな榎の茂つた廣場があつた。
それで私のこころおぼえでは、幼ない時、私は竹籔が好きで、いつも附近の竹籔へ遊びに行つたものだつた。また憶ひ出す、それらは私自身によつて柳の聳えた竹籔や、幽霊の出る竹籔や、雀の多い竹籔や、狐の隠れてゐる竹籔などと呼ばれてゐたことを。そして私はかづ多いそれらのうち私が生れたと言ふ家の裏の竹籔がいちばん好きであつた。
それで私の少年時代は随分さびしかつた。
附近に家もあまりなかつたので、友達もなかつた。そのうちの数人は薄幸にも死んでいつた。私はいつもうすら寒い蜜柑の青葉の下で、竹の葉の搖れる音に耳を澄しながら、いろんなことを考へてゐた。
そしてそれは私に、さびしいと言ふことをなんとも思はない性質にしてしまつた。
私は竹籔のことを考へる、各々の竹籔がそのなかにいかにたくさんの物語を私のために語らうとしてゐるやうであることを。
そして、それにもかかはらず、私の、ものに無関心であることについては、私は竹一本の成長についても、私自身の成長と同じやうに、いつもぼんやりとしたものより知らないのである。
それに較べると風車のことでは、私自身がよりはつきりしてない。住んでゐた町から暫くはづれの方にゆくと、かなり激しい傾斜地がある。 それは恐らく一里ぐらゐは一直線につづいてゐるつもりである。
その傾斜地の上には随分異國的なものがあつた。
私は不幸にして、その上を通つたことはないが、傾斜地の下はしばしば通つた。
このごろはすつかり異つてしまつたが、その傾斜地のだんだん畑には、棉の畑や麻の畑があつた。
それから、坂の上の通りの裏にあたるあたりには白壁の師範学校があつた。三階建の和蘭商館があつた。黒塗の倉庫があつた。
そして、私の記憶に新なことには、そこにたつたこの都市(まち)に一つぎりの古風な風車があつた。
だが、私の言ふ風車とはその風車ではないらしい。それには私は餘り興味を持たないから。勿論、近來その附近の風致がひどくくづされて、 私がそこに行くことを怖れてゐると言ふ理由もあるが…………
私は結局、かやうなことに、いつもぼんやりすぎるのであらう。
私は、べつにその竹籔を、風車を思ふことによつて、印象を記憶を喚び起すのに神経質になることは出來ないから、またそれ故、いつまでも、ぼんやりした世界を苦労なしに考へることが出來る理由でもあらう。
私が詩を書くのは、そんな状態に於いてである。
それ故、私はいつも詩を書かうと思つて書いたことはない。従つて、詩を書くために特別の苦心などをしたこともない。私はそれゆえ、私のもつとも氣安げな時、さうだ、いちばん心の純粋な時、樂しくはればれて筆をとるのである。
私にとつては藝術と言ふものは、平凡な常識である。
由來、私の一家の風が示したものは、藝術的生活とか生活的藝術とかの異論を別にして、藝術と生活とが一致した生活であつた。それ故、私の一家は對社會とは没交渉な生活をしてたらしい。
私の父は、特に氣質の上にそうしたものが甚だしかつたらしい。
私は私が季(すえ)の子であつた故だらう、私は私自身のぼんやりしたもので考へてゐる外、私の家系のこと、父自身のこと、母自身のことに就いてはちつとも知らない。
あるひは幼ない時に聞かされたことがあつたかも知れない、が思ふにそれらのものは、父母が私に與へる最上のものではない。
寧ろ私は、父母が與へるに、世にも美しい生活をもつてしたことを幸福とする。
それ故、私はいつもそれをぼんやりと考へることに満足してゐる。
何故なら、さうすることが、私のいちばん好むところであり、恐らくは父母にとつても差支へないものであらうから。また、それほど、勝手に私の思ひどほりになるものも外にない故である。
私の知つてゐる範圍では、その頃、私の家の業であつた陶器に絵をつけると言ふ仕事は、いまとは思ひもよらない藝術的な仕事であつたらしい。
それで、職人と言ふものは随分苦心もしたし、随つて、随分立派な仕事をしたものであつた。
私の家にも幾人かのさうした人がゐた。
彼等は殆んどがそうであつたが、遠い山國から、十二三歳から甘歳までを年期として、総て都市へと奉公に來たものであつた。彼等は毎日陶土の出る山や、陶土を挽く水車小舎や、または赭い陶器竈の煙の下で、自分たちの手でつくられる陶器に、たつた一本の筆で自由に美しい繪を描いて生活すると言ふことは、さう言ふことを修業するために都市へ出ている師匠に就くと言ふことは、よほど立派なことだとかんがへてゐたのであつた。
私の生活は、さうした人達の雰圍氣のなかにあつた。
私は彼等が私を大切にし、また厳格で、しかも親しみ深い彼等自身の仕事をいかに忠実に、満足に果してゐたかを知つてゐる。
事實、彼等はかくして、彼等の師匠の知るすべてのことを習得し、立派な腕前となるばかりでなく、彼等自身また若い弟子を養ふに足る人格をこしらへるのである。
そして私は何故に必要以外にこんなことを書かうとするのか、實に、私の信じるところに依れば、かくして彼等のもつ生活がいかなる外の立派な生活に比しても劣らなく立派なものであるかと言ふことを言ひたいからである。
また私は、それがつひには私の一家の幸福を破壊したところの、近代の産業組織の罪悪を、また彼等をして人間以下へと堕しめてゆく苦痛の生活を知るゆえである。
いかにPrimitif(プリミチフ:※原始的)な人格の愛らしかつたこと、だが、それらは彼等とともにあれ、結局、私はそれらのものを今にかへさうとは思はない。
それは私が芭蕉について微笑するがごときものである。
私は私の生活をもつ。彼等と違つた意味で、私は私の信じる人格の成長にふさはしい生活に向ふのである。
かくて、私は私の詩に就いては、詩の古典のことも考へたくはない。また近代のさまざまの詩風についても同じである。
ただ、かかるが故に、私は私の詩に特別ななにものをも望まない、世に言ふ藝道とか匠氣とか言ふものを崇ばない、また私は粗雜な、真實のないものを疎んするものである。
私の父はいつも細い(それは何の毛でこしらへたものかは知らない)で竹林をさらさらと書いた。
それは父が幼ない私達に書き與へたものであるが、或日、私は父の所有(もつ)てゐた明治初年の和蘭陶器を見たことがあつてから(それは白耳義(※ベルギー)のものであつたかも知らない)私は異國のもののもつ不思義な雰圍氣を樂しむことを知つた。
私の中にある一つの世界は、かかるひまに私の裡に育まれたものかも知らない。私が風車を思ひ、美しい海を思ふのも、じつはそんなところにあるのかも知らない。
私の一家は、その後、それはもう数年以前のことになるが、彼等の新らしい田舎へとかへつてしまつた。そこは私がかりに故郷と呼んでゐるところである。
そして私は再び私の本來の孤獨に残された。私の詩の生活はそこに始まつたのである。
私はいつもその故郷を思ふ。そして私はそれを思ふとき、ふしぎに大きな原始の力をそのままに、根強く伸びた竹籔をおもふ。そこに幸福をとりかへした父母をおもふ。そして私は、私のなかに遠のいてゆく一つの世界を、あのやうに美しい世界をひたすらに歌ふのである。
春山行夫
(跋文)春山行夫と僕
「月の出る町」によせる
僕が春山行夫を知つたのは、そんなに昔のことではない。だのに僕らは生れおちるとから離ればなれに育てられ、生活してきた二人の兄弟が二十幾年の後、奇遇したかの心情を経験することになつた。
その頃、名古屋で起した宗教革新運動に興味をうしなひかけてゐた僕は、同志がまたそれぞれ宗教中心といふことに不自由を感じてゐることを知つたので、二號まで出した雜誌も廢刊にし、「宗教改革同盟」といふものも解散することにした。
その頃、福士幸次郎(人も知るように彼と僕とは兄弟關係に立つ。)が名古屋での詩歌講演のために來名した。(一九二二年二月のことだ。)
彼は「樂園」の創刊號を持つてゐた。(この若さそのものの詩中心の雜誌は僕が早稲田の文科にゐた頃、即ち四五年も前から計畫してゐてやつと、しかも予期せずに、その顔を見るものであつた。それを兄が弟にずつと昔に約束したものを弟が忘れた頃、不意に興へて喜ばせる快感から、福士はさうしたのであつた。)
僕の情熱は再び詩の世界に燃えたつた。僕が春山を知つたのは、これ以後三四ヶ月を過ぎてからのことである。
その頃、春山は、名古屋のある會社に勤めの傍ら、彼の竹馬の友、井口蕉花君ともに「赤い花」といふ雜誌を出してゐた。
ところが間もなく「樂園」も「赤い花」もともに廢刊か休刊かになつてしまつた。その春、高木斐瑳雄君から話があり、「赤い花」の連中と一諸に雜誌(※『青騎士』)を始めようと思つてゐるが加はつてくれないかといふのだ。
──僕と春山との友情・生活(フラテエツア・ヴイヴオ)はこれから始まつた。
春山は會社のかへりに、殆んど毎日のように、僕の東新町の假寓(いまもこれを書いてある)の扉をたたいた。
彼の姿が見えない夜は、僕が出かけて行つた。あのいかめしくたち並んでゐるブルヂョアの住宅におしつぶされさうな一間きりの裏座敷へ。
そしてこのどちらかの部屋で僕等は語りあつた。──英佛の象徴詩を、東洋の古典詩歌を。彼の書齋のボンボン時計が夜中の二時を打つたりして驚ろいて立ち上つたこともあつた。(が彼のドコか異國的な、それでゐて、祖先伝來と思はれるやうなその時計は、いつも二時間位はすすんでゐた。そして今もすすんでゐる。)
彼は風呂手拭を振り乍ら、またいつも風呂屋の前まで、おくつてきてくれた。あやつり人形の鋒鎗持ちの格好で(願はくば彼から一切の和服をとり去ることを!)。
人通りの少ない電車道から入つた、廣い屋敷町の月の出は変つてゐた。
その月は黄ろく疲れた顔を出した。どこか、文明のおとぎばなしのお姫様を思はせた。
“gisimilsalvirinoelirantaeltombo"(※それ[月]は墓から蘇った女性のようだ)などと「サロメ」の文句をエスペラントで口づさんでみたこともあつた。
が、春山はその月を僕と同じように眺めたのか、どうかは知らない。ともかくかかる月の出る町で、彼の隣りの門前で僕がウリーニ(※小便)したことだけは忘れてない筈だ。(かかる町ではまさに噴泉の趣興をそへる!)そして彼は僕にその家がポリつイステエヨ、マーストロ(※警察署長)の屋敷であることを警告したのだから。
彼の洋服姿が脇に二三冊の詩集をかかえて、廣小路のページメントの上をやや背をこめて足早に通りすぎるさまを見たものは、彼の脊高がいかに調和的な映畫の主題であるかを思ふであらう。
かかるとき、まさに彼のエキゾチシズムは、彼のボンボン時計の響とは全く異つた響と速度とを起す!
そしてまた折々僕とともに歩くのだが、僕の黒いトンビに山高帽姿(これはポオを失神させたレエヴン(※Raven大鴉)である)は彼の文明のものの姿としていかに野人くさく見えることであらう。彼の言ふがごとく村長の赤毛布ぶりといふところであらう。
しかり、彼は文明人型であり、僕は野蠻人型である。「青騎士」同人のすすめによつて僕は五六年間の詩の一部を一九二二年十月に發表したのだが(※『晴天』)、彼は僕が五六年の間に開拓した詩歌の分野を僅か五六ヶ月で自分のものにしてしまつた。そして彼の豊かな天分は、なほ彼獨自の世界をあまた探索、開墾しつつある。
彼こそはまさに出藍の天才であらう。が僕はダヴィンチがラファエルに對して抱いた嘆をいままたくりかへしはしない。むしろよき才を弟に持つた兄の喜びが僕の胸をしめてゐる。
ただ彼があまりに文明人であることによつて、彼の將來に多少の杞憂を抱きつつ、一世紀にごくまれにあらはれることをゆるされるであらう天才の選詩集を世におくることに、誇りと喜びを持つものである。
一九二四年三月十六日
日曜日の晝、田舎の家でかきをはる
佐藤一英