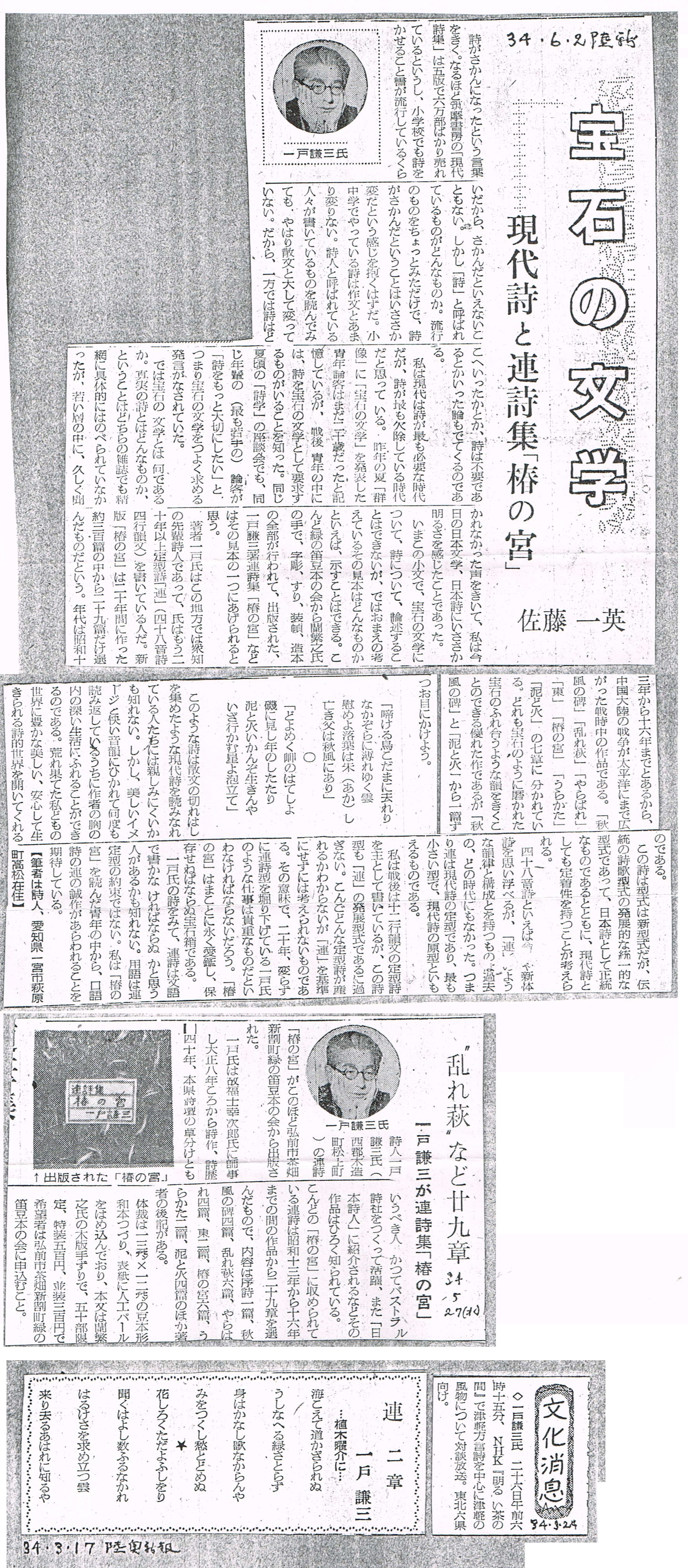(2021.11.26up / update) Back
いちのへ けんぞう【一戸謙三】(1899〜1979)
書評
宝石の文学 現代詩と連詩集『椿の宮』 佐藤一英 『陸奥新報』1959.6.2
詩がさかんになったという言葉をきく。なるほど筑摩書房の「現代詩集」は五版で六万部ばかり売れているというし、小学校でも詩を書かせることが流行しているくらいだから、さかんだといえないこともない。しかし「詩」と呼ばれているものがどんなものか。流行のものをちょっとみただげで、詩がさかんだということはいささか変だという感じを抱くはずだ。小中学でやっている詩は作文とあまり変りない。詩人と呼ばれている人々が書いているものを読んでみても、やはり散文と大して変っていない。だから、一方では詩はどこへいったかとか、詩は不要であるとかいった論もでてくるのである。
私は現代は詩が最も必要な時代だが、詩が最も欠除している時代だと思っている。昨年の夏「群像」に「宝石の文学」を発表した青年論客はまだ二十歳だったと記憶しているが、戦後青年の中には、詩を宝石の文学として要求するものがいることを知った。同じ夏頃の「詩学」の座談会でも、同じ年輩の(最も若手の)論客が「時をもっと大切にしたい」と、つまり宝石の文学をつよく求める発言がなされていた。
では宝石の文学とは何であるか。真実の詩とはどんなものか、ということはどちらの維誌でも精網に具体的にはのべられていなかったが、若い層の中に、久しく聞かれなかった声をきいて、私は今日の日本文学、日本詩にいささか明るさを感じたことであった。
いまこの小文で、宝石の文学について、詩について、論述することはできないが、ではおまえの考えているその見本はどんなものか、といえば、示すことはできる。こんど縁の笛豆本の会から蘭繁之氏の手で、字彫、すり、装幀、造本の全部が行われて、出版された、一戸謙三詩集「椿の宮」などはその見本の一つにあげられると思う。
著者一戸氏はこの地方では衆知の先輩詩人であって、氏はもう二十年以上定型詩「連」(四十八音詩四行韻文)を書いている人だ。新版「椿の宮」は二十年間に作った約三百篇の中から二十九篇だけ選んだものだという。年代は昭和十三年から十六年までとあるから、中国大陸の戦争が太平洋にまで広がった戦時中の作品である。「秋風の碑」「乱れ萩」「やらばれ」「東」「椿の宮」「うらかた」「泥と火」の七章に分かれている。どれも宝石のように磨かれた、宝石のふれ合うような韻をきくことのできる優れた作であるが「秋風の碑」と「泥と火」から一篇ずつお目にかけよう。
啼ける鳥こだまに去れり
なかぞらに薄れゆく雲
慰めよ落葉は朱(あか)し
亡き父は秋風にあり
〇
どよめく岬のはてしよ
磯に見し年のしたたり
泥と火いかんぞ生きんや
いざ行かむ星よ泡立て
このような詩は散文の切れはしを集めたような現代詩を読みなれている人たちには親しみにくいかも知れない。しかし、美しいイメ一ジと快い音韻にひかれて何度も読み返しているうちに作者の胸の内の深い生活にふれることができるのである。荒れ果てた私どもの世界に豊かな美しい、安心して生きられる詩的世界を開いてくれるのである。
この詩は型式は新型式だが、伝統の詩歌型式の発展的な統一的な型式であって、日本詩として正統なものであるとともに、現代詩としても定着性を持つことが考えられる。
四十八音詩といえば今や新体詩を思い浮べるが、「連」のような韻律と構成とを持つものは過去の、どの時代にもなかった。つまり連は現代詩の定型であり、最も小さい型で、現代詩の原型ともいえるものである。
私は戦後は十二行韻文の定型詩を主として書いているが、この詩型も「連」の発展型式であるに過ぎない。こんごどんな定型詩が産れるかわからないが「連」を基準にせずには考えられないものである。その意味で、二十年、変らずに連詩型を堀り下げている一戸氏のような仕事は貴重なものだといわなければならないだろう。「椿の宮」はまことに永く愛鑑し、保存せねばならぬ宝石箱である。
一戸氏の詩をみて、連詩は文語で書かなければならぬかと思う人があるかも知れない。用語は連定型の約束ではない。私は「椿の宮」を読んだ青年の中から、口語詩の連の誠作があらわれることを期待している。
【筆者は詩人、愛知県一宮市萩原町高松在住】
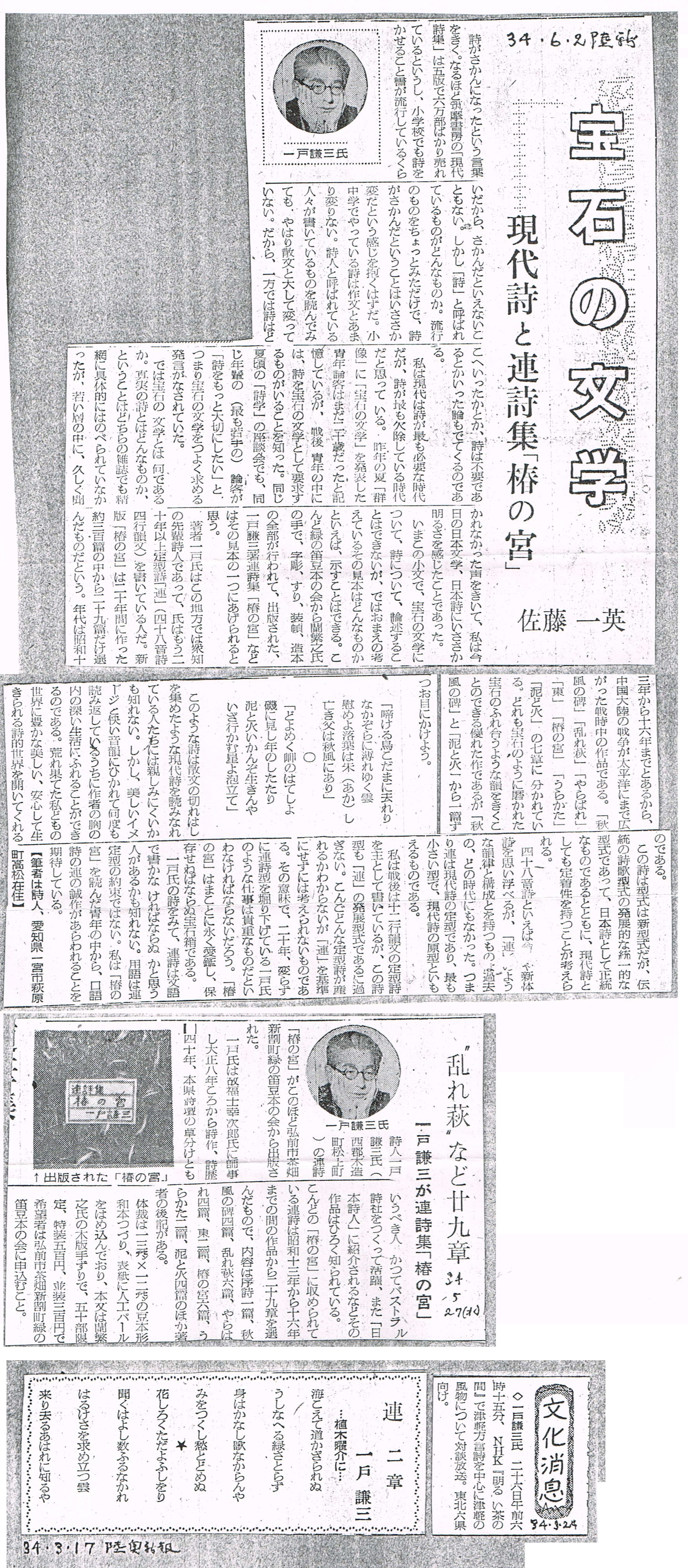

Back