 昭和6年4月(後ろは安田講堂) クリックで拡大します。
昭和6年4月(後ろは安田講堂) クリックで拡大します。「コギト」 創刊號(昭和7.3) ~ 145號 (昭和19.8) コギト発行所 肥下 恒夫刊行。
今更に「コギト」の紹介を書く、しかも例へば初めてここへ訪れて(迷ひ込んで?)来た、現代詩に興味があるといふばかりの人達に分かり易く、 となると、どんな風に説明したらよいものなのだらう。自信がない。
「あれは戦争に協力した文学者集団が若い日に興した反動的な同人雑誌にすぎない」
といふ文脈で、弾劾まがひの文章が、一昔前ならば文壇でも学術界でも普通に罷り通ってゐた時代がありました。
テレビ・新聞のジャーナリズムでリベラル良識を培ってきた一般の人には、その方が分かり易く、文学研究者にとっても、
かつて文学が面してゐた状況を高みから反体制的に総括することで、見識が一段上がったやうに感じられた、
さういふ時代が戦後のつい最近まで続いてゐたのです。若い批評家達はさぞかし「紅衞兵の気分」を味はったことでしょう。そして当時晩年に差し掛かった文学者の多くは、戦時中に関はった所業について洞ヶ峠を決め込み、保身の為に「コギト」および「日本浪曼派」を「踏絵」のやうに踏んで見せてきたのでした。
ここで単に「コギト」といふ雑誌の沿革をお話したところで仕方がありません。もう少し続けさせて下さい。
さて、今では「何故文学をするのか」といふ問ひに対して、世界平和のためであるとか、有名になりたいからとか、
本音のところ生活のためとか、ただ素直に好きだからとか、様々に答へることができますが、つまりはモチベーションが自由に保証されてゐる時代です。むしろ重要なのは「対象」や「装ひ」が時代遅れではないかどうか、「何を」「どんな風に」の一点かもしれません。
しかしここに「何を」でも「どんな風に」でもなく、「何故」といふ動機をのっぴきならないモチベーションとして掲げ、明快な解答を見出せぬまま暗闇の時代を前のめりの姿勢で突き進まざるを得なかった一群のグループとして「コギト」の人々がありました。
彼等は暗闇の中で躓きます。所謂戦争協力の問題です。それを当事者が居なくなった今、あらためて眺め直してみようと、つまり彼等の様相を当時の歴史的な状況に立ってとらへ直し、その発生や変態の必然が意味するところに、現在どんな反省が汲み取られるのだらうかと、
私は自分の好きな抒情詩の背景に広がる政治的な問題について関心を寄せるやうになりました。
過度の豊かさの元で生活してゐる事さへ自覚できなくなった一方で、国際社会は再びキナ臭い方向に向かひつつある現代です。「何故文学をするのか」はイロニーとしてすぐれて今日的な命題でもあるとも云へませんか。
そしてその問ひに答へることができなかったならば、私達は再び同じやうな轍を踏む愚を、後世の批評家から受けることになるのではないでしょうか。
抒情詩を愛する立場から、その作業は反省を他者に突きつける類のものではなく、 彼等の意志を時代相から救ひ上げるものへと凝り、追体験すればするほど鎭魂の心情から離れられなくなりました。
「コギト」とは、デカルトの謂ふ「cogito ergo sum我思ふ故に我あり」に
おける「内省する自我」を指す言葉であると解釈されます。
良心に基づく純潔を核に据ゑた彼等の抒情の特徴は、時代の混乱のなかで旗印に掲げた「何故自分たちは文学をするのか」一点に集約的に顕れてゐます。
彼等が文学的出発をする前夜の昭和初年の文壇状況といふのは、「何のために」と革命が語られ、「どんな風に」とモダニズムの可能性が試される、
同人誌が乱立して文学的青春の謳歌が保証された時代でありました。
双方はやがてモチベーションを書き手であるおのれの中にではなく、文学の効用や手段といった外部に求めていったのですが、
元々は彼等もまた「何故文学をするのか」の問ひについて、片や社会的不正義に対する怒り、片や冗漫な主観垂れ流しに対するプロテストとして良心が命じた革新運動でありました。
それが社会の変容に伴ひ、一方は有無を言はさず当局に潰され、一方は権力とは無縁の場所に逼塞していった、そんな具合に青春が清算されてゆく落日の中においてでした、当時高校時代に主宰してゐた短歌雑誌「炫火・かぎろひ」の同人を中心に、大学生になったクラスメートたちが鳩合して新たに文藝同人誌を創刊しようと考へたのは。
創刊宣言は大変勇ましく高踏的なものです。
「私らは古典を殼として愛する それから私らは殼を破る意志を愛する」
編集後記の最後に添へられたこの言葉には、共産主義の理想を否定する帝国主義の体制が、今後我々をも否応無しに引きずって進んでゆくだらうといふことへの危機感を踏まへ、
ならばこちらも素養としてあった古典の知識を盾として身に強固に纏ひ、風上に立つその詩精神の純潔が命ずるまま、
体制が意図するよりもさらに強い過激なやり方で自分達の意志をぶつけてやる。そして体制やそれに尤らしく追隨する俗人文学者に潜んだ「生半可な姿勢」や「嘘」を、反対にこちらから暴きたててやるのだといふ、
彼等が選択した文学上の方法、所謂「イロニー」の芽生えが注意深く表はされてゐます。さうする以外には自分達の根底にある文学の動機を純粋に保つことができないと判断したからです。
「四季」が知的操作の点ばかりでなく、政治への不干渉といふ態度においてモダニズムとの情な緒的隣接を色濃く残してゐるとするならば、
「コギト」が往々プロレタリア文学との関係において語られるのは、さういふ文学の動機面において高見順が云ったやうな、
正義に拘らずにはをれない「ひとつの根」を両者が胚胎してゐたからと云へるでせう。
若干の世代的な相違が彼等を直接的な反抗と屈折した呪詛へとの色分けをしたのです。
若輩の彼等に向けられた先輩たちからの批判を、「コギト」のリーダーであった批評家、保田與重郎の韜晦する文体は巧みにかはし、跳ね返してゆきます。一方、伊東静雄や田中克己などコギト同人の詩人達の詩作品は、精神の「危機の場所」を歌ふことで輝きを帯びてゆきます。
つまり一人の卓越な批評家と、同志ともいふべき周辺の詩人達との「共同の営為」の関係の中で、「コギト」は日本の文学史に対して独自の主張をしはじめるのです。
しかし結果として、先輩達(プロレタリア詩人達)は潰され、後輩達(コギト同人達)は動機を韜晦したまま、やがて体制の右傾化が増すに連れ過激が過激に感じられなくなってしまふ、
それ自体イロニックな政治状況のうちに解消し、自然な形で戦争にも賛同することとなってゆきます。
戦争への憎しみを、被害者として批判し続けてきた「コギト」次世代の若い批評家達の心情は、理解はできるものの、すでに21世紀を迎へた今、「孫世代」以降にあたる私達にとって、 あのやうな時代を生んだ「必然」を直視することは、そのまま短絡的に具体的な憎しみへと繋がるものではありえません。 しかしながらまた、それを与り知らぬ知識として受け継ぐのではなく、鎮魂の意を以て動機を救ひ上げたいとの思ひが私にはあります。
「何や、カッコつけたこと云うとるな。つまり校則がどんどん厳しなる学校で、生徒会に入って先生の不倫を吊し上げたれ、みたいなことか? わからんわ。御託抜きで簡単に教へてんか、コギトって何やのん?」
大阪高等学校同窓生が昭和7年に始めた文藝同人雑誌です。終戦間際の雑誌統合で廃刊となるまで計145号が発行されました。
主な創刊同人は、保田與重郎、肥下恒夫、田中克己、中島栄次郎、松下武雄、小高根太郎、杉浦正一郎、服部正己、薄井敏夫、松田明、石山直一ら。 昭和10年代に一世を風靡した保田與重郎の文芸評論を中心に据え、抒情詩人の伊東静雄が主要作品を発表した雑誌としても名高い。外部からの同人を迎へ、 「四季」他からも多くの寄稿者が往来し、昭和十年代を通じて日本のロマン主義文学の拠って立つ代表的な文藝雑誌として機能しました。 非営利雑誌としての資金確保を可能にしたのは、同人中の素封家であった肥下恒夫の文学上の友情に賭ける情熱によるものでした。
「まぁええわ。ほんで下が創刊当時の写真とか? 気張ってまんな。大阪からけんか売りにきたちうわけやな。」
といふか(汗 笑)。なんやかや威勢よく見えても、結局人情のオチ(サゲ)を大切にする心弱き文学青年達のあつまりであるわけです。当事者たる田中克己の回想はこちらで。
「さよか。」

昭和9年1月、大阪高校同期生(帝国大学図書館前にて)クリックで拡大します。

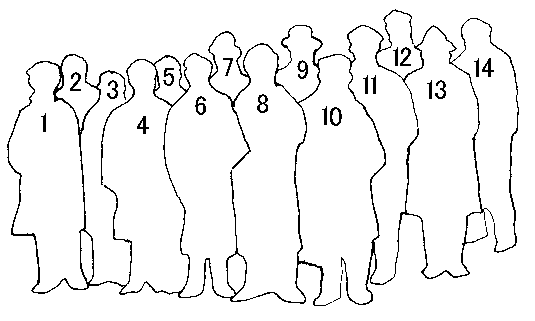
01 :田中克己
02 :長野敏一
03 :薄井敏夫
04 :紅松一雄
05 :山田鷹夫
06 :鎌田正美
07 :保田與重郎
08 :山本治雄
09 :井上[木+參]しん
10 :原田運治
11 :藤田久一
12 :丸三郎
13 :肥下恒夫
14 :友眞久衛
青色はコギト同人